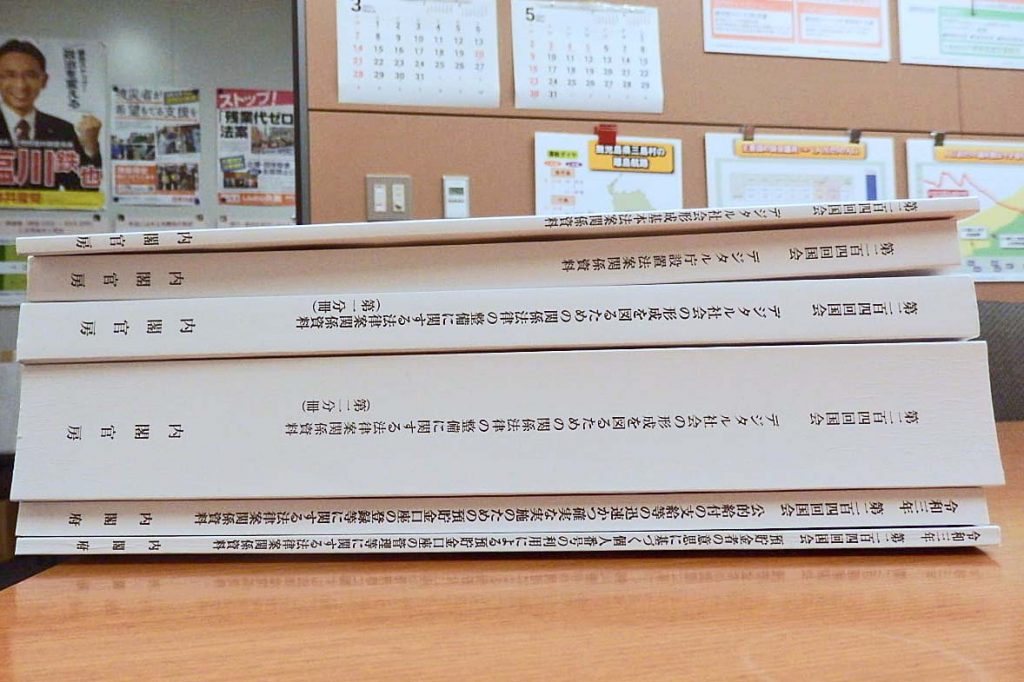衛星放送WG職員に集中
 菅義偉首相の長男、正剛氏が勤務する放送関連会社「東北新社」の総務省接待をめぐり、同社の接待の大部分が衛星放送に関する同省のワーキンググループ(WG)の事務方職員に対して行われ、東北新社にとって有利な内容を盛り込んだWG報告書案が作成される期間に集中していたことが明らかになった。一連の接待攻勢で、東北新社に有利になるように行政がゆがめられたと告発しました。
菅義偉首相の長男、正剛氏が勤務する放送関連会社「東北新社」の総務省接待をめぐり、同社の接待の大部分が衛星放送に関する同省のワーキンググループ(WG)の事務方職員に対して行われ、東北新社にとって有利な内容を盛り込んだWG報告書案が作成される期間に集中していたことが明らかになった。一連の接待攻勢で、東北新社に有利になるように行政がゆがめられたと告発しました。
同省の検討会「衛星放送の未来像に関するWG」は2018年5月の第5回で、衛星放送への新規事業者の参入を拡大する報告書案を取りまとめました。新規参入枠をつくるため、東北新社を有力企業とする衛星放送協会は、電波の周波数の帯域幅(スロット)で42スロットを自主返納。東北新社も6スロットを自主返納しました。
私は、18年報告書案後に東北新社から接待を受けたWGの事務方職員の数・回数などをただしました。
同省の原邦彰官房長は、WGが再始動する第7回までに東北新社が行った接待21回のうち、WG事務方職員が参加したのは19回と答弁。2回目の報告書案が出される第12回までの接待28回のうち26回がWG事務方へのものであることを明らかにしました。
私は、同社の接待がこの時期に集中していると指摘し、その結果、WGが新たにまとめた報告書案には、BS右旋帯域の4K放送を認めることや、衛星の利用料低減が盛り込まれたと指摘。長男が勤務する東北新社と特別の関係にある菅首相の存在が行政をゆがめる大本にあったのではないか、と追及しました。
菅首相が「総務省の中でしっかり検証している」と言い逃れたのに対し、私は東北新社社長が菅首相に対して今回問題となっている18年10月にも献金を行っていたと指摘。菅首相がこれまで述べてきた「総選挙の応援」という理屈は成り立たないと強調し、贈収賄も問われる疑惑であり徹底解明が必要だと迫りました。
衆議院TV・ビデオライブラリから見る
【論戦ハイライト】接待攻勢で東北新社の要望に沿う/疑惑の徹底解明を/衆院予算委/塩川議員が追及
 「しんぶん赤旗」3月1日・2面より
「しんぶん赤旗」3月1日・2面より
菅義偉首相の長男、正剛氏が勤める放送関連会社「東北新社」による総務省幹部への接待問題。1日の衆院予算委員会での日本共産党の塩川鉄也議員の追及で、東北新社が衛星放送に関する検討会の総務省事務方職員に接待攻勢をかけ、放送行政がゆがめられた疑いが浮き彫りになりました。
焦点となっているのは、総務省の検討会「衛星放送の未来に関するワーキンググループ(WG)」。小林史明政務官が座長として2018年5月にとりまとめた報告書案は、衛星放送への新規参入の拡大を求めるもので、既存事業者の東北新社に厳しい内容でした。
塩川氏は、接待を報じた週刊誌報道では「BSのスター(チャンネル)がスロット返して」「俺たちが悪いんじゃなくて小林が悪いんだよ」「どっかで一敗地に塗(まみ)れないと」などの会話が報じられていることを紹介。東北新社がスロット(電波周波数の帯域幅)を自主返納したのは総務省の強い要請と将来の見返りを期待してのもので、その後、WGを再始動させ新たな報告書をつくるため、同社がWGの総務省事務方へ接待攻勢をかけている姿を浮き彫りにしました。
10人中6人
塩川 新たな論点整理の場として再開された第7回WGの総務省事務方10人中、東北新社と会食した職員は誰か。
原邦彰・総務省官房長 吉田真人情報流通行政局長ら6人だ。
小林政務官のもとで報告書案を取りまとめた第5回WGには当時情報流通行政局長だった山田真貴子内閣広報官、再始動した第7回WGには総務省事務方トップで情報流通行政局長だった吉田総務審議官、新たな報告書を取りまとめた直前の第11回WGには谷脇康彦総務審議官も出席。いずれも東北新社の接待を受けていました。
塩川氏は、WGの新しい報告書案では、これまで認められなかった右旋帯域への4K化や衛星放送利用料の低減など、東北新社が有力企業である衛星放送協会の要望に沿った内容に変わったとして、次のようにただしました。
塩川 一連の接待攻勢によって、東北新社に有利となるように行政がゆがめられたのではないか。
武田良太総務相 現段階ではゆがめられた事実はない。国民から疑念の目を向けられることとなっており、検証するよう改めて指示を出した。
調査不十分
塩川氏は、正剛氏の影響は「確認できなかった」とする接待問題に関する同省調査で、吉田真人氏が情報流通行政局総務課長着任以降に東北新社と3回程度会食を行った記憶があるとしている点をあげ、次のようにただしました。
塩川 3回の会食の際、東北新社側で菅正剛氏が同席していたことは覚えているか。
吉田 木田由紀夫氏が相手側でいた記憶はある。菅氏が同席した回もあったやに思う。
塩川氏は、総務省の調査では不十分だとして、疑惑の徹底解明を求めました。
「議事録」
<第204通常国会 2021年3月1日 予算委員会 17号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
今日は、総務省接待問題について質問をいたします。
きっかけとなった週刊文春の報道では、昨年十二月十日の東北新社と秋本局長の会食の会話が紹介をされております。
菅正剛氏が、BSのスターがスロットを返している。木田氏が、俺たちが悪いんじゃなくて小林が悪いんだよと。秋本局長は、うん、そうだよということを踏まえて、秋本局長は、小林氏のことを念頭に、でも、どっかで一敗地にまみれないと、全然勘違いのままいっちゃいますよねと。こういうやり取りがあったということが紹介をされ、秋本局長もそのことを認めておりました。
BSのスターというのは、東北新社のスターチャンネルのことであります。スロットというのは、放送事業を行う場合の電波の周波数の帯域幅のことであります。小林氏とありますのは、小林史明当時の総務大臣政務官のことで、このやり取りにあるのは、二〇一八年五月の衛星放送の未来像に関するワーキンググループで取りまとめた報告書の内容にも関わるものであります。
総務省に確認をいたします。
この小林史明政務官が中心となったワーキンググループの報告書は、新規参入を拡大することを求める内容でした。
二〇一八年の十一月、東北新社を有力企業とする衛星放送協会は、四十二スロットの自主返納を決め、総務省に報告をしました。東北新社も、BS放送のスターチャンネルのスロットの一部を自主返納した。これは、そのとおりですね。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
二〇一九年十一月に認定されましたBS放送の新規参入事業者などの放送開始に向け、現在、BS右旋帯域において帯域再編作業が進められておりますが、その再編作業の中で、スロットの縮減を行った事業者がいます。
株式会社スター・チャンネルにおいても、スターチャンネル1、スターチャンネル2、スターチャンネル3のスロットの縮減が二〇二〇年十一月三十日に行われております。
これらのスロット縮減は、各社が経営判断に基づき行ったものでございます。
〔委員長退席、山際委員長代理着席〕
○塩川委員 この二〇一八年の五月の報告書の中身に関わって、既存の衛星放送事業者にとっては、4Kを推進している中、4K推進に協力している既存事業者を差しおいて、なぜ4Kではない新規事業者を増やすのかということだったのではないか。しかし、総務省側の強い要請もあり、厳しい経営環境を打開するためにも、将来の見返りを期待しての自主返納だったのではないか。そこで東北新社は衛星放送の未来像に関するワーキンググループの総務省事務方への働きかけを強めたのが、その後の接待攻勢だったということではないでしょうか。
総務省に確認しますが、この二〇一八年五月の第五回衛星放送の未来像に関するワーキンググループの総務省の事務方、出席は十人でしたが、その十人について、その後、東北新社との会食に出席した職員は誰か、お答えください。
○原政府参考人 お答えいたします。
衛星放送の未来像に関するワーキンググループ第五回の総務省出席者のうち、今回の総務省調査において東北新社との会食が判明したのは、当時の役職で申し上げますが、奈良大臣官房審議官、湯本放送政策課長、井幡衛星・地域放送課長、豊嶋情報通信作品振興課長の四名でございます。
○塩川委員 三島さんについてはどうですか。
○原政府参考人 お答えします。
失礼いたしました。三島も入っております。
○塩川委員 このときの情報流通行政局長は山田真貴子さんなんですけれども、それはそのとおりですね。それは何で入っていないんですか。
○原政府参考人 お答えいたします。
今回、総務省の調査で判明いたしましたのは、現職の職員ということでございます。山田広報官、もうお辞めになられましたが、当時情報流通行政局長でありましたが、今回の総務省の調査ではないということで、総務省の調査では先ほど申し上げたということでございます。
○塩川委員 当時でも山田さんそのものだったわけですから、つまり、この第五回のワーキンググループの総務省事務方、出席している十人のうち六人が東北新社への会食に参加をしているということであります。
次に聞きますが、昨年四月には、休止をしていたこのワーキンググループが再開をしました。十二月に再び報告書をまとめました。この昨年四月、新たな論点整理の場として再開された第七回ワーキンググループの総務省事務方十人中、東北新社との会食に名前を連ねていた職員は誰でしょうか。
○原政府参考人 お答えいたします。
第七回ワーキンググループ、これも当時の役職で申し上げますが、吉田眞人情報流通行政局長、湯本情報流通行政局総務課長、豊嶋情報通信政策課長、井幡地上放送課長、三島情報通信作品振興課長、吉田恭子衛星・地域放送課長、六名でございます。
○塩川委員 第七回についても、十人中六人、やはり過半数が東北新社と会食を行っております。昨年四月に再開したワーキンググループの総務省事務方トップは、情報流通行政局長だった吉田眞人現総務審議官であります。新たな報告書取りまとめの直前である昨年十一月の第十一回ワーキンググループには、谷脇康彦総務審議官も出席をしておりました。
重ねて聞きますが、小林政務官の下で報告書を取りまとめた二〇一八年五月から、再度ワーキンググループが立ち上がった二〇二〇年四月の間で、総務省職員が東北新社と会食をした回数は何回で、そのうちワーキンググループの事務方経験者の会食回数は何回だったのか、この点を確認します。
○原政府参考人 お答えいたします。
今回の調査において判明した東北新社との会食のうち、御指摘の期間に係るもの、これは一回の会食に複数の職員が出席した場合一回とカウントしておりますが、第五回から第七回は二十回でございました。このうち、ワーキンググループに一回でも出席した者の参加した会食は十八回ということでございます。
○塩川委員 ですから、一度出した報告書の第五回のワーキンググループから、再開をして新たな報告書を出すそのタイミングとなった二〇二〇年の四月の段階、その間に二十回の会食がある。二十回の会食のうち総務省の事務方が参加していたのが十八回。
これには山田さんは入っていませんよね。入っているとしたら、加えたら一個増えるということですね。
○原政府参考人 お答えいたします。
総務省の調査ということでございますので、山田さんは入ってございません。
○塩川委員 ですから、山田氏を加えれば二十一回中十九回であります。
今回判明した接待のほとんどが、この時期に集中をしている。東北新社は、衛星放送の未来像に関するワーキンググループの事務方ばかり会食に誘っているということが、ここの実態に明らかではないでしょうか。
その後も会食を重ねて、十二月までには二十七回。そのうちワーキンググループの事務方経験者との会食が二十五回。これに山田氏を加えたら、二十八回中二十六回ということになるわけであります。
その結果取りまとめられた昨年十二月の報告書では、BSの右巻きの帯域の4K放送への割当てや、総務省が衛星の利用料金の低減を積極的に進めるといった取りまとめが行われました。これらは、東北新社が有力企業となっている衛星放送協会の要望、右回りの帯域への4K化の希望や、衛星放送利用料金の低廉化に沿ったものであります。
総理にお尋ねします。こういった一連の接待攻勢によって、東北新社に有利となるように行政がゆがめられたのではありませんか。お答えください。
○武田国務大臣 改めて、今回、行政そして国家公務員に対する多くの疑念を生むことになりました。心からおわび申し上げたいと思います。
調査チームの報告によれば、現段階までに全ての当事者の方々から複数回にわたりヒアリング等の調査を行ったその結果でありますけれども、現段階では、行政をゆがめられたという事実というものは確認できておりませんが、今回の事案により、衛星基幹放送の業務の認定そのものに対して国民から強い疑念の目が向けられることとなったことを重く受け止めております。
このため、新谷副大臣をヘッドとする検証委員会を早急に立ち上げて、過去の衛星基幹放送の認定プロセスについて、実際の意思決定がどのように行われたのか、行政がゆがめられるといった疑いを招くようなことがなかったかについて検証するよう、改めて指示を出しました。
検証委員会は、客観的かつ公正に検証いただけるよう、第三者の有識者に構成員となっていただく予定であります。検証内容や方法などについても、有識者の方々の御意見も踏まえながら検討いたします。
国民の信頼を取り戻せるよう、できるだけ早急に対応してまいりたいと考えております。
○塩川委員 認定の問題だけじゃないんですよ。
今指摘をしたように、BSの右巻き帯域への4K化の希望とか、衛星放送利用料金の低廉化とか、こういうことがどうだったのかについて検証しなければいけないのに、検証委員会にそういう中身は入っていないじゃないですか。
倫理規程違反に問われる段階ではなくて、贈収賄といった汚職が問われる問題であり、徹底解明が必要であります。
総理にお尋ねします。
東北新社と会食した職員は他の衛星事業者との会食はなかったといいます。なぜ総務省は東北新社だけを特別扱いするのか、それは菅総理の存在があるからではないでしょうか。東北新社からすれば、総務大臣経験者の菅義偉議員の息子であり、総務大臣政務秘書官を務めた菅正剛氏を採用することによって、総務省とのコネ、接点を使うことができるし、総務省から忖度が生じる。
また、東北新社社長親子から菅議員は五百万円の政治献金を受け取っておりました。総選挙の時期に献金を行っただけではありません。二〇一二年、一四年、一七年の総選挙の時期ではない、総選挙のない二〇一八年十月にも献金がありました。この時期は、今取り上げたように、ちょうど東北新社が衛星放送行政を自社に有利となるように総務省幹部と会食を重ねてきたときであります。東北新社と特別の関係がある菅総理の存在が、行政をゆがめる大本にあったのではありませんか。
〔山際委員長代理退席、委員長着席〕
○菅内閣総理大臣 いずれにしろ、総務省の中でしっかりと検証しているんじゃないでしょうか。そうしたことを徹底して検証すべきことだというふうに思います。
○塩川委員 いや、検証のそもそもテーマが問題なのに、そもそも菅総理の存在が行政をゆがめる大本になったのではないのかと。菅氏の身内の話、そして、この献金の時期というのも、まさに問題となっている時期ではありませんか。そのことについてきちっとお答えください。
○菅内閣総理大臣 私は、法律に基づいてしっかり手続をしております。ですから、私の存在がいろいろなことにということでありますけれども、そうしたことは私はないと思います。
○塩川委員 政治家の意向を忖度するような今の行政の在り方の大本に菅首相の人事介入の問題がある、このことも極めて重大だ。このことを指摘をして、質問を終わります。
 デジタル関連5法案、法案資料の計45カ所の誤りについて国会にも国民にも知らせず放置していたとして政府の責任を追及。大本に『菅首相の看板政策だからとにかく早く進める』という拙速な対応があったからではないか。そのことへの反省がまず必要だ、とただしました。
デジタル関連5法案、法案資料の計45カ所の誤りについて国会にも国民にも知らせず放置していたとして政府の責任を追及。大本に『菅首相の看板政策だからとにかく早く進める』という拙速な対応があったからではないか。そのことへの反省がまず必要だ、とただしました。