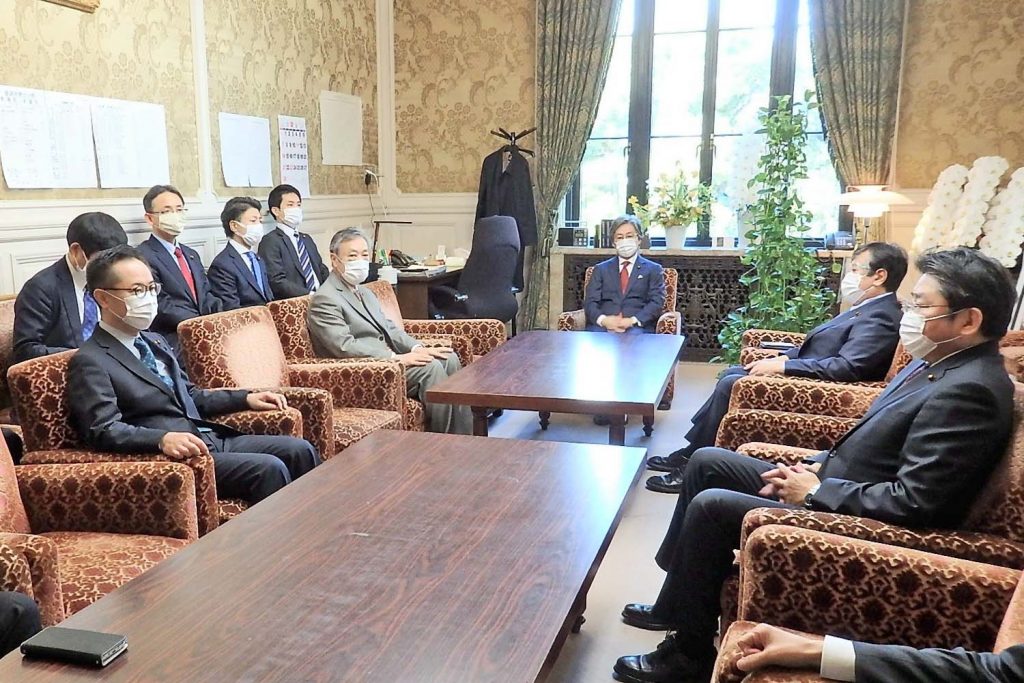総務省幹部が放送事業会社「東北新社」に勤務する菅義偉首相の長男・正剛氏らから接待を受けていた問題について、事実関係をただしました。
総務省幹部が放送事業会社「東北新社」に勤務する菅義偉首相の長男・正剛氏らから接待を受けていた問題について、事実関係をただしました。
私は、総務審議官当時に1人あたり7万4千円の接待を受けていた山田真貴子内閣広報官の会食の内容について質問。
加藤勝信官房長官は「和牛ステーキ、海鮮料理などが提供された」とはじめて明かし、「(参加人数5人の会食の)合計額が37万1013円と確認できた」と述べました。
また、私は、総務省の調査結果は山田氏本人が東北新社側と連絡を取って報告したものであり、自分が関わる事件を自分が調査して報告するなんてありえない、と批判しました。
加藤官房長官は、「山田氏は総務省を退職しており、特別職の国家公務員は公務員倫理法の対象外である」と答弁。
私は、政策立案過程に関与する特別職に倫理法令がないことは問題だと主張しました。
また、他の事業者との間に同様の接待はなかったとする総務省の調査結果について、総務省幹部が歴代にわたって東北新社とだけ会食を重ねている。『特別扱い』はなぜなのか、と迫りました。
総務省の阪本克彦政策立案総括審議官は「この場で即答できない」などとして明らかにしませんでした。
私は、接待の背景に、総務相秘書官を務めた正剛氏と総務省幹部との“特別な縁”があると強調。
また、身内の特別扱いと官僚の忖度(そんたく)という構図は森友・加計学園疑惑と全く同じ構図だ、と厳しく批判。山田氏と総務省幹部ら4人、正剛氏を含む東北新社関係者の国会招致を求めました。
「議事録」
<第204通常国会 2021年2月24日 内閣委員会 5号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
内閣委員会の質疑に入らせていただきます。
今日は、国家公務員制度、公務員の倫理法令に関わってということで、総務省の接待問題をまず質問したいと思っております。
しかしながら、この理事会におきまして、私が要求をいたしました総務省の谷脇氏、吉田氏、秋本氏、湯本氏、その国会出席が与党の反対で認められなかったというのは極めて認め難いことだと言わざるを得ません。予算委員会にも出席をしている秋本、湯本氏も出さないというのは一体どういうことなのか。まさに内閣委員会が国家公務員制度、公務員の倫理法令を所管しているというのであれば、当然、具体の事例として総務省の接待問題を議論するのは当たり前のことであって、それを拒否する与党の姿勢は極めて認め難い、断固抗議をするものであります。
そこで、まず総務省にお尋ねをいたしますが、月曜日、二十二日に総務省から出されました倫理規程に違反する疑いがある会食一覧についてお尋ねをいたします。
ここで名前が挙がっている職員については、衛星放送行政を担う歴代局長や課長らが連続して接待を受けていた、こういうことを示していると思いますが、確認です。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
そういったものに関係している職員がそこに掲げられております。(塩川委員「もう一回」と呼ぶ)
○木原委員長 もう一度、大きな声で明瞭に御発言ください。
○阪本政府参考人 はい。
お答えいたします。
そのような担当をしておる、あるいは、おった職員が挙げられていたところでございます。
○塩川委員 少なくとも、情報流通行政局長あるいは情報流通行政局担当の官房審議官、衛星・地域放送課長などについては、若干欠けているのもありますけれども、三代にわたって名前が出ているというのが実態であります。
次に、東北新社は三十八件全てで会食の費用を負担したと述べている、これはそのとおりですね。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
それぞれ、一応、会食につきましては、それぞれ会費につきまして、東北新社の方でもお支払いいただいているというふうに承知しています。
○塩川委員 いや、東北新社に確認をして、東北新社側は全て負担をしていると述べていたのではありませんか。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
東北新社側の方で負担していただいていると承知しております。
○塩川委員 だから、秋本さんが一部負担をしていたと言っていたというのは事実と異なるということですね。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
自己負担分につきましては、現在精査しているところでございます。
○塩川委員 この点でも秋本氏にはしっかりとおいでいただいて、本人からこの点についての説明をいただきたいということを重ねて申し上げておきます。
続けてお聞きしますが、この東北新社との会食は調査をしましたが、他の事業者との会食は行っていないのか、その点はどうですか。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
四名の総務省職員、谷脇、吉田、秋本、湯本につきましては、総務省の大臣官房において聴取をした際に、今回問題となった事業者以外の者との間で倫理法違反と疑われるような事案がなかったかどうかにつきましても調査を行っております。
調査をした結果、四名と他の放送事業者との間で倫理法違反を疑われるような事案はなかった、そう報告を受けております。
○塩川委員 倫理法令の疑いがなかったという点も、今回の東北新社のことがあるとにわかに信じ難いというのがありますけれども、調査として、四人以外については聞いたんですか。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
今回の四名以外につきましても、そういった事案がなかったかどうかにつきまして調査を行っております。
○塩川委員 調査を行っている途上。
○阪本政府参考人 お答えします。
調査を行いまして、同じく、そのような事案はなかったとの報告を受けております。
○塩川委員 これは報告書が出されるということなんでしょうか。
それで、報告書はいつ出るんですかね。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
本日までに調査を終えまして、その結果を国家公務員倫理審査会に報告する予定でございます。
○塩川委員 それは、今日、倫理審査会に提出をする、何時ぐらいですか。
○阪本政府参考人 早急に提出すべく、今作業中でございます。
○塩川委員 またその報告書を見て改めて問いたいと思います。
衛星放送行政を担う総務省幹部が軒並み、歴代にわたって東北新社とのみ会食を重ねる、こういう特別扱いというのはなぜなんでしょうか。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
非常にお答えしにくいところではございますが、まさに今回そういった倫理法等につきましての意識が非常に薄かったということではないかと考えております。
○塩川委員 いや、意識が低いから東北新社とのみ会食したということなんですか。
○阪本政府参考人 済みません、繰り返しのお答えになって申し訳ございませんが、まさに国家公務員というのは常に中立公正性を保ちながら職務を遂行することが重要でございまして、そういう中で今回の事案があったということは、まさにそういった倫理法等に関する理解が薄かった、そういうことだと理解しております。
○塩川委員 もう一回。
○木原委員長 もう一度御質問いただきます。
○塩川委員 東北新社だけ会食に応じた、ほかの事業者の会食に応じなかったというふうに答えられましたから、なぜそんな違いが出るんですか。
○木原委員長 少々お待ちください。
よろしいですか。よく整理をして御答弁いただきたいと思います。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
現時点におきまして、そういった理由というところにつきましてはちょっとこの場で即答はできませんが、まさに事実としてそういうふうな状況になっておるということにつきましては重く受け止めて、そして、厳しく対処してまいりたいと思っております。
○塩川委員 理由を即答できない、理由を言えないということで報告書を出されるんですか。理由も明らかにせずに報告書を出すということですか。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
まさに今回、公務員の倫理法に違反するかどうかという、そういう外形的な態様、そういうのがあったかどうかという事実関係につきましてまずは調査を行っておりまして、そして、その結果に基づいての御報告を今作成しているというところでございます。
○塩川委員 報告書がどうなっているのか拝見した上で、改めてその点をただしたいと思います。なぜというのがなしの調査はあり得ない、報告はあり得ないわけで、その点は是非ともはっきりさせていただきたい。
そういう点でも、谷脇氏、吉田氏、秋本氏、湯本氏は、東北新社との最初の会食の際には、同席していた相手方の中には菅総理の長男であります菅正剛氏がいらっしゃったわけですけれども、この四氏については、最初に東北新社と会食した際に、菅正剛氏が菅総理の息子だということは認識しておられたんでしょうか。
○阪本政府参考人 お答え申し上げます。
まさにその四名から総務省大臣官房において調査を行いまして、四名と菅正剛氏との最初の接点について聴取をいたしました。
そして、それらにつきまして、まず、谷脇総務審議官からは、最初の会食のときに知ったというふうな回答、そして、吉田総務審議官からは、菅義偉総理大臣が総務大臣当時に政務の秘書官をしていたということで知り合った、そして、秋本大臣官房付は、木田由紀夫氏を介して平成二十七年以降に知り合った、そして、湯本大臣官房付は、菅義偉総理大臣が総務大臣当時、政務秘書官をしていた菅氏と知り合った、そういった回答を受けております。
○塩川委員 少なくとも、この四人のうち三人は、菅正剛氏が政務秘書官だったことは当然承知をしていたということでありますし、知らないという人は当然いないだろうと思いますけれども、こういった特別の縁があったということが背景にある。
ですから、総務省幹部による東北新社とのみ会食を重ねるという特別扱いは、菅総理の長男の菅正剛氏が同席したからこその特別扱いということになるんじゃないでしょうか。この点について調べられましたか。
○阪本政府参考人 お答え申し上げます。
これらの会食につきましては、東北新社の方からのお話を受けて会食をしたというふうに伺っておりまして、必ずしも、菅正剛氏がいるからというふうなことでその会合を行ったとは聞いておりません。
また、実際に、菅正剛氏がいない場もあったというふうに承知しております。
○塩川委員 最初の会食の話をしているわけです。その最初の会食のときには菅正剛氏はいらっしゃる。案内についても名前も入っていた。そういう確認の中での出席ということになるんじゃないでしょうか。
この問題について、報告書を踏まえて引き続き取り上げたいと思いますが、官房長官にお尋ねします。
総務省の幹部が東北新社から度重なる接待を受けていた。この接待が東北新社に係る放送事業の許認可などに影響を与えなかったと言えるんでしょうか。
○加藤国務大臣 去る二十二日、総務省から、国家公務員倫理法違反に該当する可能性がある行為という報告がなされ、今、倫理審査会というんでしょうか、そこに報告をし、処分について検討をされているというふうに承知をしております。適切に対処されるものというふうに承知をしております。
また、今お話があった件でありますけれども、国家公務員は、常に中立性、効率性を保ちつつ職務を遂行することが重要であり、法令に基づいて粛々と職務執行が行われていること、これがまさに基本であります。
今回の調査で、国家公務員倫理法違反の疑いのある事実が認められた事案が十二名、延べ三十八件に上ったこと、これは甚だ遺憾でありますし、総務省において、再発防止策を含め厳正な対処、そして再発防止策をしっかり実施していただきたいと思います。
あわせて、国民からの強い疑念の目が向けられることになったこと、これはしっかり重く受け止め、今朝の総務大臣の記者会見でもたしか発言があったと思いますけれども、今後、全力で国民の信頼の回復に取り組むべく、具体的な検討がなされるものと承知をしております。
○塩川委員 この間取り上げられていますように、東北新社、また、その子会社に係る総務省の関与という点でいっても、二〇一七年八月の放送法関係審査基準の策定ですとか、二〇一八年五月の囲碁・将棋チャンネル、ザ・シネマHDがCS放送に係る衛星基幹放送に認定された件や、二〇二〇年三月のスターチャンネル1、3の放送事項の変更の許可、その十二月、スターチャンネル1の認定の更新、こういう点でも、総務省は東北新社に係る多数の許認可の権限を持っております。
また、東北新社が加盟する衛星放送協会は、昨年の秋に、衛星料金の低減を求める要望を総務省の会議の場でも出していた。そういう時期に会食を重ねていた。その点でも、贈収賄など刑事事件に発展する可能性もある問題であって、倫理法令にとどまる話ではない、徹底解明が必要だ。
その点でも、当委員会においても、国家公務員制度所管の立場から、しかるべき、当事者にはしっかりと出席をしてもらう、こういうことで徹底解明が必要だということを申し上げておきます。
続けて、官房長官にお尋ねをいたしますが、内閣広報官である山田真貴子氏の接待問題についてであります。
二十二日月曜日に報告をされた山田氏の調査というのは、誰が行ったものなんでしょうか。
○木原委員長 ちょっとお待ちいただいて。
総務省からお答えいただけますか。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
総務省が確認をしたというふうに承知しておりますが、具体的なその調査、確認方法まで、済みません、ただいまお答えできるものを持ち合わせておりません。
○塩川委員 いや、内閣広報官ですので、官房長官の下にいる方でありますからお聞きしているわけですけれども、この一枚紙を見ますと、上に米印があって、山田氏が、相手方から確認を取りつつ、現時点で確認できた範囲での事実関係として、報告のあったものと書いてあるんですよ。
ということは、山田さん本人が東北新社側と連絡を取って出しました、こういう説明として受け取ったんですが、そのとおりでよろしいですか。
○加藤国務大臣 まず、本件は総務省から出された資料で、総務省がまさに今答弁をさせていただいたように、山田広報官から確認された事実として受けて、それを総務省から出されたものと承知をしております。
加えて、今朝、杉田副長官に広報官から報告がございまして、ほぼ同趣旨の話を私どもは承知をしているところであります。
○塩川委員 そうすると、今のこのペーパーでいえば、総務省が出したという話ですけれども、その場合に、先ほどの米印のところなんですが、要は、山田さんが東北新社から確認を取って明らかにしたものを総務省が記録をした、山田さんが東北新社と連絡を取ったということでいいですか。
○阪本政府参考人 お答えいたします。
まさにそのようなことで結構でございます。
○塩川委員 自分が関わる事件を自分が調査をして報告をするなんて、あり得ないじゃないですか。
官房長官、おかしいと思いませんか。自分が関わる事件について自分が調査をして報告をしていた、そんなことはあり得ないと思うんですが。
○加藤国務大臣 これは調査ということになれば、調査する側に一定程度権限がなきゃならないということになりますけれども、御承知のように、制度的にいえば、今の内閣広報官の行為は総務省在職中の行為でありまして、総務省を退官し、内閣広報官を、退任した時点で、いわゆる懲戒処分等ができないという規定になっております。
また、内閣広報官は、特別職の国家公務員であり、一般職のような法律に基づく懲戒処分の規定も設けられていないという現行の規定がございます。
しかし、規定があるからということではなくて、私どもとしては、今、総務省の関係者の処分等がこれから確定するということでありますから、そうした対応を見ながら対応はしていきたいというふうに考えているところであります。
ですから、したがって、そういった状況の中でありますから、まずは御本人から、先方から確認をして御報告をいただく、これがまず基本になるんだと思います。
○塩川委員 いや、そもそも、特別職について、倫理法令が対象にならないということ自身がおかしいんじゃないでしょうか。
特別職国家公務員について、官邸にたくさんの方がいらっしゃるわけです。この間の中央省庁再編、官邸機能強化の中で、総理の補佐官や総理の秘書官や、また、この山田さんのような内閣広報官とか、そういった国家の枢要を担うような、政策立案過程に関わるような特別職の国家公務員について倫理法令がないということはおかしいと思いませんか。
○加藤国務大臣 いやいや、今申し上げたのは、まず、在職中の行為でありますから、これは。ですから、在職中の行為であり、総務省を退官し、内閣広報官に就任した現時点では懲戒処分の対象にならないということを申し上げているところであります。
それから、もう一個言ったのは、一般職のような法律に基づく懲戒処分の規定は設けられていないということであります。内閣広報官としての非違行為については、内閣官房職員の訓告等に関する規程に基づく厳重訓戒又は訓告等が可能と承知をしております。
○塩川委員 いや、特別職国家公務員について倫理法令は必要ないのかと。
○加藤国務大臣 特別職の国家公務員というその性格に基づいて、現在の制度ができ上がっているものと承知をしております。
○塩川委員 こういった格好で抜け穴になっているという点も、そもそも問われてくる問題であります。この点についても、しっかりと今後具体的な対応を考えていくことが求められている大きな課題だと申し上げておきます。
それで、実際に、山田内閣広報官が総務審議官当時の接待では七万円以上という高額だったわけですが、どういう会食か、これは一度だけなのか。菅総理は、予算委員会の答弁で、詳細については確認したいと述べておりましたが、この点は確認されたんでしょうか。
○加藤国務大臣 先ほど申し上げましたように、杉田副長官に対して御本人から報告がございました。その中で、今、回数のお話があったと思いますけれども、総務省在職中についての記録を東北新社に確認し報告したところ、この一件のみという報告があったと聞いております。
○塩川委員 七万円、どんな会食だったのかは確認されていないんですか。
○加藤国務大臣 会食の具体的な中身は明確ではありませんが、和牛ステーキ、海鮮料理などがメニューというか、提供されたということであります。
それから、具体的な金額については、東北新社に問い合わせたところ、合計額が三十七万一千十三円と確認できましたので、参加人数が五人ということで、頭割りをした金額ということで報告が行われているところであります。
○塩川委員 この点でも、山田さんにも御出席いただいて、具体的な経緯を含めて、ただす機会を設けていくことが必要であります。本人任せの調査など論外だということを申し上げておきます。
官房長官にお尋ねしますが、菅総理の身内の特別扱いと官僚の忖度という構図は、モリカケ疑惑をめぐる安倍前総理の身内の特別扱いと官僚の忖度と全く同じ構図であります。人事を通じた過度な官僚支配の仕組みがこのような行政のゆがみをもたらしたという認識はお持ちでありませんか。
○加藤国務大臣 今般、公務員倫理審査規程違反に該当する可能性が高い行為があったこと、これは甚だ遺憾だというふうに考えております。
ただ、その件と、官邸としてあるいは政府全体として人事をどうするか、これは別物だというふうに思います。
○塩川委員 この問題についての徹底解明という点で、冒頭申し上げましたけれども、谷脇氏、吉田氏、秋本氏、湯本氏についての当委員会への出席と、山田真貴子内閣広報官の当委員会への出席、また、東北新社側の木田氏や菅正剛氏らの国会、当委員会への出席を求めたいと思います。
○木原委員長 引き続き理事会で協議をいたします。