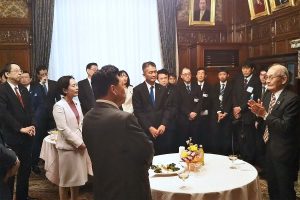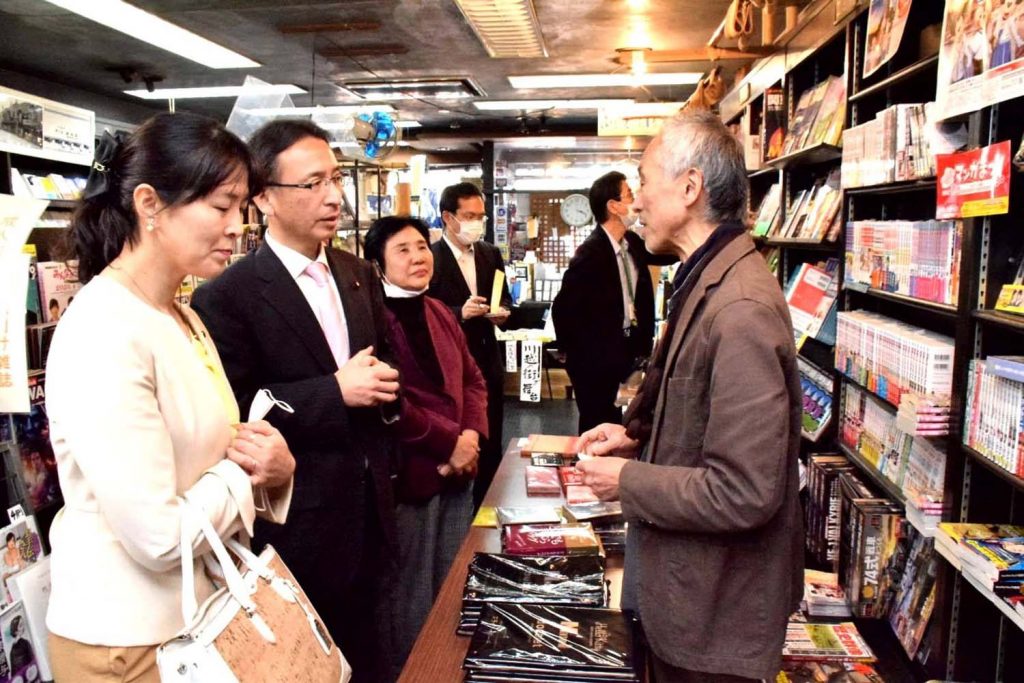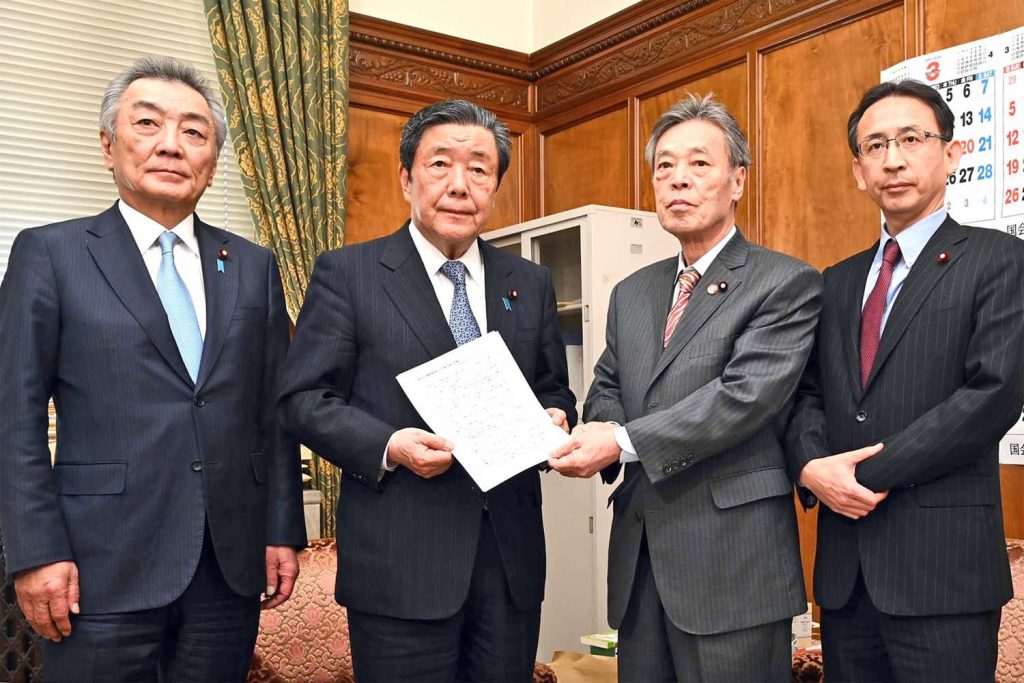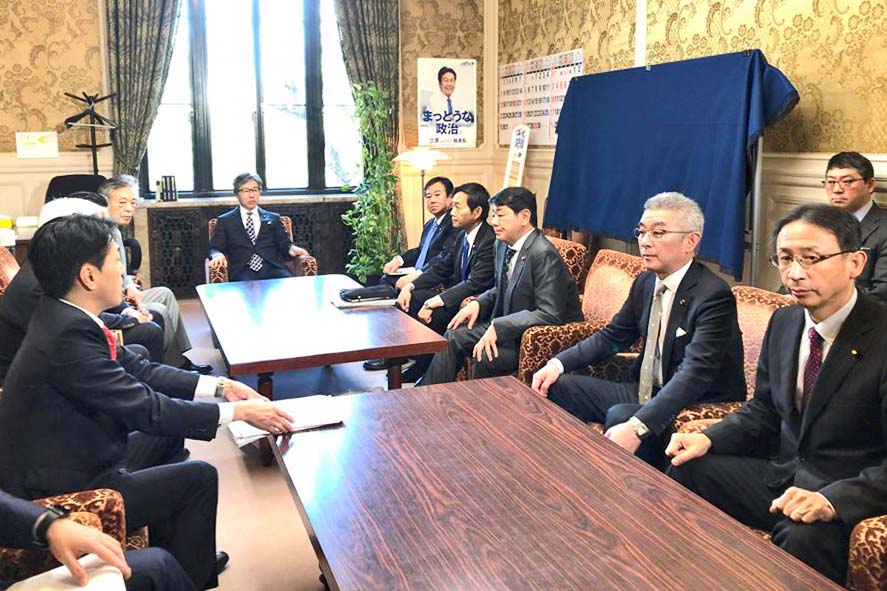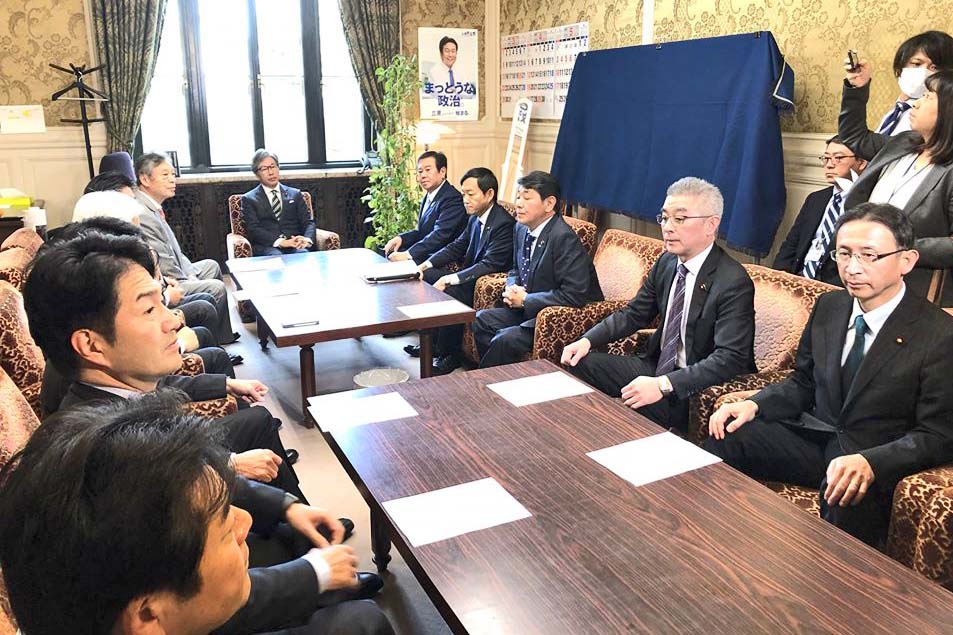新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に加える改定法案が、内閣委員会で採決され、自民、公明、維新と、立憲民主党などの共同会派の賛成多数で可決。日本共産党は反対しました。
新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に加える改定法案が、内閣委員会で採決され、自民、公明、維新と、立憲民主党などの共同会派の賛成多数で可決。日本共産党は反対しました。
特措法は、私権制限を伴う重大な決定の「緊急事態宣言」には専門家の意見聴取を定めておらず、宣言の発動要件も不明確です。
私の追及に対し、西村康稔担当相は専門家の意見聴取を義務づけていないことについて「正直、この法律を読んだ時はそういう印象をもった」としつつ、「全体の体系をうけて専門家の意見を聞くことを担保している」と釈明。
緊急事態宣言後に都道府県対策本部長(知事)が行う「要請」や「指示」は、どこの地域でいつまで「外出自粛」なのか、どのような施設でいつまで「使用制限・停止」されるのか法文上の規定はない。
私は、知事の判断で恣意(しい)的な運用が行われるのではないか。こういった点での歯止めがないと指摘しました。
さらに特措法は緊急事態宣言の前であっても知事に「公私の団体・個人に対し必要な協力の要請」ができる権限を与えています。
私は、うがい・手洗いの奨励だけでなく、外出抑制やイベント開催についての検討の要請など、知事の判断で踏み込んだ措置をすることに歯止めがあるのかと追及。
西村担当相は要請の内容が限定されていないと認めました。
私は反対討論で、特措法の最大の問題点は、緊急事態宣言の発動で「外出自粛要請」や「学校・社会福祉施設・興行場等に使用等の制限・停止の要請・指示」などができ、私人の権利制限を行えること。特措法には制限がもたらす人権侵害の救済措置も経済的な補償もない。人権の幅広い制限をもたらし、その歯止めが極めて曖昧で問題だ。このような法案をわずか3時間で採決するなど許されない。安倍晋三首相が独断で全国一律休校を決定し、国民は強い不安を抱いている。安倍政権に緊急事態宣言の発動を可能とすることは断じて認められないと強調しました。
新型インフル特措法改定案、衆院内閣委員会での反対討論の要旨は以下の通り。
本案は新型コロナウイルスを新型インフル特措法の対象に追加するものです。特措法の最大の問題点は、「外出の自粛要請」や「学校・社会福祉施設、興行場等に対し使用等の制限・停止の要請」さらには「指示」、土地所有者の同意なしに臨時医療施設開設のための土地使用も可能となる私権制限が行えるようになることです。
これらは、憲法に保障された基本的人権を制約するものであり、経済活動にも大きな影響をもたらします。
都道府県知事がこれらの私権制限の「要請」「指示」を行う出発点が、政府対策本部の本部長である首相による「緊急事態宣言」です。
同「宣言」を発動する要件は不明確です。政府は「重篤である症例の発生頻度が相当程度高い」「全国的かつ急速なまん延」をあげていますが、「重篤」「まん延」の基準や誰が判断するかが曖昧です。
政府行動計画や基本的対処方針を定める際には、「あらかじめ、専門家の意見を聞かなければならない」としながら、私権制限を伴う「宣言」決定には、専門家の意見聴取を義務づけていません。
「外出の自粛」は、どこの地域で、いつまでなのか、各種施設の「使用制限」はどのような施設が対象で、いつまでなのかといった歯止めがなく、必要以上の私権制限の懸念がぬぐえません。
制限がもたらす人権侵害に対する救済措置も経済的措置に対する補償もありません。
「宣言」下では、「指定公共機関」のNHKも、首相から「必要な指示」を受けることとなっており、NHKの自主性・独立性を確保できず、国民の知る権利を脅かしかねません。
特措法は、「宣言」前でも、都道府県知事に、「公私の団体・個人に対し、必要な協力の要請」を可能とする権限を与えています。この「要請」は、うがい手洗いの奨励にとどまらず、外出の抑制や大規模イベントの開催検討なども否定しておらず、歯止めがかかっていません。
特措法は、市民の自由と人権の幅広い制限をもたらし、その歯止めが極めて曖昧なもので、問題があります。
わずか3時間での採決など許されません。
安倍首相が突如打ち出した一律休校は、専門家の意見も聞かず、首相が独断で決定したことに、国民は強い不安を抱いています。本案によって、安倍政権に緊急事態宣言の発動を可能とすることは認められません。
衆議院TV・ビデオライブラリから見る
「議事録」(質疑)
<第201通常国会 2020年3月11日 内閣委員会 3号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
新型インフル特措法の改正案について質問をいたします。
今回の法案は、この新型インフル特措法に新型コロナウイルス感染症対応を盛り込むものであります。
そこで、まず、新型インフル特措法における緊急事態宣言に関してお尋ねをいたします。
第三十二条に基づいて政府対策本部長が緊急事態宣言を行うときに、あらかじめ専門家の意見を聞くということを法定していない、それはなぜなんでしょうか。
○西村国務大臣 ちょっと、法制定時の話をもう一度よく吟味をしなきゃいけないかと思いますけれども、基本的に、この法律の体系の中で、基本的人権の尊重といいますか、第五条で、さまざまな措置をとるときには最小化しなきゃいけないという措置が盛り込まれておりますので、そういったことも含めて、しっかりとそこに縛りがかかっているということで私は理解をしているところでございます。
○塩川委員 いや、質問に答えていないんですが。
何で、専門家の意見をあらかじめ聞かなければならないということが緊急事態宣言の場合にあってそうなっていないのか、規定されていないのか。そこはどうですか。
○西村国務大臣 先ほど申し上げた緊急事態宣言というのは非常に重い措置で、都道府県知事に相当強い権限、私権を制約する権限が与えられるということで、法律全体の中で、第五条の規定で基本的人権の尊重があり、さらに、この緊急事態宣言を出すことも含めて、この法律体系上は、政府行動計画をつくり、そして基本的対処方針をそれに基づいてつくるという法体系になっております。
そして、その基本的対処方針を定めるときに、専門的な知識を有する者、学識経験者の意見を聞かなきゃならないということで、既に諮問委員会が設置をされているところでございます。
そういう意味で、この大きな方針を定める、基本的対処方針を定めるときに専門家の意見を聞き、そして、それに基づいてさまざまのこの法律に基づく措置がとられるという意味では、大きな意味ではそこで専門家に意見を聞いているということでありますし、全体として基本的人権の尊重を図っているという理解でございます。
○塩川委員 今答弁が一部あったんですけれども、確認ですけれども、政府対策本部長が緊急事態宣言を行うときに、あらかじめ専門家の意見を聞くことは法定されていない、行動計画あるいは基本的対処方針においては聞きますねと。
ですから、特措法では、政府行動計画を作成するときは、「あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。」と規定をしています。また、特措法では、政府行動計画に基づき基本的対処方針を定めるときは、「あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。」と規定をしています。
そういう意味では、今お話しになったように、大きな方針、政府行動計画や基本的対処方針をつくるときには、あらかじめ専門家の意見を聞くことを義務づけているわけですけれども、やはり、まさに私権の制限、強い私権の制限を伴うような緊急事態宣言を行うときの要件はどうなっているのかといったときに、一番やはり問われる問題じゃないですか。まさにそのときに、何で、あらかじめ専門家の意見を聞かなければならないという義務づけがないのか、おかしいんじゃないですか。
○西村国務大臣 正直申し上げて、私も、最初にこの法律を読んだときは、そういう印象を持ったわけでございます。
ただ、今申し上げたように、ちょっと法制局の資料をもう一度よく吟味しなきゃいけません、過去の立法者の意思を含めてですね。当時、民主党政権で、先ほど、中川大臣が担当大臣で法制を、制定されたわけでありますけれども、そのときのこともよく調べなきゃいけないと思いますが。
まずは、基本的対処方針を定めるときに、大きな方針を決めるときに専門家の意見を聞いて、そのもとで緊急事態宣言も出される、その方針にのっとって出されるという理解では、全体としては聞いているということでありますし、それを補完する形で、まさに政府行動計画では、きちんと諮問委員会の意見を聞いて緊急事態宣言を行うことが定められているところでありまして、そういう意味で、この法律に基づいて行動計画をつくり、そしてその中で、緊急事態宣言を出すときには専門家の意見を聞かなければならない、聞くこととしているということに、政府は閣議決定をいたしておりますので、ある意味で、この法律の全体の体系を受けて、具体的に、そのような形で専門家の意見を聞くことを担保しているという整理になっていると思います。
○塩川委員 いや、強い私権の制限を伴う緊急事態宣言を行うという際に、その要件が妥当かどうかというところが問われているわけですよね。重篤性、感染性、この問題について、まさにあらかじめ専門家の意見を聞かなければならない。
この特措法というのは緊急事態宣言を行うということが大きな柱の法律なんですから、その肝心なときに、あらかじめ専門家の意見を聞かなければいけないという義務づけが入っていないというのは、そもそもおかしいわけですよ。これはこのままでいいということでいいんですか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、大きな体系としては、専門家の御意見をいただいて基本的対処方針をつくり、それに基づいて緊急事態宣言を出すという法体系になっております。
その基本的対処方針をつくるのは、政府行動計画に基づいてつくることになっておりまして、その政府行動計画というのはこの法律でつくることになっておりますが、その政府行動計画の中で、きちんと、緊急事態宣言を発するときには、その要件に該当するかどうかの判断について、この諮問委員会たる専門家の意見をしっかり聞いて判断をするということになっておりますので、そういう意味で、法体系上は、そういう形で専門家の意見を聞くことは担保されているということでございます。
○塩川委員 強い私権の制限を伴うような緊急事態宣言を行う際に、あらかじめ専門家の知見をしっかりと聞かなければならないというところが、一番の肝のはずなんですよ。そこのところがここに盛り込まれていないという点が極めて重大で、それは、まさに今の安倍総理は、科学的知見を示さないまま政治的に判断をして、全国一斉休校を要請し、現場は大きな混乱が生じたわけであります。
この緊急事態宣言を行う際に、あらかじめ専門家の意見を聞くことの義務づけがないということは、容認できないということを申し上げておきます。
次に、この緊急事態宣言に基づき、都道府県対策本部長は、外出自粛の要請や、学校、社会福祉施設、興行場等の使用制限、停止の要請や指示ができるとされています。
この要請の期間ですとか区域ですとか対象施設の範囲というのは、法文上の規定はもちろんないわけですけれども、どこでどのように定めるということなんでしょうか。
○西村国務大臣 御指摘は、本部が立ち上がった後、そして緊急事態宣言が出された後の四十五条の規定のことですね。
この規定については、使用制限、停止の要請あるいは指示、こうしたことができるわけですけれども、その期間とかそれから範囲について、それをどの範囲で行うかということでありますけれども、確かに、ここも、都道府県知事は専門家の意見を聞くことにはなっていないんですけれども、法文上はなっていないんですが、法体系でいいますと、先ほど申し上げたように、全体の基本的対処方針が専門家の意見を聞き設定されて、そのもとで、内閣総理大臣たる政府対策本部長が総合調整を行うということで、都道府県知事ともさまざまな調整を行っていく中で、そうした専門家の考え方なども都道府県知事にはしっかりとお示ししながら対応していくことになるというのが実態だと思いますけれども、しかし、実際のところ、どういう形で進むかという御懸念も確かにあるかと思います。
専門家の意見を伺いながら、私権の制限との関係も十分配慮して、適切に判断が行われるようにぜひしていきたいというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 ですから、緊急事態宣言、二年とか一年とか、この話はこれとしてあるわけですけれども、実際に私権の制限を伴うような要請を行う際に、それはいつまで続くんですか、どの範囲にかかるんですか、こういうところについて明示的に示されるものがないと、これは多くの方々に懸念が生じるのは当然のことと思うんですが、それはいかがですか。
○西村国務大臣 この四十五条の条文に書いておりますけれども、まさに、今回の場合は新型コロナウイルス感染症、これの潜伏期間とか治癒までの期間とか、今さまざま症例が出てきておりますので、今ある専門家会議の中でもいろいろ御議論があって一定の整理がなされつつありますけれども、そうしたものを考慮して一定の期間を定めて、利用の制限の要請なりを行っていくということでございます。
ですので、そういう意味で、政府対策本部においてしっかりと専門家の意見を聞きながら、それを都道府県知事と調整をしながら、そうした期間を設定をし、そして、施設については、一定面積以上ということで政令指定がなされておりますので、政令指定に基づいて、ある程度推測はつくわけでありますけれども、そうした運用になっていくものというふうに思いますが、現在、今回の新型コロナウイルス感染症の対象となる適用の期間を、現在のところ一年。二年以内となっておりますけれども、一年というふうに考えておりますので、その一年以内の間で、こうした潜伏期間とか治癒までの期間などを考慮して都道府県知事が定めていくということになるものと思います。
○塩川委員 外出自粛の要請とか、一年なんという想定というのは、それ自身が極めて深刻な問題ですから、そういうことではなくて、実際に具体に措置を行う際に、その期間はどれぐらいなんですか、どの対象で行うんですか、そういったところについて法文上の限定がないという点で、先ほど大臣の答弁にも、知事が行うような場合にも専門家の意見を聞くことにはなっていないということになれば、場合によると、その知事の判断で恣意的な運用が行われるのではないか、こういった点での歯どめがないということも指摘をせざるを得ません。必要以上の私権制限が行われる懸念が生じるということを申し上げておきます。
さらに、特措法では、緊急事態宣言の前であっても、第二十四条において、都道府県対策本部長の権限が規定をされております。
第二十四条の第九項では、公私の団体、個人に対し、必要な協力の要請をすることができるとあります。
この第二十四条第九項に基づく要請内容には、何らか限定というのはあるんですか。
○西村国務大臣 御指摘の法二十四条の九項、これにおきましては、御指摘のように、公私の団体、個人に対して協力の要請をすることができるということでありまして、具体的には、手洗い、うがいなど感染対策の広報活動においてボランティア団体への協力を要請すること、あるいは、学校、社会福祉施設での文化祭等のイベントを延期することなど感染対策を実施すること等への協力を要請すること、これを想定しているところでございます。
○塩川委員 手洗い、うがいですとか、それはよくわかる話なんですけれども、しかし、知事の判断でより踏み込んだ措置というのを要請というのも、行うことに何らかの歯どめがあるのかという問題なんですが。
都道府県知事は、この特措法第二十四条第九項に基づき、例えば、学校等に限らず、職場を含め、広く感染対策の徹底の要請を行う、こういうこともやれるということですか。
○西村国務大臣 まさに、法人格の有無を問わずに、ボランティア団体とか、集会を行う任意団体などに対して、文化祭等のイベントを延期すること、あるいは施設の使用を極力制限することなど、感染対策を実施することを協力を要請することを想定しているわけであります。
この法律を適用する段階というのは、まさに今回規定をさせていただいたように、蔓延のおそれが高いと認めるときでありますので、まさに、それをほっておくと、蔓延によって国民の生命、健康に重大な影響を及ぼし、そして国民生活、経済に大きな影響を及ぼすという事態が想定されるときでありますので、そういう、国民の命を守らなきゃいけないという要請と、それから、五条に書かれているように、私権の制約については最小限になるべき、基本的人権を尊重すべきという、この両方のバランスを適時適切に考えながら、どこまでの措置をやれば命を守れるのか、あるいはやり過ぎとならないのかということを常に考えながら判断をしていくということになると思います。
○塩川委員 そうしますと、緊急事態宣言の前の段階での、蔓延のおそれが高いと認められるとき、この新型コロナウイルス感染症対策が特措法で動き始めるという事態になった、そういうときには、第二十四条は、権限行使が知事は可能になるということであるわけだけれども、そうなりますと、蔓延のおそれが高いと認められるときといったことで、知事の権限行使は、外出の抑制とか、あるいは大規模イベントの中止といった要請というような、より踏み込んだ措置を行うということもあり得る。そこへの歯どめというのは何かあるんですか。
○西村国務大臣 まさに今回、法律改正をお願いして、新型コロナウイルス感染症をこの対象にするという上で、その次に、蔓延のおそれが高いと認められると厚労大臣が報告して、政府対策本部が立ち上がります。それによって幾つかの、先ほどおっしゃったような措置が適用できるようになります。
その上に、次に、緊急事態宣言が発出されれば、更に強い権限が与えられるということでありますけれども、まさに、緊急事態宣言のときは、全国的かつ急速な蔓延により国民生活、国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるという段階でありますので、当然、国民の命を守り、そして生活、経済を守っていく、特に生活を守っていくというところで、これは、やはり封じ込めるために必要な措置はとらなきゃいけないということでありますが、ただ、そのときも、五条にありますように、基本的人権の尊重がありますので、その措置は必要最小限ではならないということがかかってあるわけであります。
したがいまして、基本的対処方針の中で、専門家の意見を聞きながら、そうした方針をしっかりと定めて、そして、それに基づいて適時適切に判断をしていくということでございます。
○塩川委員 要請内容に限定がないということであったわけですけれども、知事の判断でいわば私権制限を伴うような要請が行われることへの歯どめがないということになります。そういう点でも、このままの規定、条文でいいのかということが出てくるわけであります。
二〇一二年の新型インフル特措法の審議における参議院の附帯決議があります。先ほど中川委員も紹介されておられましたが、第十七項の、新型インフルエンザ対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度については、本法施行後三年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとある。これについては政府はどのように対応したのかをお聞きします。
○西村国務大臣 第十七項の項目でありますけれども、御指摘の項目につきましては、法の公布後、平成二十四年に開催されています新型インフルエンザ等対策有識者会議におきましても、行政不服審査法等で対応するという原則を示しており、その後もその方針に変更はなかったというふうに承知をしておりますが、いずれにしましても、附帯決議に書かれていることでもございます。今回の新型感染症の終息後には、改めてその課題についても検討を行いたいというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 行政不服審査法という一般法での対応で済ます話ではない、まさに私権制限をもたらすような緊急事態宣言を行える、そういう特措法においての人権侵害に対する救済措置というのは、しっかりそこでとるべきだということであります。
この緊急事態宣言の決定過程の記録の作成、保存、公開といった透明性の確保や科学的な知見を踏まえた専門家の事前の関与などが、保障する規定が盛り込まれていない法律です。私権制限を行う場合における人権侵害の救済措置や経済的被害への補償措置も規定をされておりません。
法律の勝手な解釈を繰り返してきたのが安倍政権であり、安倍総理のもとで、国民の権利制限をもたらす特措法の改正は認められないということを申し上げて、質問を終わります。
「議事録」(反対討論)
<第201通常国会 2020年3月11日 内閣委員会 3号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
日本共産党を代表し、新型インフルエンザ特措法改正案に反対の討論を行います。
本改正案は、新型コロナウイルスを二年間、インフル特措法の対象に追加をするものです。
そもそも、特措法の最大の問題点は、外出の自粛要請や学校、社会福祉施設、興行場等に対し、使用等の制限、停止の要請、さらには指示、土地所有者の同意なしに臨時医療施設開設のための土地使用も可能とした私権制限が行えるようになることです。これらは、憲法に保障された移動の自由や集会の自由、表現の自由といった基本的人権を制約するものであり、経済活動にも大きな影響をもたらすものです。
当該都道府県知事がこれらの私権制限の要請、指示を行う出発となるのが、政府対策本部の本部長である内閣総理大臣が行う緊急事態宣言です。
緊急事態宣言を発動する要件は不明確です。政府は、重篤である症例の発生頻度が相当程度高い、全国的かつ急速な蔓延を挙げていますが、重篤、蔓延をいかなる基準で誰が判断するのか曖昧です。政府行動計画の作成や基本的対処方針を定める際にはあらかじめ専門家の意見を聞かなければならないとしながら、私権制限を伴う緊急事態宣言の決定には専門家の意見聴取を義務づけていないことは重大です。
外出の自粛は、どこの地域で、いつまでなのか、各種施設の使用制限は、どのような施設が対象で、いつまでなのかといった歯どめはなく、必要以上の私権の制限が行われる懸念が拭えません。特措法には、これらの制限がもたらす人権侵害に対する救済措置はなく、経済的措置に対する補償もありません。
緊急事態宣言のもとでは、指定公共機関のNHKも政府対策本部長の総理から必要な指示を受けることとなっており、NHKの自主性、独立性を確保できず、国民の知る権利を脅かしかねません。
さらに、特措法は、緊急事態宣言の前であっても、都道府県対策本部長である知事に、公私の団体、個人に対し、必要な協力の要請を可能とする権限が与えられています。この要請は、うがい、手洗いの奨励にとどまらず、外出の抑制や大規模イベントの開催検討などが含まれることを否定しておらず、歯どめがかかっていません。
特措法は、市民の自由と人権の幅広い制限をもたらし、その歯どめが極めて曖昧なもので、問題があります。そのような法案をわずか三時間で採決を行うなど、断じて許されません。
安倍総理が突如打ち出した全国の学校の一斉休校の決定は、専門家の意見も聞かず総理の独断で決定したことに、国民は強い不安を抱いています。本案によって安倍政権に緊急事態宣言の発動を可能とすることは、断じて認められません。
以上、反対の討論を終わります。
 政府が提示している国会同意人事案のうち公正取引委員会委員長候補者の古谷一之内閣官房副長官補から所信を聴取しました。
政府が提示している国会同意人事案のうち公正取引委員会委員長候補者の古谷一之内閣官房副長官補から所信を聴取しました。