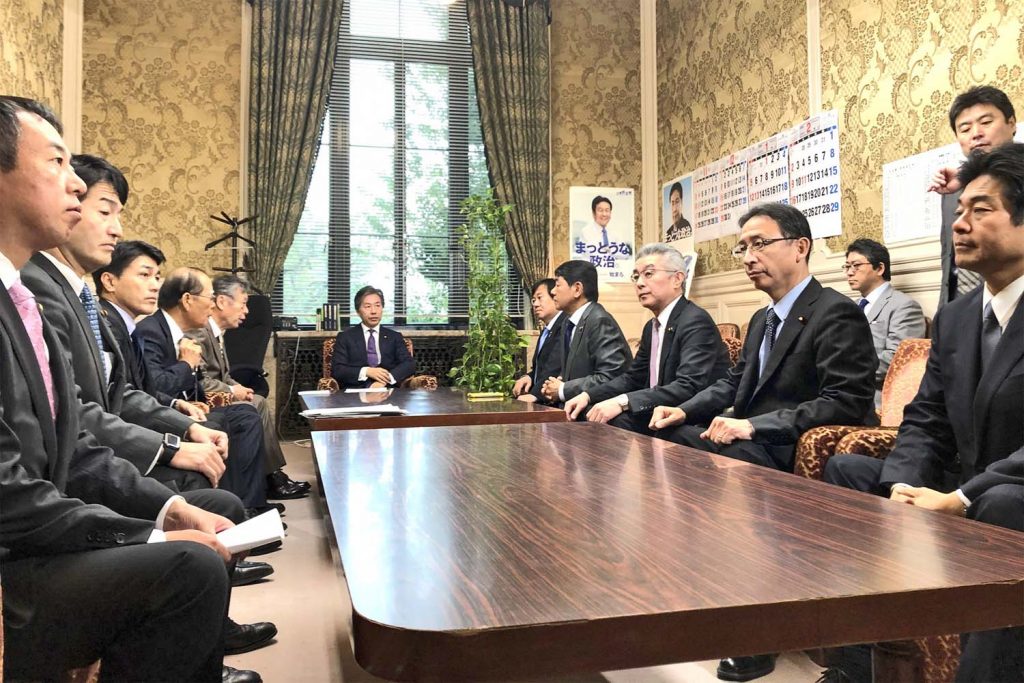カジノ問題集中質疑に立ちました。
カジノ問題集中質疑に立ちました。
カジノを誘致する自治体が国の認定を受けるさい、議会の議決が必要となる「区域整備計画」の認定期間は初回10年、以降5年ごとの更新とされています。一方、自治体がカジノ事業者と結ぶ「実施協定」の期間は30年間を超える長期になることが容認されています。
私は、認定の有効期間を超えた事業期間を実施協定で結ぶのは、議会の議決を形骸化させるのではないか――と質問。
赤羽一嘉国交相(IR担当)は「議会の議決を経なければ認定の更新はできない」と答えました。
さらに私は、知事や議会の構成がかわり、認定の更新時期に自治体側がカジノから撤退しようとしても、事業者との「協定」が優先されるのではないかと追及。
赤羽国交相は「そういうことも想定される」と認めました。
政府が検討中の「基本方針」案は、自治体側の申請により認定取り消しが行われた場合の事業者への「補償」規定に言及しており、実施協定がしばりになり、一度始めたら後戻りできず、カジノに反対する民意が通らない仕組みだ。
赤羽国交相は「支障が生じないようにしたい」と答えました。
こうした事業のために、カジノ管理委員会を設置すべきではないし、カジノ実施法は廃止すべきだ。
衆議院TV・ビデオライブラリから見る
「議事録」
<第200通常国会 2019年11月29日 内閣委員会 6号>
○松本委員長 次に、塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
カジノ集中での質疑を行います。
赤羽大臣に、区域整備計画と実施協定の関係について、まずお尋ねをいたします。
都道府県等自治体が基本方針、実施方針に即して作成する区域整備計画についてですが、この区域整備計画の最初の認定の有効期間は、初回は十年、その後、五年ごとの更新になっています。その際、区域整備計画の申請に当たっては、議会の議決を経なければならないとなっております。
このように議会の議決を経なければならないというのは、地域における合意形成を十分に図るという趣旨ではないかと思いますが、その点を確認したいと思います。
○赤羽国務大臣 そのように理解をしております。
○塩川委員 ですから、住民の意思というのが当然重要だということになるわけであります。
都道府県が認定申請を行う場合には、立地市町村の同意を得ることも法定化もされております。立地市町村を含め、地域における合意形成を十分図ることが必要となっていることです。
一方、カジノ事業者と自治体が結ぶ実施協定においては、この区域整備計画で言う最初の十年に限定されず、より長期の事業計画を設定することができるとされていると承知していますが、そのとおりでしょうか。
○赤羽国務大臣 この趣旨は、もともと、基本方針案に書いていると思いますが、よりよい施設を長期間運営していただけるような、途中で投げ出すような運営者でないことがベターだという趣旨であるわけでございますが、いいですか、それで。
○塩川委員 確認ですけれども、事業者と自治体が結ぶ実施協定においては、区域整備計画で言う、初度の、最初の有効期間の十年に限定されず、より長期の事業計画を設定することができるということは、そのとおりですね。
○赤羽国務大臣 はい、そうです。
○塩川委員 実際、カジノ実施法の審議の際の政府の答弁でも、実施協定の中では三十年、四十年という有効期間を定めることができるという話もありました。
例えば、今、大阪府市の実施方針案、これも、基本方針も案の段階ですから、もちろんその実施方針の案の段階ですけれども、カジノの事業期間は三十五年としています。さらに、事業期間の延長期間は原則として三十年という記載もありますので、非常に超長期にカジノを運営するということを、事業者と都道府県・政令指定都市、自治体の間で実施協定を取り結ぶという案になっているということです。
そうしますと、この区域整備計画の申請については議会の議決を必要としますが、その有効期間の十年を大幅に超えた事業期間を実施協定で結ぶというのは、議会の議決を形骸化させるものになるんじゃありませんか。
○赤羽国務大臣 認定期間、最初は十年間で、次回以後五年ということであります。そのときに議会の議決を得られなければ、認定の延長はできないというのが原則です。
○塩川委員 その点は本当にそうかという点ですけれども、基本方針案では、IR事業は長期間にわたる安定的で継続的な実施の確保が必要であることを踏まえ、都道府県等とIR事業者との合意により、区域整備計画の認定の有効期間を超えることも可能であると、まさに、政府のつくっている基本方針案の段階で、長期の期間での実施協定を取り結ぶことも可能なんだというふうに、まさにお墨つきを与えているという状況になっています。
ですから、そうはいっても、知事や市長がかわる、あるいは議会の構成が変わって、IR、カジノは認めないとなったときに、その手を縛るということにはならないんですか。
○赤羽国務大臣 そういったことも想定されるんだと思うんですが、我々は、実施協定の中に、立ち行かなくなった場合の決め事とか、議決がとれなかったときに損害賠償を起こさないとか、そうした項目を盛り込んでいただければというふうに思っております。
○塩川委員 損害賠償を起こさないという話ですけれども、実際にスタートのときには、当時の首長や議会の構成によって、IR、カジノを進めましょうということになったとしても、その途中で、いや、それはおかしいというまさに住民の声があって、市長や知事がかわる、議会の構成が変わる、とめようとなったときに、本当にそういった損害賠償を求めないというスキームになるのか。
というのは、最初の実施協定に何が書かれているかという話になるわけですよ。最初の実施協定で縛りがかかるんじゃないのかという問題であるわけです。
基本方針案の中では、都道府県等とIR事業者との間の実施協定においては、都道府県等の申請により認定の取消しが行われた場合における補償について規定しておくことも可能としているわけです。ですから、何か問題があって認定の取消しを行うといったような場合に、その変更を行った自治体の側に補償の責務が生じるという規定を置くことも可能だということをわざわざ書いているんですよ。現に、大阪府市の実施方針案にもそのような内容が盛り込まれています。
そうなると、実施協定の段階で、途中で変更したら補償もしますよといったことも含めて書かれているのだったら、途中で知事や市長、議会の構成が変わったとしても、もう後戻りができない、こういう仕組みにならざるを得ないんじゃないですか。それが実施協定の中身ということを皆さんおっしゃっているということじゃないですか。
○赤羽国務大臣 済みません、大阪の具体的な案について、私、まだ承知をしておりませんし、言及できませんが、原則論は、先ほど申し上げました、認定期間は十年間、その後五年間でございまして、その間に議決を要するということが書かれるわけですから、そうした原則にのっとって。
まだ、大阪云々ということじゃなくて、今八つから出ていて、それを最大三つまで絞り込む中でのプロセスで、そうしたことの支障が生じないように、塩川先生からの御提言もありましたので、参考にさせていただいて、対応を検討していきたいと思っております。
○塩川委員 この点については、実施協定が縛りとなって、結果として民意を反映するということができなくなるんじゃないのかということが問われているわけです。こういうことを申し上げるというのも、その制度、スキームそのものがそういうことで設計されているということが問われているわけです。
この点で、ことし八月の、日経新聞主催のIRフォーラム大阪というのが開かれました。そこに当時の萩生田光一自民党幹事長代行が出席をし、発言をしております。萩生田氏は、あえてこの場で申し上げるが、基本方針をつくる中できちんと解説を入れさせている、十年たったときに、知事や市長や議会の構成が変わって、やっぱりあんたたち出ていってくれと言っても訴訟になる、これはどうあっても自治体の側に非があるということになる。
結局、議会の構成、知事や市長がかわって、あんたたち出てくれと言っても、訴訟という形で、自治体の方が悪いんだという形で、やめることができなくなるというのが実施協定の中身となるように、あるいは基本方針の中にしっかりと解説を入れるというふうに書いているわけで、まさにそのとおりの基本方針の案になっているわけです。
ですから、知事や市長がかわっても議会の構成が変わっても、一度始めたカジノは後戻りできないということを、こういうスキームの中で盛り込んでいるということになるんじゃないですか。
○赤羽国務大臣 済みません、私は萩生田さんのその発言を全く承知をしておりませんのであれですけれども、そのケース、ケース、いろいろなケースが考えられるんだと思います。
今塩川先生が言われたようなことがないように、何か決まって、首長さんがかわることだけが原因でころっと変わるということじゃなくて、施設自体が最初のときと状況が違って、もう午前中の答弁でも答えさせていただきましたが、いろいろな障害が出てきたときにはやはり見直しが必要であるわけですし、そうしたことで認定期間も十年、五年、五年というふうにしているわけですから、そうした原則論は大事にしながら、一つ一つ対応していかなければいけないと思っております。
○塩川委員 いや、要するに、事業者と自治体が結ぶ実施協定の中で、事業者に譲歩するような、おもねるような、そういう中身が盛り込まれていたら、それに拘束されるんじゃないのか。十年、五年先での見直しというのが実際にはできなくなるという点でも、こういったスキームで動かすようなカジノを進めるということは認められない。
こういったカジノ推進のためのカジノ管理委員会を設置すべきではありませんし、カジノ法そのものを廃止せよということを申し上げて、質問を終わります。
 全建総連(吉田三男委員長)の皆さんと、来年度予算、建設業の労働環境改善に関して懇談。日本共産党から笠井亮建設国保対策委員長はじめ11人が出席。
全建総連(吉田三男委員長)の皆さんと、来年度予算、建設業の労働環境改善に関して懇談。日本共産党から笠井亮建設国保対策委員長はじめ11人が出席。