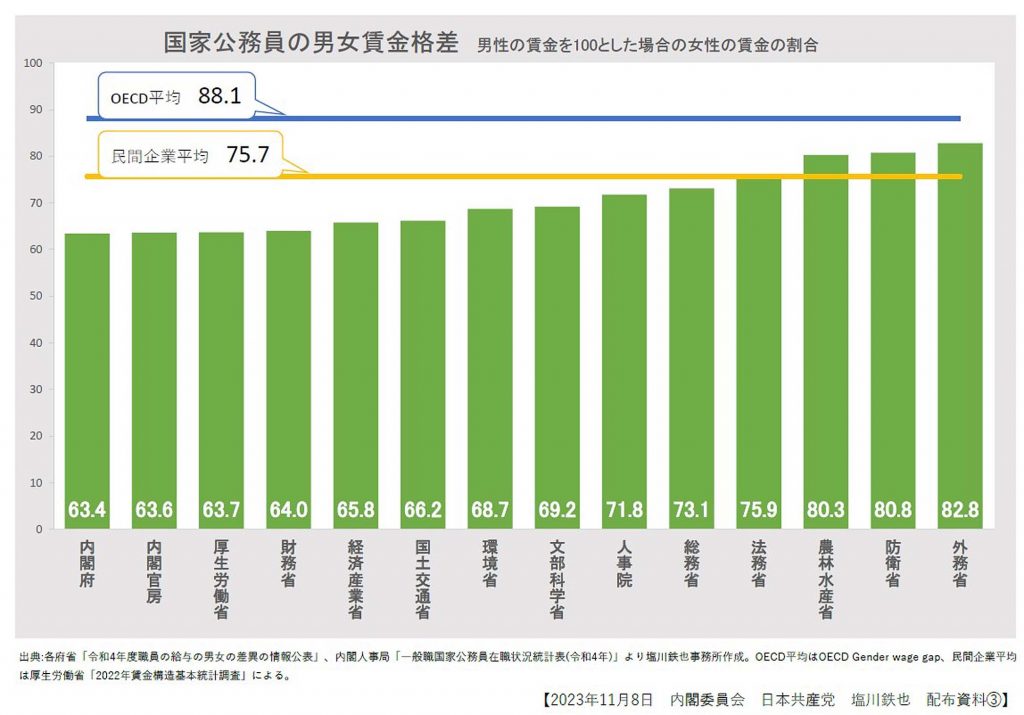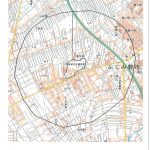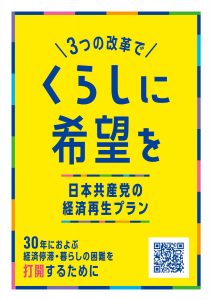国家公務員の一般職給与法、特別職給与法改正案が、採決されました。一般職の給与を引き上げる改定案は日本共産党を含む賛成多数で可決。
国家公務員の一般職給与法、特別職給与法改正案が、採決されました。一般職の給与を引き上げる改定案は日本共産党を含む賛成多数で可決。
首相や閣僚らの給与を増額する特別職の改定案は、共産、立民、維新、れいわなどが反対しましたが、自民、公明、国民の賛成多数で可決されました。
立民が提出した首相らの給与を据え置く修正案に共産、維新、れいわなどが賛成しましたが、自民、公明、国民の反対で否決されました。
私は質疑で、物価高騰で苦しむ国民に軍拡増税・社会保障負担増を強いるだけでなく、これまでコストカット型経済を推進し、賃金の上がらない国にした自民党政治の責任は重大だと強調。首相、閣僚の給与引き上げは国民の理解を得られないとして特別職給与法改定案の撤回を要求しました。
また、私は、人事院が一般職の国家公務員の給与に最大20%の格差をつける地域手当の見直しとして、級地区分の「大くくり化」を検討していることについて、東京都と岩手県における最低賃金の格差の割合が19・8%に上り、地域手当の格差に符合すると指摘。「公務の地域手当が、民間の地域間格差の固定化、拡大もつくり出しているのではないか」と質問。
人事院は「民間企業が国家公務員の給与を参考にすることもあると承知している」と地域手当の影響を否定しませんでした。
私は「おおくくり化しても格差は解消されない」と追及。全国どこでも最低生計費は同水準であることが明らかになっているとして、「地域手当は廃止すべきだ」と迫ったのに対し、川本人事院総裁は「諸方面の意見を聞きながら検討する」と答えるに留まりました。
「議事録」
<質疑>
<反対討論>