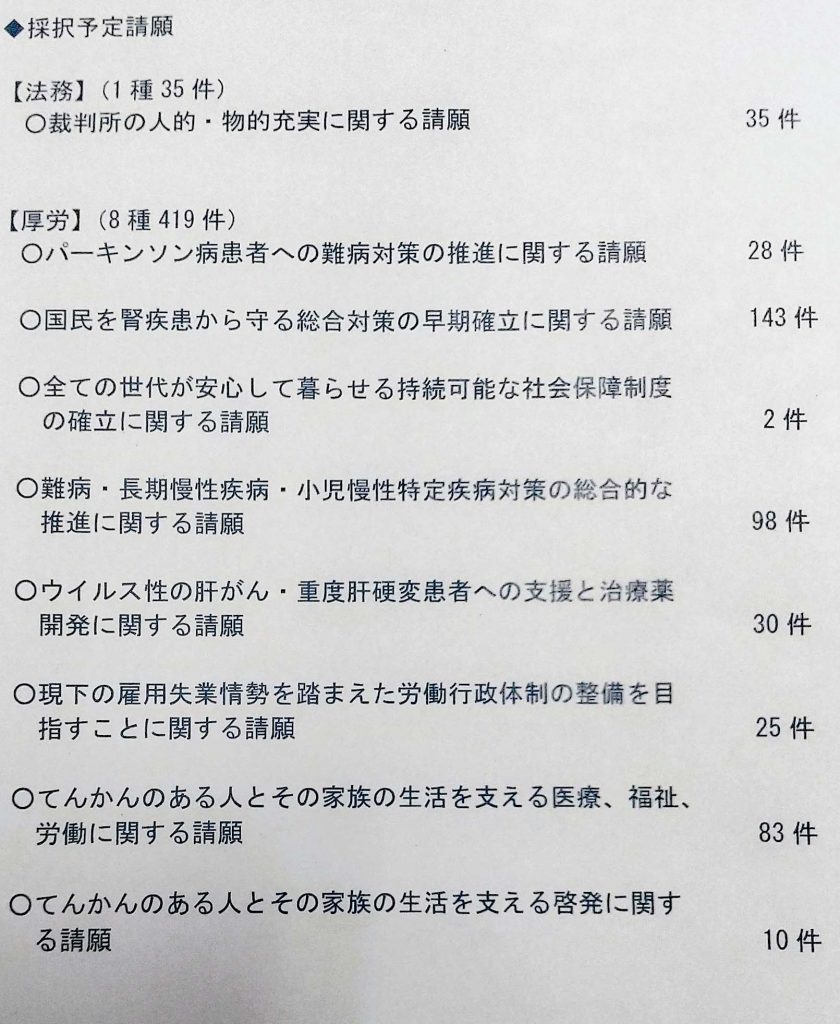前橋市内で街頭演説会。梅村さえこ衆院北関東比例予定候補、たなはしせつ子群馬1区予定候補と訴え!
前橋市内で街頭演説会。梅村さえこ衆院北関東比例予定候補、たなはしせつ子群馬1区予定候補と訴え!
声を上げれば政治は変わる。群馬では、18才までの子ども医療費無料化と高崎市を除く全市町村で学校給食費無償化を実現。国政では、保険証廃止撤回を求める世論と運動が岸田政権を追い詰めている。
大軍拡こそ平和壊す/塩川・梅村比例予定候補北関東3県駆ける
「しんぶん赤旗」7月5日・首都圏版より
塩川鉄也衆議院議員・北関東比例予定候補と梅村さえこ同予定候補は2日、茨城、栃木、群馬の3県を駆け巡り、各県委員会との懇談や街頭宣伝をしました。
塩川・梅村両氏は群馬県で、午後4時ごろから党県委員会と懇談。医療関係者からマイナンバー問題への怒りの声が届き、青年学生から生活苦や高学費、戦争への不安が寄せられ、共産党への関心も広がっていることを交流しました。
総選挙に向けた各党の活動が活発化し、統一協会・国際勝共連合が新しい反共ビラを配布している状況も報告され、党の自力をつける活動に全力をあげることを確認しました。酒井宏明県議、伊藤たつや5区予定候補も参加しました。
懇談後に前橋市内での街頭演説。梅村氏は、国際的にも遅れたジェンダー平等をとりあげ、声をあげれば政治は変わると訴えました。塩川氏は、大軍拡こそが平和を壊し、大増税につながると指摘。23日投票の県知事選挙で県民の平和の声を大きくあげようと呼びかけました。たなはしせつ子1区予定候補は高崎市を除く全市町村に学校給食費無償化が広がったことを紹介しました。(この演説は群馬県委員会のユーチューブチャンネルで視聴できます)