 市民の暮らしを守り、生活相談4000件の小林すみ子候補は、保健所復活、学校給食費ゼロ、18歳子ども医療費ゼロ、子どもの国保税ゼロの「四つの実現」と、ゴミの有料化と原発事故汚染土持ち込みの「二つのストップ」をめざします!
市民の暮らしを守り、生活相談4000件の小林すみ子候補は、保健所復活、学校給食費ゼロ、18歳子ども医療費ゼロ、子どもの国保税ゼロの「四つの実現」と、ゴミの有料化と原発事故汚染土持ち込みの「二つのストップ」をめざします!
何としても押し上げて下さい!
 健康保険証を廃止してマイナンバーカードに置き換えようとするマイナンバー法等改正案が審議入りしました。
健康保険証を廃止してマイナンバーカードに置き換えようとするマイナンバー法等改正案が審議入りしました。
私は「保険証を“人質”に、窓口負担を増やしてまで、マイナカードの取得・利用を強要することは許されない」と批判しました。
法案では、保険証を廃止し、マイナカードで保険資格を確認することができない人には「資格確認書」を発行するとしています。
私は、資格を有することを示す保険証を被保険者に届けることは国・保険者の責務だと指摘。申請交付のマイナ保険証と資格確認書に置き換えるのは「責任放棄であり、国民皆保険制度を揺るがすものだ」と迫りました。
加藤厚生労働大臣は「マイナ保険証には多くのメリットがある」としか答弁しませんでした。
私は、法案がマイナンバー利用を「すべての行政分野において推進する」としており、社会保守・税・災害対策の3分野に限定している現行制度の仕組みを大きく変えるものだと指摘。プライバシー侵害の危険性を一層高めるものだと批判しました。
また、私は、年金受給口座を手始めに、本人が「不同意」としなければ自動的にマイナンバーと紐づける特例が盛り込まれたことは、本人「同意」の原則から180度の転換であり、制度への国民不振が一層高まると強調しました。
河野デジタル大臣は「本制度の周知徹底をはかることを予定している」などと答弁するだけでした。
さらに、私は、デジタル化推進のために戸籍などに「氏名の振り仮名」を追加する問題も取り上げ、人格を象徴する氏名・読み方は尊重されるべきだと主張。
改めて、マイナンバー制度の廃止を強く求めました。
質問の要旨は以下の通りです
日本共産党を代表してマイナンバー法等改正案について質問します。
まず、健康保険証廃止の問題です。
国民の大きな反対の声があるにもかかわらず、本案は、保険証を廃止し、マイナンバーカードに置き換えようとするものです。
資格を有することを示す保険証を、被保険者に届けることは、国・保険者の責務です。マイナ保険証も本案で創設される「資格確認書」も、本人からの申請に応じた交付です。保険証を廃止して申請交付とすることは、国・保険者の責任放棄であり、国民皆保険制度をゆるがすものです。
本案は、マイナ保険証も資格確認書も持たない人に、不利益をもたらすことになるのではありませんか。
そもそも、マイナカードの取得は、義務ではなく、希望者のみではありませんか。保険証を“人質”に、窓口負担を増やしてまで、マイナカードの取得・利用を強要することは、許されません。
医療関係者は、オンライン資格確認システムについて「医療機関の経済的負担やデータ漏えいリスク負担」の危惧を訴えています。高齢者・障害者施設からは「マイナ保険証と暗証番号の管理や資格確認書の申請管理が困難」との声が上がっています。これらの声をどう受け止めているのですか。
マイナ保険証利用の押し付け、保険証の廃止は撤回すべきです。答弁を求めます。
次に、マイナンバー制度拡大の問題です。
マイナンバー制度は、政府が住民一人ひとりに生涯変わらない番号をつけ、多分野の個人情報を紐づけるものです。プライバシー侵害のリスクが避けられません。
それ故、現行制度は、社会保障・税・災害対策の3分野に限定し、利用する事務・情報連携も法律で規定し、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管は本人同意があっても禁止しています。こうした厳格な縛りは、国民総背番号制導入やプライバシー侵害に対して国民の批判があったからではありませんか。
にもかかわらず、本案は、基本理念の中で、マイナンバー利用を、3分野に限定せず、全ての行政分野において推進するとしています。マイナンバー利用の対象に理美容師・教員・調理師等の国家資格の事務等を追加し、さらに法定事務に「準ずる事務」や、条例で措置した自治体事務は法定することなく、マイナンバーを利用できるとしています。
マイナンバーの情報連携は、法定から外して「法改正なし」とし、国会審議もなしに拡大できるようにしています。
これは、マイナンバー制度の仕組みを大きく変えるものであり、プライバシー侵害の危険性を一層高めるものではありませんか。答弁を求めます。
マイナカードの「本人確認」も問題です。
政府は「交付の際に市町村で厳格な本人確認を行う」「利用には暗証番号か顔認証が必要である」と安全性を強調してきました。ところが、本案では、マイナカードの「直接交付」の規定を緩め、2回目以降の「暗証番号入力」なしを認めるとしています。
マイナカード普及のために、安全確保策を後退させるものではありませんか。
また、公金受取口座登録の特例も問題です。
本案は、年金受給口座を手始めに、本人から「不同意」との回答がなければ、自動的にマイナンバーと紐づける特例を盛り込んでいます。これまでの本人同意「あり」の原則から180度の転換ではありませんか。
このようなやり方では、制度に対する国民の不信は一層高まるものです。
最後に、デジタル化の推進のために盛り込んだ、戸籍等の「氏名の振り仮名」の問題です。
本案は、氏名の振り仮名は「一般に認められている」読み方に限るとしています。これでは、行政が「一般的な読み方」の審査を行うことになります。命名に介入することは許されません。
また、現在戸籍に記載されている人の「振り仮名」は、本籍地市町村長が記載するとしています。本人が知らない間に、現に使っているものとは違う「振り仮名」となる可能性があるのではありませんか。
氏名は個人の人格を象徴するものであり、その読み方は尊重されなければなりません。
マイナンバー制度は廃止すべきだと申し述べ、質問を終わります。
 政府が、提出を検討している日本学術会議法改正案として、会員選考に総理大臣の意を受けた有識者が関与する案を示している問題を追及しました。
政府が、提出を検討している日本学術会議法改正案として、会員選考に総理大臣の意を受けた有識者が関与する案を示している問題を追及しました。
内閣府が4月5日に日本学術会議幹事会に説明した改正案の資料では、会員選考のルールや人選に意見を述べる選考諮問委員会の委員を選ぶ際に「関係機関と協議」が必要としています。
私は「関係機関とはどこか」と質問。
内閣府は参考事例として「総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)」をあげました。
私はCSTIの議長は総理大臣であることを確認し、「総理が指名したCSTIのメンバーが、学術会議の会員候補選考を左右する選考諮問委員会の人事に深く関与することになるのではないか」と質問。
後藤茂之担当大臣は「総理の関与はないという前提だ。一般論として、(CSTIの有識者が)一人の有識者として自らの経験や識見に基づき判断されることだ」と答弁。
私は「総理直属の司令塔組織であるCSTIの下に学術会議を置くようなものだ」と批判。
後藤大臣は「学術会議幹事会でも様々な意見・懸念が出されていることは受け止めたい」としつつ「政府案は透明性を高めるためのものだ」と答弁しました。
私は会員選考の透明性を言うなら、政府による6人の会員候補の任命拒否こそ不透明そのものだと批判。任命拒否の撤回と法案を提出しないよう求めました。
「議事録」
<第211回通常国会 2023年4月14日 内閣委員会 第13号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
今日は、まず、学術会議法案について質問をいたします。
政府が今国会に提出を予定している日本学術会議法案については、厳しい批判の声が寄せられております。ノーベル賞受賞者とフィールズ賞受賞者の皆さんが、「日本学術会議法改正につき熟慮を求めます」という声明も出されています。その中では、「今回の法改正が、学術会議の独立性を毀損するおそれのあるものとなっていることに対し、私たちは大きな危惧を抱いております。」「政府は性急な法改正を再考し、日本学術会議との議論の場を重ねることを強く希望します。」、このような声明の内容について、重く受け止めるべきであります。
そこで、学術会議の選考ルールの制定や会員候補選考に深く関与する権能を持つ選考諮問委員会についてお尋ねをいたします。
配付資料で、これは内閣府が学術会議の幹事会で説明された資料で、学術会議のホームページにもアップをされているものですが、内閣府の日本学術会議法の見直しの検討状況によると、二枚目の表、横長の方ですが、上の枠囲みのところに、下の方は青い字で書いてありますけれども、選考諮問委員は、科学に関する知見を有する関係機関と協議の上、会長が任命するとあります。
この関係機関とは何を想定しているのかについて御説明ください。
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
まず、政府において進めております見直しは、コオプテーション方式を前提として、会員、連携会員以外の声も聞きながら幅広く、バランスよく選考を進めていく、そういう、学術会議が自ら現在進められている自主的な改革の考え方を踏まえて、国民の信頼確保という観点から、それに制度的な透明性を確保するための枠組みを与えよう、そういうものでございます。
御指摘の選考諮問委員会については、お示しいただいた紙の中身、これ自体はまず検討中という前提でお渡ししたものでございますけれども、学術会議が国民から理解され、信頼される存在であり続けるためには、会員などの選考が透明なプロセスで行われることが必要だろうというふうに考えております。したがって、会員等以外の有識者から成る選考諮問委員会を学術会議の中に設置して、会員などの選考に関する規則、選考について意見を述べるということによって、コオプテーション方式を前提としながら、選考プロセスの透明化を図ろうとしているものでございます。
選考諮問委員会の委員、ここも検討中でございますけれども、その紙にございますとおり、科学に関する研究の動向、これを取り巻く内外の社会情勢、あるいは、産業若しくは国民生活における科学に関する研究成果の活用、そういったことについて広い経験、高い識見を有する方の中から、会員選考に必要な知見を有する人を選んでいく。それは、御指摘のとおり、学術会議の会長が科学に関する知見を有する方と協議して任命するということでございますので、まず、政府が何かプロセスに介入するというようなことは考えておりません。特段、独立性に変更を加えるというようなつもりもございません。
済みません、長くなりました。
その上で、御指摘の選考諮問委員会の任命に当たっての協議先でございます。この点についてもまさに現在検討中でございまして、現時点で申し上げることはできませんけれども、御存じのとおり、平成十六年に学術会議法を改正したとき、このときは、選考プロセスを変えましたので、初回の会員選考を行うために日本学術会議会員候補者選考委員会というものを設置いたしました。それで、その委員会の委員の人選は、客観性、公平性を確保するために、そのときも、科学に関する知見を有する総合科学技術会議の有識者議員、それから日本学士院の院長、そのお二人に学術会議会長が協議して任命したというふうに承知しております。そういった例も参考にしながら、今、検討しているところでございます。
直接申し上げられなくて申し訳ございません。よろしくお願いします。
○塩川委員 配付資料の一番後ろですよね。今、最後に説明された、日本学術会議法の附則の第四条のところに、コオプテーションにする、その前段階のときに会員を選ぶ際に、初回の会員選考に当たってこういったスキームを設けたということですけれども、その際に、日本学士院の院長もありますけれども、総合科学技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するものということになっておりました。
こういうのが一応は念頭にあるという説明を学術会議の方にはされたということですかね。
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、こういった例も参考にしながら検討している、そういうふうに御説明いたしました。
○塩川委員 参考にしながらということですから、これが念頭の一つにあるということであります。
会長が協議を行う関係機関とは、総合科学技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するものを想定しているということで、これは、現在の総合科学技術・イノベーション会議、CSTIのメンバーを想定しています。
CSTIの議長というのはどなたになるんでしょうか。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。
総合科学技術・イノベーション会議の議長は内閣総理大臣となっております。
○塩川委員 大臣にお尋ねします。
総理大臣が議長であるCSTIのメンバーが、学術会議の会員候補選考を左右する選考諮問委員会の人選に深く関与する、こういうことを政府としては想定しているということでよろしいでしょうか。
○後藤国務大臣 今、政府参考人から答弁したとおり、選考諮問委員の任命に当たっての協議先については、平成十六年の例も参考にしながら現在検討しているところでありますから、現時点でお答えできないことについては御理解をいただきたいと思います。
また、選考諮問委員会の委員については、繰り返しになりますけれども、科学に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における科学に関する研究成果の活用の状況、科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者の中から、会員選考に必要な知見を有する人を、学術会議会長が科学に関する知見を有する者と協議の上任命することとしておりますけれども、現在検討中のプロセスにおいて、内閣総理大臣が委員の選考に関与するという考えはありません。
○塩川委員 この選考諮問委員会というものの権能として、選考に係る規則の制定、学術会議側の規則ですよね、並びに会員候補者の選考及び連携会員の任命の際に、あらかじめ同委員会に諮問するとなっています。
つまり、会員選びのルールを作る点、あるいは実際の会員候補者の選考に当たって、あらかじめ選考諮問委員会に諮問するということですから、そういう点でも深く会員候補選考に関与するというのが政府のこの選考諮問委員会の中身であって、その選考諮問委員会、五人と想定しているメンバーを選ぶ際に、会長が任命するとは言いますけれども、ここにあるように、CSTIのメンバーの意見、これをしっかり把握する、こういった、協議の上となっているわけであります。そこのところが非常に大きな重みとなって、学術会議側に関わってくるということになります。
ですから、参考にと言いますけれども、具体の例示としてはCSTIになっているわけですから、内閣府のホームページを見ますと、CSTIは、内閣総理大臣のリーダーシップの下、科学技術・イノベーション政策の推進のための司令塔として、我が国全体の科学技術を俯瞰し、総合的かつ基本的な政策の企画立案及び総合調整を行っているとあります。
総理をトップとする司令塔の役割を果たす政府機関のメンバーが学術会議の会員候補の選考にいわば深く関与、介入するものであり、そのことが学術会議の独立性を侵害するものとなるのではありませんか。
○後藤国務大臣 内容については先ほど申し上げたとおりで、あくまで、平成十六年のときにはこういう方たちに協議をしながら扱ったことがあるということを一つの参考としながら、しかし我々は内閣総理大臣が委員の選考に関与するという考えはないということを前提に、今、制度を検討しているところであります。ですから、こういう内容がそのまま決まりそうだという前提に立ってのお話についてはお答えをすることはできないと申し上げております。
一般論として申し上げるとすると、例えば、政府が任命する審議会の委員等が選考諮問委員の人選に当たって協議を受けることになる場合であっても、一人の有識者として自らの経験や識見に基づいて判断されることとなると考えております。
学術会議の会員についても、総理が任命するものではありますけれども、政府から独立して職務をしっかりと行っていただいているのではないかというふうにも思っております。
○塩川委員 学術会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関であり、独立して職務を行うとあります。いわば、政府の審議会のように政府が求める特定の任務、目的に基づいて議論する会議体とは根本的に違います。その違いの大本にあるのが会員の選考方法、コオプテーション、これに対して、外から介入する仕組みとなりかねないというのが今回の出されている法案で政府が説明している中身だということが極めて重大だということであります。
CSTIで学術会議の在り方の議論をしたときに、CSTIのメンバーの皆さんは、当然、学術会議の梶田会長もメンバーで途中から入っているわけですけれども、梶田会長を除けば、政府の学術会議法改正案について誰も反対をする立場に立っていない、政府案に同調する立場だったという点も看過することができません。やはり総理直属の司令塔組織であるCSTIの下に学術会議を置くようなもので、学術会議を政府の下請機関にしようとするものと言わざるを得ません。法案への批判が広がるのは当然であります。
学術会議の理解も得られていない、こういった法案はそもそも出すべきではないのではありませんか。
○後藤国務大臣 学術会議あるいは五日の学術会議の幹事会においても様々な御意見や御懸念が示されていることはしっかりと受け止めておりますし、そうしたことも踏まえて検討しなければならないというふうに思っております。
学術会議の見直しについては、ただし、学術会議においてもそれぞれ、学術会議自身で、様々な関係者との議論を通じて、令和三年四月の、より良い役割発揮に向けてを取りまとめて、これに基づいて自主的な改革を進めているところであると承知をいたしております。
政府において検討を進めている見直し法案は、学術会議が現在自主的に進めておられる考え方を踏まえた上で、国民の信頼確保という観点から、それに制度的に透明性を確保するための枠組みを与えようとするものだというふうに考えております。
選考プロセスについて申し上げれば、選考諮問委員会の委員も会長が任命し、意見尊重義務はありますけれども、最終的に会員候補者を推薦するのは学術会議であるということであります。
また、諸外国のアカデミーが独立した民間団体でありながら国を代表する地位を認められ、国から財政的支援を受けることを含めて、国民に説明できるよう運営されているのと異なりまして、日本の学術会議は、主要先進国では唯一、国費で賄われる国の機関として独立して職務を行っている、そういうことでありますから、国民の信頼に応えるような、そういう透明なプロセスで行われる会員の選考等の改革は必要なことなのではないか、そのように考えております。
いずれにしても、今国会に提出をしたいということで考えておりますけれども、一層丁寧に学術会議に御説明し、十分に意見を聞きながら、検討を進めていきたいと考えております。
〔委員長退席、藤井委員長代理着席〕
○塩川委員 会員選考プロセスの透明性の向上ということを理由としているわけですけれども、透明性の向上というんだったら、政府が行った、政府による六人の会員候補の任命拒否こそ、不透明そのものなんですよ。そのことについて何らの説明もしないでこういう法案を出すこと自身がけしからぬと言わざるを得ません。ですから、政府がやるべきことは、このような法案を出さない、そして、そもそも任命を拒否したこの六人について直ちに任命する、このことを強く求めるものであります。
学術会議については以上でありますので、大臣は退席いただいて結構であります。
次に、環境省にお尋ねをいたします。
環境省が行っている原発事故由来の除染土再生利用実証事業についてお尋ねをいたします。
所沢では、近隣の地元町会も反対の決議を上げました。所沢の市議会も反対の決議を上げました。市長も、地域住民の理解がなければ分かったとは言わないと述べております。地域の理解は全く得られておりません。撤回すべきではないでしょうか。(小林副大臣「委員長」と呼ぶ)
○藤井委員長代理 ちょっと待ってください。(塩川委員「委員長、ちょっと止めてくださいよ、だったら、時間。止めてよ」と呼ぶ)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
○藤井委員長代理 速記を起こしてください。
内閣府笹川室長。(塩川委員「求めていませんよ。答弁を求めていないんだよ」と呼ぶ)先ほどちょっと手を挙げておられたので、済みません。
○笹川政府参考人 ファクトに関する、事実関係に関する御説明がございますので、一言申し上げます。
先ほど、塩川先生から、CSTIの政策討議についての言及がございました。
その中で、CSTIは、梶田会長を除いて、政府案に賛成であったというたしか御指摘がございましたので、一言だけ申し上げさせていただきます。
このときのCSTIの議論は、政府が何か政府案を提出して審議をお願いしたわけではなく、幅広い視点から自由に御議論いただくということで、一年近く議論をしてきたものでございます。
したがって、梶田会長以外賛成だったというのは若干不正確、不正確と言っては失礼ですが、補足した方がいいかなと思って、済みません、手を挙げた次第でございます。
以上です。
○塩川委員 反対の意見を述べていないということを言ったんですよ。考え方についての議論をやっていたんだから、それについて、政府と立場が異なるような発言がその中に出てこないということを議事録を見て言っているわけですから、そんなことについて、聞いてもいないのにしゃしゃり出てくること自身がおかしいと、この場で強く抗議いたします。
○小林副大臣 塩川委員にお答えをいたします。
環境調査研究所で計画をしている実証事業に関して、周辺自治会において実証事業に反対する旨の決議がなされたこと、また、所沢市議会において、住民合意のない実証事業は認めない旨の決議がなされたことは承知をいたしております。
環境省としては、これまでにいただいた様々な御質問や御意見について、引き続き、丁寧にお答えをしていく姿勢に変わりはございません。
以上です。
○塩川委員 環境省が福島県内で実証事業を計画した二本松市の原セ地区では、事業が中止となっております。原セ地区の事業について、福島地方環境事務所が出した地区住民へのお知らせ文書には、事業着手ができない理由について、説明会において風評被害への懸念など多数の御意見をいただいたため、現時点で事業着手できておらず、計画どおりの工程を進めることが困難となりました、地元の御理解をいただくことが重要であることから、受注者との契約についても解除に向けて調整と述べております。
このように二本松市で事業が取りやめとなったのは、近隣住民の方から反対の声が上がったからということではありませんか。
○小林副大臣 お答えいたします。
環境省では、二本松市内に仮置きをされていた除去土壌を二本松市道の整備に再生利用する実証事業ができないか、二〇一六年から検討しておりました。お述べのとおり、周辺住民に対して複数回の説明会を実施いたしましたが、風評被害への懸念など多数の御質問などをいただきましたが、当時はまだ再生利用の実証事業の前例がなく、御理解いただける具体的なデータをお示しできなかったということであります。
一方、同時期に飯舘村長泥地区でも実証事業を検討しており、そちらの受入れ環境が整ったことから、まずは長泥の案件を優先して実施をし、二本松の案件については見送ることとして、その旨を地元の方々にお知らせをしたということであります。
○塩川委員 風評被害への懸念など多数の意見が出て、地元の御理解をいただくことが重要という立場だから、結果としてやらなかったんですよ。であれば、環境省が実証事業を計画している所沢も、新宿御苑も、またつくばにおいても、みんな住民から反対の声が上がっているわけで、住民の理解が得られない計画は撤回をすべきだということを強く求めて、委員長の裁きは納得のいくものじゃありません、そういったことを改めて抗議をしまして、質問を終わります。
 医療ビックデータ法案(次世代医療基盤法)の改定案を賛成多数で可決しました。日本共産党、れいわ新選組は反対しました。
医療ビックデータ法案(次世代医療基盤法)の改定案を賛成多数で可決しました。日本共産党、れいわ新選組は反対しました。
本制度は本来本人の同意が必要な医療情報の第三者提供を、認定事業者相手に限り本人への通知のみですますことができるものとしています。
私は「本人同意の形骸化につながる」と指摘。実際2022年には認定事業者が通知をせずに95,195人分の医療情報を提供した問題が起きています。
そのうえで他の情報と合わせることで復元可能な「仮名加工医療情報」や、公的データベースとの連結を可能とする「連結可能匿名加工医療情報」を創設する改定案について、個人特定のリスクが高まると批判しました。
高市担当大臣は個人の権利利益が侵害されることを防ぐ仕組みになっていると述べるにとどまりました。
また、医療機関や自治体などすべての医療情報を取り扱う者に対し、国の施策への協力を求める努力規定も改定案に含まれています。改定案が検討されたWGでは、前述の問題を起こした事業者の委員が「病院の協力を得るのが非常に大きな足かせ」「任意というよりほぼ義務化を」と事業者の都合を優先させた発言をしています。
私は「医療情報提供への圧力をかける規定になる」と指摘、医療情報の保護よりも利活用優先、企業利益を優先するあり方を批判しました。
「議事録」
<第211回通常国会 2023年4月12日 内閣委員会 第12号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
次世代医療基盤法案、医療ビッグデータ法案について質問をいたします。
個人情報保護法におきましては、個人の心身に関する情報である医療情報は、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮する個人情報である要配慮個人情報に当たります。要配慮個人情報の取得や第三者提供の際には、あらかじめ本人の同意を得るオプトインの手続が必要であり、本人に通知をした上で本人が停止を求めなければ提供するオプトアウトの手続は認めておりません。医療情報の第三者提供については、オプトアウト手続は認められないということであります。
一方、次世代医療基盤法に基づく匿名加工医療情報は、医療情報の利活用を推進するために、利活用の壁となっているとした本人同意のオプトイン手続を外して、オプトアウト手続としたものであります。
これは、本人同意の手続を形骸化をするものではないのか、その点についてまずお伺いします。
○高市国務大臣 次世代医療基盤法は、個人情報保護法の特例法として、主務大臣の認定を受けた事業者に対する場合に限り、同意でなく、オプトアウト手続によって医療機関から医療情報を提供することを認めるものでございます。
これは、患者などへの丁寧な通知が行われることによって自分の医療情報の提供を拒否する機会が付与されること、認定作成事業者は、十分な安全管理措置が確保されていることなどについて主務大臣から認定を受けるとともに、その監督下に置かれることにより医療情報の慎重な取扱いが確保されること、また、医療機関等から提供された医療情報は認定作成事業者によって特定の個人が識別されることがないよう匿名加工が施された形で利用されることなどによりまして、個人の権利利益が侵害されることを防ぐ仕組みとなっていることによるものでございます。
○塩川委員 やはり個人情報、特にこういった医療情報などの要配慮個人情報というのは、その人自身の個人情報をしっかりとコントロールできるような仕組みにしていくことが必要であって、それについて、丁寧なとはいいながらも、オプトアウト手続ではそれに応えるものとは言えないという点を指摘をしておくものです。
その上で、今回の法改正で措置する連結可能匿名加工医療情報は、公的データベースとの結合で、個人の医療情報が時系列で把握をできるようになります。また、仮名加工医療情報は希少な症例や薬剤使用などの特異な記述も残すので、容易に個人が特定可能となり得ます。
より慎重に取り扱うべき個人情報の第三者提供なのにオプトアウト手続でよいのか、明確な本人同意の手続を取るべきではないのか、この点についてお答えください。
○高市国務大臣 NDBなどの公的データベースとの連結を可能とする連結可能匿名加工医療情報につきましては、あくまでも匿名加工し、本人を特定できない形で提供するものでございます。従来の匿名加工医療情報と同様の理由によりまして、適切に個人の権利利益の保護が図られると考えております。
また、新たに創設する仮名加工医療情報については、匿名加工医療情報と同様に、患者さんへの丁寧な通知が行われることによって、自分の医療情報の提供を拒否する機会が付与されております。
また、認定作成事業者は、十分な安全管理措置等が確保されていることなどについて主務大臣から認定を受けるとともに、その監督下に置かれることにより医療情報の慎重な取扱いが確保されます。
また、医療機関などから提供された医療情報は、認定作成事業者により、その情報だけでは特定の個人が識別されることがないよう加工された形で、安全管理措置を適切に講じる体制を有する者として国の認定を受けた利用事業者に限って利用を認めることによって、個人の権利利益が侵害されることを防ぐ仕組みとしております。
このため、同意ではなく、オプトアウト手続により、医療機関などから認定事業者への医療情報の提供を認めるものでございます。
○塩川委員 仮名加工情報は、本来、第三者提供が禁止されておりますが、仮名加工医療情報は本人通知のみで第三者提供を可能としております。個人情報保護の規定の緩和ばかり進めているというのが実態であります。
そこでお尋ねしますが、匿名加工医療情報について、利用の停止を求める意思表示がされた件数及び割合はどうなっているのかについてお答えください。
○西辻政府参考人 お答え申し上げます。
次世代医療基盤法におきましては、医療機関等から本人に通知を行う方法として、インターネット掲示や院内掲示など単に本人が容易に知り得る状況に置くのではなく、あらかじめ本人に通知するということを求めております。
オプトアウトの具体的な件数、割合でございますが、正確に把握しているわけではございませんが、認定匿名加工医療情報作成事業者において一定の期間におけるオプトアウトが行われた割合については、おおむね一%未満であったというふうに聞いております。
○塩川委員 オプトアウトの手続で、拒否が一%未満ということでありました。
もう一つお尋ねしますが、難病患者データベースや小児慢性特定疾病患者等のデータベースにつきまして、本人同意を基に医療情報を取得をするとなっておりますが、この難病DBや小慢DBについて、同意を拒否した件数及び割合がどうなっているのかについて御説明ください。
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
厚生労働省の健康局難病対策課で実施した平成三十年のウェブアンケートによりますと、難病患者では、毎回同意していないが二%、同意していないときも何度かあったが一〇%、小児慢性特定疾患患者等では、毎回同意していないが一%、同意していないときも何度かあったが一二%となってございます。
アンケートでございますので、件数は承知しておりません。
○塩川委員 今お答えいただきましたように、オプトアウトの匿名加工医療情報の場合に拒否は一%未満でしたが、オプトインの難病データベースや小慢データベースの場合には十数%が拒否のときがあるということであります。難病患者や小児慢性特定疾病患者で医療情報提供に同意しない理由として、個人情報をむやみに提供したくないからという回答も多かったわけであります。
大臣にお尋ねしますが、やはりオプトアウト手続では、このような本人の意思表示が明確にされないのではないかと思いますが、お答えください。
○高市国務大臣 次世代医療基盤法は、医療情報について匿名加工又は仮名加工を施した上で利活用を行う制度ではございますが、その利活用につきましては、患者さん御本人に対してしっかりあらかじめ認識をしていただくことが重要であると考えております。
ですから、同法におけるオプトアウトでは、ウェブページへの掲載など単に患者本人が知り得る状態に置くということではなく、御本人が認識する機会の確保の観点から、あらかじめ本人に対して通知することを求めております。
通知の手段としましては、その内容が御本人に認識される適切かつ合理的な方法により行うことを求めております。主に医療機関の窓口などにおいて患者さん御本人に対して書面などを用いて通知が行われていると承知をしております。
また、通知に関しましては、十六歳未満の方については保護者に対しても通知を行うことや、障害をお持ちの方や高齢者に対しては十分な配慮を行うこと、また、さらには御本人またその御遺族などからの問合せに係る窓口機能の確保なども求めております。
患者本人の皆様などに対して本制度をしっかりと認識していただいた上で、医療情報を提供していただく仕組みを構築いたしております。
○塩川委員 これまでオプトインで行っていた難病の場合などにつきましては、イエス、ノーにチェックをする、あるいは署名をするという形での明確な意思表示というのがあるわけですけれども、オプトアウトの場合には通知ですから、そういう点でも非常に本人の意思表示というのが明確にされるような状況にないということを指摘をし、個人情報保護の根幹である本人同意の手続がなし崩しとなるといった点が強く危惧されるものであります。
一方で、医療情報を利活用する事業者サイドを見ますと、要配慮個人情報である医療情報に対する適切な取扱いが軽んじられている。このことは、昨年の、認定事業者であるライフデータイニシアティブとNTTデータが第三十条に基づく本人への通知を行わずに計九万五千百九十五人分の医療情報を提供した、プライバシーの侵害が懸念される、こういった事態があったことも極めて重大であります。
そこで、今回の法改正で、医療機関や介護事業所、自治体、学校等に対し、国の施策への協力の努力規定が盛り込まれております。
本改正案に向けた検討の場でありますワーキンググループでは、さきに示した問題を起こしたLDIの委員の方が、病院の協力を得るのが非常に大きな足かせだ、今の法律では医療機関からデータを出すのはあくまでも任意、ここが非常に効率も悪いし、一診療機関当たり五百万ほどの費用が必要になってくる、データ集めは義務化してほしいと要求するなど、事業者の都合を優先する発言を行っております。
医療提供取扱事業者には医療情報提供の義務づけはないのに、医療情報提供への圧力をかける、そういう規定になってしまうのではないのかと強く懸念するところですが、この点、いかがでしょうか。
○高市国務大臣 この改正法で新設する協力規定でございますが、医療分野の研究開発を推進するために医療情報の利活用がますます重要となる中、収集する医療情報の充実を図るために、本法の趣旨を医療機関や地方自治体などに御理解いただき、御協力をお願いする目的で設けるものでございます。
今回の協力規定を設けた後も、医療機関などが本法に基づく医療情報の提供を行うかどうかは任意でございます。さらに、医療機関などから提供する旨の通知を受けた患者さんが協力することも任意でございます。
医療情報の提供は任意であるということを前提に、医療情報を研究開発に利用することの意義、またその成果を分かりやすく広報してまいりたいと存じます。
○塩川委員 任意といいながら、医療情報の提供を求めていくといったことが新たに規定で盛り込まれるわけですから、関係の、医療情報についての、医療提供の取扱事業者に新たな大きな負担、負荷をかける、こういった点でも、それぞれの国民への、個人情報の提供、医療情報の提供を促進するという流れを強める点でも懸念するものであります。
次世代医療基盤法の見直しに当たって、経団連の要望書では、医療機関による通知の事務負担軽減のためといって、ポスターに印刷されたQRコード等によりスマホ上での通知文書の誘導、閲覧をもって通知とみなすことについても検討すべきだといった要求も出されています。
こういった利活用優先、個人情報保護軽視の姿勢は許されないと思いますが、この点、いかがですか。
○高市国務大臣 あくまでも、個人情報をしっかりと保護した上で、貴重な医療情報の活用を促していくということでございます。
○塩川委員 事業者サイドでは、より一層情報収集がしやすいような、そういうスキームということで個人情報保護の規定をどんどん後退させる、こういった要求が背景にあるということは極めて問題があるわけで、現在の認定医療情報等取扱受託事業者はNTTデータ、日鉄ソリューションズ、日立製作所の三社でありますが、一方、医療ビッグデータを推進する国の機関を見ると、健康・医療戦略室に日立製作所、デジタル庁にNTTデータ、日鉄ソリューションズ、日立製作所がある。国の組織体制では、医療情報の保護よりも利活用優先、企業利益を優先する構図となっている。こういった組織の構成そのものが問題があるということを最後に指摘をして、質問を終わります。
秋山もえ県議は、コロナ禍に施設職員のPCR検査や薬局での無症状者への検査を実現。保健所関係職員93名の増員をかちとった。自民・公明・民主が鴻巣保健所上尾分室廃止に賛成した時に、反対貫いたのが共産党。秋山勝利で上尾・伊奈地域に保健所新設を!
 秋山もえ候補の勝利で学校給食費の無償化を!地場産・有機食材を使い、オーガニック給食の実現を!上尾市議会では、学校給食費の無償化を求める請願に自民・公明は反対。
秋山もえ候補の勝利で学校給食費の無償化を!地場産・有機食材を使い、オーガニック給食の実現を!上尾市議会では、学校給食費の無償化を求める請願に自民・公明は反対。
しかし、市民運動と共産党の論戦で、岸田首相も「学校給食費の無償化に向けた課題整理を行う」と言い始めた。秋山勝利で実現を!
秋山もえ候補は障害者支援に全力。自ら手話を学び、県知事記者会見や県議会本会議での手話通訳配置を実現。自・公・民が特別支援学校の計画的増設求める請願を否決しても、市民と共に、上尾南分校始め、特別支援学校12カ所の建設・増設、千人の定員増を実現。今度は高齢難聴者への補聴器補助の実現を!
 国土交通省の元事務次官である本田勝氏らが、同省と利害関係のある民間企業「空港施設」の人事に介入した問題をただしました。同省は事務方ナンバー2の国土交通審議官に聞き取りすらしていないなどずさんな調査が浮き彫りとなりました。
国土交通省の元事務次官である本田勝氏らが、同省と利害関係のある民間企業「空港施設」の人事に介入した問題をただしました。同省は事務方ナンバー2の国土交通審議官に聞き取りすらしていないなどずさんな調査が浮き彫りとなりました。
同省は4日、国土交通委員会理事会に、現職職員による再就職のあっせんと、OBから同省への働きかけ、いずれも「確認できなかった」との報告書を提出しています。
私は、聞き取りは国土交通審議官からも行ったのかと質問。
国交省は「確認は行っていない」と認めました。
私は、2011年にも、当時国土交通審議官だった宿利正史氏が天下り人事の差配をし、13年に違法性が認定されていることを指摘し、その国交審議官に確認すらしないで「まともな調査と言えるのか」とさらなる調査を要求。
国交省は「調査の対象は適切だ」と調査を拒否しました。
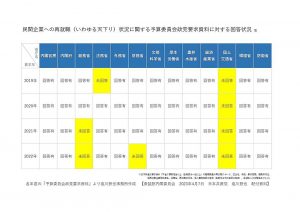
私は、本田氏が2011年当時、官房長として、実際には違法だった天下りを「シロ」だとする報告書に関与した人物であることは重大だと指摘するとともに、国交省は日本共産党が要求してきた天下りに関する資料に2019年以降未回答を続けているとして「国交省は天下りを是正するつもりがない」と批判。
OBの人事に口を挟めば違法となるため表立って動けない現役幹部に代わって「OBを介して天下りのあっせんを行っていることが当然想定される」と強調し「徹底調査を行え」と追及しました。
松野官房長官は「一般論として法規制の対象に当たらないOBについて、国交省として調査する立場にない」と答えました。
私は、国交審議官への聞き取りを含めた徹底調査を求めるとともに、天下りそのものを禁止せよと主張しました。
「議事録」
<第211回通常国会 2023年4月7日 内閣委員会 第11号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
今日は、国交省の幹部OBが国交省と利害関係のある民間企業、空港施設の人事に介入した問題について質問をいたします。
国交省にお尋ねしますが、国交省作成の、国土交通委員会の理事会に提出した説明ペーパーの中に、国土交通省幹部職員への確認とありますけれども、どの幹部に確認したのか。この確認したという幹部職員が誰かをまず教えてもらえますか。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
まず、三月二十九日、これは新聞報道が出る前ですけれども、三月二十九日に朝日新聞からの取材がございました。これを受けて……(塩川委員「幹部職員が誰かだけ答えて」と呼ぶ)はい。
実は、三回、確認行為を行ってございます。
今申し上げた取材を踏まえまして、航空局内で関与の有無を確認するとともに、翌日の三十日の新聞報道を踏まえ、国土交通大臣から事務次官へ、そして事務次官から官房長や航空局長へ、さらに大臣官房人事課長からその他の関係幹部へ、関与の有無を確認しております。
さらに、四月二日に新聞報道が出たことを踏まえまして、大臣官房人事課長より、報道に名前が出てきました山口氏が空港施設株式会社の代表取締役に就任した時点の航空局長など関係幹部、さらに、空港施設株式会社に入社して以降の東京航空局長経験者、これらの方々へ関与の有無を確認しているところでございます。
○塩川委員 国土交通審議官、省名審議官とかには確認されたんですか。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
審議官についてお尋ねがありましたけれども、三月三十日におきましては、先ほど大臣から次官、次官から官房長と申し上げましたけれども、そのほか、大臣官房人事課長から航空局の本省部長級、審議官級の三名、さらに、本省課長級の六名に対して、関与の有無を確認しているところでございます。
さらに、四月二日の新聞報道を踏まえまして、改めて、先ほど申し上げた山口氏が空港施設株式会社の代表取締役に就任した令和三年五月時点での航空局長、航空局の本省部長、審議官級の三名、さらに、本省課長級の六名、加えて、山口氏が同社に入社した令和元年十二月以降の東京航空局長経験者、この方々に対して関与の有無を確認したところでございます。
○塩川委員 省名審議官に確認したのかということを、もう一回、ちゃんと答えてよ。
○宮路委員長代理 加藤総括審議官、端的にお答えいただけますか。
○加藤政府参考人 国土交通審議官に対しましては確認は行っておりません。
○塩川委員 私、国交省の天下り問題は、二〇一一年のときにこの内閣委員会で何度か取り上げたことがあります。国交省が組織的に天下り人事を行っているということを告発しました。その後、二〇一三年に再就職等監視委員会が違法認定をいたしました。
どういった案件だったのか、説明をいただけますか。
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の事案につきましては、二〇一一年当時、国土交通審議官であった職員が、ある二つの団体の理事長に対し、当該団体の役員ポストが空くかどうかの情報提供を依頼し、また、うち一つの団体には、国交省の元職員が無職であろうとの情報を提供したことなどが認められたものでございます。
こういった行為が、元職員を再就職させる目的で、営利企業等の地位に関する情報提供を依頼したり、当該者に関する情報を提供することなどを禁ずる国公法第百六条の二第一項の規定に違反する行為に該当すると認定されたものでございます。
以上でございます。
○塩川委員 再就職規制、国公法違反が認定される二件、そういったことを明らかにしたということですけれども、そのときに、では、誰がやったかというと、省名審議官だったわけですよ、国土交通審議官。つまり、そのときの旧運輸省のトップが実際に旧運輸省系の天下り人事を差配をしていたといったことが違法に問われたわけであります。国土交通省の事務次官を務めた宿利正史氏が国土交通審議官のときに、元幹部職員の天下りで口利きを行ったとして、政府の再就職等監視委員会が国公法違反と認定した案件であります。
私は、玉突き人事ですとか、こういった人事について調査と、天下りそのものの禁止を求めてきたところですけれども、そこで、国交省OBの副社長を社長にするよう求めたという本田勝元事務次官ですけれども、旧運輸省出身で、二〇一一年の私の質問当時は官房長だったと思いますが、それでよろしいですか。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
大変申し訳ありません、事前に御通告いただいておりましたので、本田の経歴の詳細については、今、手元に用意してございません。
○塩川委員 二〇一一年のこの不祥事を私が質問したときに、国交省として報告書を取りまとめているわけですよ。そのときに、二〇一一年の九月から官房長だったのがこの本田勝氏ですから、その関わりについては承知していないんですか。
この報告書がどういう中身かということは、事前にも要請しているわけですけれども、それについて答えてもらえますか。
○加藤政府参考人 お答えいたします。
平成二十三年二月そして三月にかけてなされました、委員御指摘の、当時在職中であった国土交通審議官による言動が国家公務員法で禁止された再就職のあっせんに該当するのではないかという点、これにつきまして、平成二十三年八月から十一月にかけまして、国土交通省において国土交通副大臣を委員長とする調査委員会を設置いたしまして、当事者からヒアリング等を通じた調査を行ったところでございます。
○塩川委員 副大臣をトップにした調査委員会、その際に取りまとめた報告書、これは当然、官房長だった本田勝氏が関与していますよね。
○加藤政府参考人 平成二十三年八月から十一月にかけて行われました調査、その結果につきまして、省内の幹部で共有されているものと考えております。
○塩川委員 当然、官房長ですから、人事について統括しているわけで、こういった調査委員会をやっていた人なんですよ。
本田勝さん自身が、その後、省名審議官、国土交通審議官にもなり、事務次官にもなっているんです。二〇一一年の案件で、二〇一三年に再就職監視委員会で違法が認定された際、その二件に関わっていた宿利氏に次いで、旧運輸省畑で、その後、事務次官に上がったというのが本田勝氏なんですよ。旧運輸省関係の人事をいわば統括をする、こういう立場でやってきた方であって、そういった人が今回名前が出ているというところについて、やはり深く関与があるんじゃないかということを考える必要があると思うんです。
二〇一一年の事件のときには、旧運輸省のトップの省名審議官が実際に差配をしていた。今回の案件について、現役はどういうふうに関与していたかということがきちっとまず確認されなければいけないのに、現役職員の国交審議官、旧運輸省畑の人を含めて調査もしていないんですから、これでまともな調査と言えるのかということがあるわけであります。
ですから、そもそも二〇一一年当時の調査そのものが極めて問題があった。つまり、二〇一一年当時、二回質問をして、それぞれ国交省が調査を行って報告を出したんですが、その二回とも、当然のことながら、国交省としては白という結論だったわけです。それなのに、二年後に、少なくとも再就職監視委員会はそのうちの二件について違法を認定するということだったわけですから、こういった調査報告、黒だったものを白と認定したような調査報告を取りまとめた中心にいたのが本田勝氏だったということも、リアルに見ておく必要があると思います。
国交省のこの白という結論は再就職監視委員会の調査結果で覆されたわけでありまして、本田氏を始め、国交省がまともな調査をするつもりがなかったということが、ここに示されているということが言えると思います。
その上で、資料をお配りいたしました、各省の再就職、天下りなど、人事に関する予算委員会要求資料、日本共産党として毎年要求しておりますけれども、見ていただきましたように、この再就職、天下り状況に関する資料について、未回答の役所というのが幾つか残されているわけであります。
それを見ると、国土交通省については、二〇一九年以来ずっと未回答のままを続けているわけであります。これは国会の行政監視の発揮に当たって極めてゆゆしき問題だと思っておりますが、何でこんなふうに未回答なんですか。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
本件につきましては、資料要求の対象期間が過去十年となっておりました。一方で、国土交通省における職員の退職後の民間企業等への再就職の届出に関する資料の保存期間、これは一定期間、三年に限られているというところでございます。こうしたことを踏まえますと、要求への対応が困難でございますので、提出を行っていなかったと承知しております。
一方で、保存期間内のものについては、提出は可能でございます。このため、今後、同旨の資料要求がなされた場合には、要求者の御了解をいただけるということを前提に、しかるべき対応を図ってまいりたいと考えております。
○塩川委員 そんな説明を一言もしないで、未回答のままなんですよ。これは誠実な対応だと言えるんですか。ほかの役所は出しているんだから。なぜ出せないのかといったことについて、こうすれば工夫ができますとか、この点があるのでお答えがなかなか困難ですとか、そういうことも何にもなしに、未回答のままでずっとやっている。このこと自身が、まともに、こういった天下りについて明らかにするつもりがない、要するに隠したいと思っているんじゃないのかということを言わざるを得ません。
それで、官房長官にお尋ねしますけれども、私、今回の事件を考えたときに、要は、これまで、現役の方が、トップの幹部が実際に天下りを差配をしていた、それをこういった形で違法性が問われたものですから、直接現役が表立って動けないということをもってOBを介して行っているんじゃないのか、こういうことが当然のことながら想定をされるわけであります。
現役幹部がOBの人事に口を挟めば違法となる。そのため、現役幹部の代わりに幹部OBが天下りに関与しているのではないのか。こういったことについて、この資料を出すことを含めて徹底調査すべきだと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。
○松野国務大臣 塩川先生にお答えをさせていただきます。
空港施設株式会社の件につきましては、一般論として、法規制の対象に当たらないOBの行動について、国土交通省としては調査する立場になく、またその権限も有しないところでありますが、国土交通省が関与しているという誤解を招きかねないものであることから、国土交通大臣の指示の下、本田元国土交通事務次官及び山口元東京航空局長の両名に対し具体的かつ詳細な聞き取りが行われ、その結果、現役職員の関与が疑われる事実は確認できなかったものと承知をしています。
さらに、関係する部門の幹部職員に対して確認を行った結果、現職職員による空港施設株式会社への再就職のあっせん、OBから国土交通省に対する働きかけのいずれについても確認できなかったと聞いています。
いずれにせよ、引き続き、国土交通省において適切に対応していくことが重要であると考えております。
○塩川委員 国土交通審議官がOBに働きかけしたかどうか、確認していないんですよ。それぐらい、確認しろという指示、出せませんか。
○宮路委員長代理 既に持ち時間が経過しておりますので、最後、加藤総括審議官。
○加藤政府参考人 お答えします。
今般の調査の対象につきましては、空港施設株式会社の役員人事に係るあっせんを行い得る者、あるいは、空港施設株式会社、当時の代表取締役である山口氏から不当な働きかけを受け得る者として、一般的に想定し得る者を調査対象としたところでございます。今回の報道を踏まえた調査の対象としては適切であると考えております。
○塩川委員 かつては国交審議官が天下りに関与していたということが違法だと問われたわけですから、そういった対象の人をしっかり調べるのは大前提でありますし、そういう調査を求めるとともに、天下りあっせん禁止ではやはり駄目なんですよ。天下りそのものを禁止することが求められていると思いますし、少なくともOBを介した再就職あっせんは禁止をすべきだということを求めて、質問を終わります。
 フリーランスの取引適正化と就業環境を整備する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」が、衆院内閣委員会で、全会一致で可決されました。
フリーランスの取引適正化と就業環境を整備する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」が、衆院内閣委員会で、全会一致で可決されました。
フリーランスという働き方は報酬の支払い遅延や一方的な契約内容の変更などのトラブルが多発する一方、法的保護が弱いことが問題とされてきました。
わが党はこの間、労働者性を拡張・適用してフリーランスを保護することを求めてきました。
質疑で「労働者性があいまいなフリーランス就業者は、労働者でありながら企業に自営業者に偽装される場合や、従属性のある自営業者にされる場合がある」と指摘。「本案が偽装雇用の背中を押すようなやり方になってはいけない」として、労働者として保護の対象を拡大するよう訴えました。
後藤茂之担当大臣は「必要な場合は、既存の法律で保護される」との答弁に留まりました。
私は、取引の適正化についても、長時間労働を強いる納期や締め切りの規制を設けることも必須だと述べ、「フリーランス保護においても、業種業界ごとにガイドラインを制定し、運用する必要がある。所管省庁と業界が協議して、ふさわしいルール作りを促す働きかけをぜひやってほしい」と求めました。
「議事録」
<第211回通常国会 2023年4月5日 内閣委員会 第10号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
フリーランス法案について質問をいたします。
今回の法案の策定過程におきまして、そもそもフリーランスに対しての保護をどういうふうに行っていくのかといった制度の検討が行われてきたわけですけれども、この法案については、労政審には報告だけで、議論が行われておりませんでした。
昨年九月の労政審雇用環境・均等分科会において、労働者代表委員が、労働側として唐突感、違和感があるとして、世界的には、新たな就業形態に対応した法的保護に関しては、労働者性を認める方向で保護を図っていこうという取組が進んでおり、日本でも労働者性の早急な見直しは必須であり、労政審で検討すべきだと述べておりました。
大臣、お尋ねしますけれども、このフリーランスの対応につきまして、労働者性の拡張についての見直しを行うことは必須ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○後藤国務大臣 使用者に対し立場が弱い労働者が劣悪な環境で働くことがないように、労働基準法は、事業又は事務所で使用される者で、賃金を支払われる者を保護すべき労働者と定義した上で、使用者が遵守しなければならない労働条件の最低基準を定め、罰則をもって担保をいたしております。
その上で、労働者の具体的な判断基準を明確にする観点から、それまでの裁判例等を基にしました判断基準を定めまして、労働者として保護されるべき者か否かを実態を勘案して総合的に判断しております。
いわゆるフリーランスと呼ばれる方でありましても、実態を勘案して総合的に判断した結果、労働者性があると判断されれば、労働基準法等に基づいて労働者として必要な保護を図っていく。また、フリーランスの労働者性の判断基準については、令和三年三月に策定したガイドラインにより周知を図ってきております。
一方で、労働基準法による労働者の範囲を拡大することによりまして、フリーランスを労働基準法上の労働者として、発注事業者に使用者と同様の義務を課すことにつきましては、発注事業者に過大な義務を課すことになりかねないといった法制的な課題、フリーランスへの発注控えにつながり、就業機会の縮小を招く可能性があるなど、課題が多いと考えております。
一方で、我が国でフリーランスが直面しているトラブルについて見ますと、事業者間取引において見られるものが多く、また、ハラスメントなどのトラブルについても取引上の力関係に由来しているものと考えることができることから、本法案は、取引適正化等を図る法制として立案し、対策を講じたものでございます。
○塩川委員 フリーランス・トラブル一一〇番の相談で、この間、社員からフリーランスに変更される事例が増えているという話もされております。事務とか営業とかマッサージとかスポーツインストラクターとかなどが多いということですが、雇用契約を業務委託契約に変更する、雇用契約にしたらもうからないからとうそぶくような企業もあったということであります。
このようなトラブルに対しては、契約の形式にとらわれず、実態判断をして労働者保護をかけると言っておりますが、実際には、労基署にかけ合っても、契約の形式が委託であれば門前払いされてしまうケースが少なくない。
こういった現状、実態を踏まえた場合に、このような今起こっている問題に対処できるように、労働者性の拡張の議論を行うべきではありませんか。
○後藤国務大臣 労働基準法等の適用については、業務委託や請負等の契約の名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断することになっておりますし、いわゆるフリーランスと呼ばれる方であっても、こうした判断の結果、労働者と認められる場合には、今回の新法とは関係なく、労働基準法等の適用をしてまいります。
引き続き、労働基準監督署においてもこうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者性の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図りまして、労働基準法等による保護が適切に行われるように努めてまいりたいと思います。
○塩川委員 実態を勘案してといっても、そうなっていない実態というのも現にあるわけですから、そういった点におきましても、この一九八五年の労基法上の労働者性の判断基準がいわば古くて狭いといった点が今問われているわけで、その見直しが必要であります。
ILOにおいては、労働者性が曖昧な就業者は、本来は労働者でありながら、企業が故意に自営業者に偽装する場合、いわゆる偽装雇用と、従属性のある自営業者、従属的自営業者に分かれ、偽装雇用については誤分類の修正、従属的自営業者には一定の保護を提供する必要があるとしています。
ですから、この両面での法的措置が必要なんじゃないのか。つまり、従属的自営業者についての一定の保護、今回のフリーランス法案としてそういう対処というのは必要なものと考えています。同時に、やはり偽装雇用になるような今の現状というのが率直に言ってあったときに、労働者性の拡張、こういった議論が法的措置も含めて必要ではないのか。改めてお尋ねします。
○後藤国務大臣 偽装雇用と考えられるようなケースについては、実態判断として、法律的な形式は別として、そこはしっかりと労働基準法等の適用をしていくということで、そういった意味での対応は今後ともしっかりと進めてまいりたいと思います。
○塩川委員 JILPTのフリーランスの労働基準法上の労働者性に関する調査を見ましても、労働者性が高いとか中程度というのを合わせると七一・九%、七割以上が労働者に近い働き方をしているという傾向が示されております。まさにそういう労働者に近い働き方をしているという実態があるといった点でも、フリーランスの保護は労働者性の適用を広げる方向を検討、具体化をすべきだということを重ねて求めたいと思いますが、改めて、いかがでしょうか。
○後藤国務大臣 重ねて同じ答弁では恐縮なんでありますけれども、基本的には、労働者性の認められる方について言えば、それは、どんな法律形態であろうとも、労働者として必要な保護をしていくわけでありますけれども、労働者の範囲を拡大することによって、フリーランスを労働基準法上の労働者として、発注事業者に使用者と同様の義務を課すことについては、法制的な課題、例えば、雇用関係において見られるような使用従属関係があるとは言えないために、発注事業者に対して使用者と同様の義務を課すことができるのかどうかといったような課題をしっかりと整理する必要がありますし、また、フリーランスへの発注控えにつながり、就業機会の減少を招く可能性があることなども課題としてあるというふうに思っております。
そうした観点から、今回の取引法に基づく対応という形で検討をいたしております。
○塩川委員 この間、政府として、多様な働き方といった形で、偽装雇用を背中を押すようなやり方になっては決してならないわけで、そういった点での政府の対応がこの点でも極めて不十分だということを言わざるを得ません。改めて、労働者性の拡張、これはしっかりと宿題として行うべきだということを強く求めておきます。
その上で、実態として、労働基準法や労働契約法、労働組合法が定める労働者に当たるフリーランスについては、この法律の制定をもって、こういった労働関係諸法令による救済が否定されるようなことがあってはならないと思いますが、改めて確認をいたします。
○後藤国務大臣 これはもう先生がおっしゃるとおりであります。
今回の法律を作ることによって、フリーランスの取引法による規定で十分だというようなことにならないように、実際に、労働基準法等の適用については、業務委託とか請負とかの契約の名称にかかわらず、総合的に判断をして、しっかりと適用を図っていく。引き続き、労働基準監督署においてもこうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者性の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図って、労働基準法等による保護が適切に行われるように努めてまいりたいと思います。
○塩川委員 法案に関わって何点かお尋ねをいたします。
やはりフリーランスで働く方々の報酬が余りにも低いといった点も問われてまいります。その点で、最低報酬規制、こういった仕組みを設ける必要があるのではないのかという点であります。
この間、政府として具体化している取組の中で、自営型テレワークのガイドラインなどもあります。そこにおきましては、例えば、最低賃金を一つの参考として自営型テレワーカーの報酬を決定することも考えられるとあります。
従事者の報酬の最低規制を図る、こういった工夫というのが行われる必要があるのではないのかと思いますが、お答えください。
○後藤国務大臣 本法案では、いわゆるフリーランスを保護する観点から、下請代金法では規制対象にならない資本金一千万円以下の小規模な発注事業者であっても、フリーランスに委託を行う場合には発注書面の交付等の義務を課すことといたしております。
他方、事業者間取引における契約自由の観点からは、原則として、事業者取引に対する行政の介入は最小限にとどまるべきであるということに加えまして、小規模な発注事業者に対して過剰な義務を課した場合には、発注事業者が義務履行に係る負担を避けようとして特定受託事業者と取引することを避ける、いわば発注控えが生じること、財政基盤が脆弱な発注事業者も多く、義務が負担となり経営に支障を来すことも懸念されることから、規制内容はできるだけ限定することが適当であるというふうに考えております。
さらに、特定受託事業者の役務や成果物は多種多様であることから、一律の最低報酬を定めることは困難であるとも考えられます。
したがって、本法案において、特定受託事業者の最低報酬に係る規制を盛り込んでおりません。
○塩川委員 業種、業態は多種多様で、一律の最低報酬を定めるのは困難という話もありました。
そういう際にも、やはり業種、業態においてはいろいろな工夫もできることだろうと思ってはいます。お話を伺っている中では、例えば音楽家の方々の組合などにおきましては、演奏における時間、そこに最低時給というのを設けて、テレビ局の各局と交渉して協定を結んでいるといった格好での最低報酬のルール作りなどが行われているわけであります。
そういった現場で行っている取組も含めて、しっかりとやはり、労働者でいえば最低賃金に相当するような、こういったことを担保できるようなフリーランスにおける最低報酬規制というのは考えられるべきだと思っております。
もう一つ、長時間の作業時間を強いる納期や締切りの規制の問題であります。
この点も、自営型テレワークのガイドラインなどでは、成果物の納期については、作業時間が長時間に及び健康を害することがないように設定をすること、その際、通常の労働者の一日の所定労働時間の上限八時間を作業時間の目安にする、こういうことなんかも示されているところであります。
こういった長時間の作業時間を強いるような働かされ方を一定規制をする、そういう仕組みづくりというのが必要ではないでしょうか。
○後藤国務大臣 フリーランスの方についても、今先生御指摘のように、働き過ぎにより健康を害することのないように配慮をすることは非常に重要なことだと思います。
この点、現在、厚生労働省では、個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会を開催しまして、その中で、フリーランスの方々の作業時間が長時間に及び健康を害することのないようにすることも議論していると聞いております。この有識者検討会における検討結果も踏まえて、厚生労働省において適切な対応が取られていくものと考えております。
○塩川委員 やはり長時間労働を強いる、健康にも支障を来すような、そういった働かされ方がなくなるような仕組みづくりというのは必須ということを改めて強調しておきます。
今回のフリーランス法案、審議をしていて、当然、広く適用する、そういった多様な業種、業態の中において、業種横断的な規制という点では一定の制約というのは出てくるわけですけれども、やはり業種、業態に対応したような様々な工夫をする必要があるんじゃないのか。
そういう点では、下請取引の適正化におきましては、業界、業種ごとにガイドラインを策定をして、遵守状況のフォローアップですとか、ガイドラインの改定なども行われてきております。今回のフリーランス保護においても、業種、業態ごとにこういったガイドラインを設ける、それで運用していく、そういったことは必要なことではないかと思うんですが、この点についてはどうでしょうか。
○後藤国務大臣 下請取引適正化の取組においては、今御指摘もあったように、業種別の取引実績等を踏まえた対応が有効でありますことから、各業所管省庁において、下請法や独禁法の違反事例やベストプラクティス等についてまとめたガイドラインを作成して、業界に遵守を呼びかけているわけであります。
他方で、フリーランスについては多種多様な業態が想定されることから、今回の法案が成立すれば、その施行後の状況等を分析し、まずは業種別の課題、例えば映画産業だとか食品産業だとか、そうした課題の把握にまず努めることとしたいと考えています。
○塩川委員 結構、所管省庁と、それから関連する業界団体などが協議をされて、今、映画の話ですとか食品の話がありましたけれども、芸能関係者、あるいはウーバーのようなデリバリーの話、あるいは一人親方ですとか放送コンテンツ、それぞれの所管省庁が、関連する業界、フリーランスの方と協議をして、そういった点でのふさわしいルール作りを行っていく。こういうところは更に踏み込んできちっと行っていく。だから、関係の所管省庁がしっかりと対応するといったことを促す働きかけを是非やっていただきたいと思うんですが、改めて、いかがでしょうか。
○後藤国務大臣 いわゆるフリーランスについて言えば、大変に、取引、その実施される状況については多種多様で、実態についても今後把握していく必要があるというふうに思いますけれども、今御指摘されたような問題意識を持ってしっかりと分析をしていきたいと思います。
○塩川委員 業種ごとの標準契約書を作る、こういったことなんかも含めて、実際に有効に運用される、そういう取組につなげることを改めて求めて、質問を終わります。