地方選の予定候補紹介。県議予定候補の酒井ひろあき県議(前橋)、大沢あや子さん(高崎)、小林その子さん(伊勢崎)が決意表明。
 政府の「構造的な賃上げ」とは、雇用の流動化=リストラ推進。「グリーン」と言って原発推進。「平和」のためにと大軍拡大増税。国民だます政治の転換を!
政府の「構造的な賃上げ」とは、雇用の流動化=リストラ推進。「グリーン」と言って原発推進。「平和」のためにと大軍拡大増税。国民だます政治の転換を!
物価高騰の中、年金削減や医療費の負担増などとんでもない!
しかも大軍拡大増税など許せません!
物価高に最も効果のある消費税の5%への減税を!
自営業・フリーランスを廃業に追い込むインボイスは中止を!
岸田政権の大軍拡大増税はストップを!
インボイス中止消費税減税訴え/埼玉で塩川氏ら宣伝
「しんぶん赤旗」12月28日・首都圏版より
消費税の廃止を求める埼玉連絡会は23日、消費税率5%への減税、インボイス中止を求め、さいたま市の大宮駅西口で宣伝しました。埼玉土建、民商、新日本婦人の会、埼労連など7団体から42人が参加しました。
各団体の代表がリレートークし「今すべきは大軍拡・大増税ではなく、消費税減税や賃上げだ」「農業も商店街も文化の担い手のフリーフンスも疲弊させるインボイスは中止を」と訴えました。
日本共産党の塩川鉄也衆院議員は「敵基地攻撃のためのミサイルなどを爆買いする、そのために増税や暮らしを切り縮める、そんな政治は認められない。物価高騰対策に一番役立つ消費税減税を実現しよう」と訴えました。
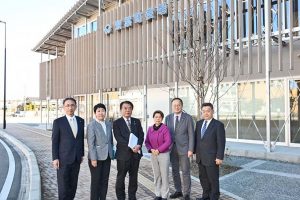 原発事故から12年近く、住民は避難先で仕事や子どもの教育を確保する一方で、いまだに帰還困難区域が85%を占め「戻りたくても戻れない」状況です。
原発事故から12年近く、住民は避難先で仕事や子どもの教育を確保する一方で、いまだに帰還困難区域が85%を占め「戻りたくても戻れない」状況です。
全域の除染とインフラ整備、産業拠点づくりが課題。2地域居住のための住宅整備や高速道路・医療費の減免の要望も。
全域除染求める/党福島チーム/双葉・大熊町で懇談
「しんぶん赤旗」12月24日・15面より
東京電力福島第1原発事故から11年9カ月が過ぎ、現地調査に入っている日本共産党国会議員団福島チームは23日、立地自治体の双葉、大熊両町を懇談に訪れました。
9月に新庁舎を町内に開設した双葉町は、事故前に約7千人いた居住者が約50人に。帰還意向調査で「戻る」が11%、「判断できない」「戻らない」が8割超です。伊沢史朗町長は「戻りたくないのでなく、戻りたくても戻れない」と告白し、戻れるよう住宅整備や企業誘致などを進めていると紹介しました。
町の85%が「帰還困難区域」のままです。国は特定復興再生拠点以外では住民の帰還意向があることを除染の実施条件としています。伊沢町長は「“除染して戻れる環境にするのが本筋”との声があり、もっともな話。被害者がちゃんと救済されることが原理原則、当たり前です」と全域除染を求めました。
大熊町では、島和広副町長らが応対。住宅や学校整備に加え、「全町避難で故郷を追われる痛みを経験したからこそ、気候変動で同じ痛みが生まれてほしくない」と温室効果ガス削減に力を入れる考えを示しました。
懇談には、笠井亮、塩川鉄也両衆院議員、岩渕友、仁比聡平両参院議員、神山悦子、吉田英策両県議が参加。笠井氏は「福島の事故がなかったかのようにする岸田政権の『原発回帰』方針を撤回させ、国と東電が事故収束・廃炉から暮らし・地域の再建まで責任を果たすよう求め、皆さんの復興の取り組みを後押しできるよう力を尽くす」と表明しました。
 党国会議員団の福島チームで東電福島第一原発の汚染水海洋放出問題の調査。
党国会議員団の福島チームで東電福島第一原発の汚染水海洋放出問題の調査。
雨水、地下水の流入により汚染水は増え続けている。東電は「最終的にはゼロにしたいが、ゼロにする確実なものがあるかといえば・・・・ない」と抜本策を持っていない。でも研究グループが提案する広域遮水壁については否定的。
 東電の広域遮水壁を検討した資料を見ても、研究グループが指摘するソイルセメント(セメントと土の混合物)の利用ではなく、粘度壁になっており、まともな検討がされたとはいえない。
東電の広域遮水壁を検討した資料を見ても、研究グループが指摘するソイルセメント(セメントと土の混合物)の利用ではなく、粘度壁になっており、まともな検討がされたとはいえない。
地下水の流入を止める抜本策を真剣に具体化すべきだ。汚染水の貯蔵タンクの建設スペースも、敷地の北側に残っている。
夕方のニュースでは、政府がGX基本方針案を取りまとめたと報道。原発を「最大限活用する」として、原発の新規建設や60年以上の運転を認めるというもの。
原発事故で何十万人もの人が、暮らしと営業、そしてふるさとを奪われたのに、その原発事故がなかったかのような原発推進策は断じて許せない!
汚染水海洋放出中止を/党国会議員団福島チーム/原発構内を視察
「しんぶん赤旗」12月23日・15面より
来春以降に東京電力福島第1原発事故の汚染水(アルプス処理水)海洋放出が狙われているなか、日本共産党国会議員団福島チームは22日、原発構内を視察しました。
 笠井亮、塩川鉄也両衆院議員と岩渕友、仁比聡平、山添拓各参院議員、神山悦子、吉田英策両福島県議が参加しました。
笠井亮、塩川鉄也両衆院議員と岩渕友、仁比聡平、山添拓各参院議員、神山悦子、吉田英策両福島県議が参加しました。
水素爆発が起きた原子炉建屋の周りには大きなガレキがいまだに残り、案内した担当者は「全て撤去しないと、核燃料を取り出せない」と説明。敷地内にはタンク約1000基、廃棄物の入ったコンテナが立ち並び、廃炉に向けた課題が山積している様子が見られました。
 汚染水の海洋放出に向けた約1キロの海底トンネルの掘削が進められ、沖合には放出口となる位置に水中構造物が設置されていました。
汚染水の海洋放出に向けた約1キロの海底トンネルの掘削が進められ、沖合には放出口となる位置に水中構造物が設置されていました。
視察後、議員団は東電に対し、多くの関係者、県民が反対している海洋放出は中止すべきだと要請。汚染水発生を止めるための「広域遮水壁」の設置などで抜本対策を早急にとり、「英知を結集してほしい」と求めました。
社会保障制度関連法案や裁量労働制などの労働法制、最低賃金引き上げの立法提案などについて懇談。
「大軍拡大増税を許さない」の一点での労働者・国民の共同を広げようと交流しました。
軍拡・生活破壊阻止/共に 国民的たたかいを/共産党国会議員団と全労連懇談
「しんぶん赤旗」12月21日・5面より
日本共産党国会議員団と全労連の黒澤幸一事務局長ら役員は20日、国会内で懇談し、安保3文書の憲法破壊・大軍拡、暮らし破壊を阻止し、最低賃金の全国一律・1500円実現や来年の春闘勝利と統一地方選での政治転換を目指して力を合わせようと意見を交換しました。
黒澤氏は、物価高騰に対して、賃上げが追い付いていないとして「来年の春闘では、10%以上、月3万円の賃上げを目指そうと議論している」と紹介。「コロナ禍で、新人の保健師が研修も受けられないまま最前線に立たされた。この極限状態が3年も続いている」と指摘。医療・公衆衛生体制の拡充で、住民も労働者も守りたいと強調しました。
全労連の各分野担当者から、「軍事費拡大のために、国立病院などの積立金を流用しようとは許しがたい」「健康保険証廃止・マイナンバー統合は反対だ」「多くの研究者が無期転換逃れの雇い止めの危機にある」「最賃を全国一律に制度改正を求めている。物価高騰で緊急に再度改定すべきだ」と要求と課題の説明がありました。
日本共産党の穀田恵二国対委員長は、「安保3文書が閣議決定され、あらゆる分野で軍事優先が噴き出ている。物価高のなかで大軍拡・大増税かと怒りがわいている。国民的なたたかいを広げたい」と強調しました。
統一地方選を目前に、「社会保障・公衆衛生拡充の政治を、国から地方まで訴えたい」と表明。賃上げについては「最賃引き上げが重要だ。政府の責任で公務員やケア労働者の賃上げも実現させたい」と述べました。
党国会議員団から塩川鉄也、宮本岳志、宮本徹の各衆院議員、伊藤岳、井上哲士、岩渕友、吉良よし子、倉林明子、仁比聡平、山添拓の各参院議員が出席しました。
環境省は、所沢市にある環境調査研修所で、原発事故によって汚染された土壌である除染土の再生利用実証事業を計画している。
過去の除染土再生利用実証事業は、福島県内の2か所で実施。南相馬市の事業場所は、住宅から1キロ近く離れた田んぼの中。飯館村の場合は、山あいの場所で帰還困難区域内。所沢市のように、近隣に民家が立ち並ぶ住宅地の近傍での実証事業は例がない。
所沢ではかつて、産廃焼却によるダイオキシン汚染が大問題となった。最近では米軍所沢通信基地に、県の残土規制条例の適用を受けない米軍横田基地の残土が搬入された。土壌汚染の調査も行われていない残土搬入に反対の声が上がった。市民の理解を得られない除染土再生利用実証事業は認められない。
環境省は、放射能濃度が低いから安全だというが、再生利用する除染土の放射能濃度の基準8000ベクレルは、原発事故の際に放射性廃棄物を少なく見せようとしてつくった基準。一方、原発の廃炉で発生する汚染物質を再利用する際の基準は100ベクレル。これ自体も高いが、8000ベクレルは、その80倍。高すぎる。
政府は今、原発再稼働・運転期間延長とともに、原発新設を計画している。その時の立地場所は廃炉原発の跡地。廃炉原発の汚染ごみを片付けないと原発が新設できない。放射性廃棄物の再利用という点で、除染土の再生利用が進めば、廃炉原発の汚染ごみの再生利用も進めやすくなる。原発事故がなかったかのように、原発の推進は許されない。
二本松市では、市民が5千の署名を集めて、実証事業を撤回させた。南相馬市でも、地元区長や市民が反対を表明し、3千人の署名を集めて、計画を中止させた。所沢でも、市民の声を集めて撤回させよう。
 所沢の環境調査研修所での除染土再利用実証事業反対集会に参加。
所沢の環境調査研修所での除染土再利用実証事業反対集会に参加。
過去の除染土再利用実証事業は福島県内の2ヵ所。所沢市のように、近隣に住宅が立ち並ぶ場所での実施例はない。市民の理解を得られない事業は認められない。
二本松市でも、南相馬市でも、住民の運動で計画を撤回させた。所沢でも!
除染土再利用の実証事業/近隣だけ説明会/市民ら抗議の声/埼玉・所沢
「しんぶん赤旗」12月21日・首都圏版より
環境省が福島県内の除染で出た土を再利用する実証事業を埼玉県所沢市で行おうとしている問題で16日夜、同市にある同省の環境調査研修所で住民説明会が開かれました。
環境省は東京電力福島第1原発事故後の除染土について、放射能濃度が1キログラムあたり8000ベクレル以下の土を公共事業などに使うとして、福島県外での実証事業を計画。所沢市の環境調査研修所を含む3ヵ所の同省関連施設があげられています。
説明会は近隣住民56人が参加し、3時間以上に及びました。同研修所の前では、「さよなら原発・in所沢連絡会有志」「福島原発裁判を支える会・所沢」「原発再稼働に反対する埼玉連絡会」「さようなら原発川越の会」の4団体が呼びかけた抗議行動が取り組まれました。
集まった市民らは、「説明会はこの周辺の住民だけが対象で、周知方法も掲示板で知らせただけ。多くの所沢市民が何も知らないなか、説明会をやったから『市民は受け入れた』なんて言わないでほしい」「所沢だけの問題じゃない。どこであろうと『汚染土』を広けるのはだめ」と抗議の声をあげました。
日本共産党の塩川鉄也衆院議員は「この事業は原発推進にもつながる。福島県内でも署名を集めて計画を徹回させた。所沢でも実証事業のストップへ、みなさんと頑張ります」と表明。城下のり子市議(県議候補)は、同日の市議会一般質問でこの問題を取り上げたことを紹介し「福島のみなさんから『所沢市民頑張れ』と背中を押されたことに、奮い立たされた」と訴えました。
基準もなし
説明会後、環境省の担当者が開いた会見によると、説明会では20人以上から、説明会の周知が不十分なことや、もっと広く公開すべきとの意見、なぜ所沢で事業を行うのか、事業の安全性などについて質問があったといいます。
同省の担当者が、参加者からの「どういう状態になったら住民の同意を得られたとなるのか」との質問に対し、「明確な基準は持っておらず、同意をとって進める事業ではない」と答えたと話す場面も。この発言に対し、記者から質問が相次ぎ、担当者は「同意を得るつもりがないのではなく、(同意を得るための)決まった手続きがないということ。みなさんが反対しているのに、環境省がごり押し的に進めることは考えていない」と釈明しました。
「賛成」0人
担当者によると、事業に対し明確に「賛成」と話した参加者はおらず、明確に「反対」と話した参加者は何人かいたといいます。
説明会に参加した50代の男性は「実際に多くの『汚染土』があり、いまだに福島に戻れない人がいるのは大変なことだと思うが、そもそも原発を推進してきた国に責任があるのでは」と話します。
50代の女性は「参加者の中に『この事業に賛成の人は手を挙げて』と言った人がいましたが、手を挙げた人は誰もいなかった。質間したほとんどの人が事業に不安や疑問を感じていたと思うし、事業が安全かのように語る環境省は無責任です。この問題を広く市民に知らせて意見を聞き、尊重してほしい」と語りました。
臨時国会では、衆議院で3種類の請願採択。
「てんかんのある人とその家族の生活を支える医療、福祉、労働に関する請願」
「全ての世代が安心して暮らせる持続可能な社会保障制度の確立に関する請願」
「パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願」
更なる請願採択に向け、真摯な議論を求めていきたい。
安倍元総理の「国葬」を検証する各会派代表者による協議会の報告が報告されました。
「国葬」実施で「世論の分断が招かれた」との共通認識を示したうえで、「国葬」の法的根拠や対象者。国会の関与などについての様々な議論を併記しました。
報告は、各会派から「(国葬儀実施は)ぎゅお政府の独断であり適切ではない」「憲法の保障する国民主権、法の下の平等、思想及び良心の自由や政教分離原則との関係で違憲である」「政治家の国葬実施は認められない」などの意見が示されたことを明記。
また、有識者ヒアリングで「国葬」の対象について「一定の基準を設けることは非常に困難」などの意見を例示し、ルール作りに「消極的な意見が多く示された」と記述しました。
私は、協議会の場で、「安倍『国葬』の違憲性を検証する場とすべきだ」と主張しました。