 日本共産党国会議員団福島チームは、東電原発事故のトリチウム汚染水の処理問題について、政府と東電からヒアリング。
日本共産党国会議員団福島チームは、東電原発事故のトリチウム汚染水の処理問題について、政府と東電からヒアリング。
浄化設備で処理した汚染水は、トリチウムしか残らないとされていたのに、実際にはヨウ素やストロンチウムなど除去されておらず、それどころか全体の8割が基準値を超える汚染のままだったことが明らかになりました。公聴会での説明が間違っていたことになります。
公聴会をやり直すのは当然のこと。汚染水の再処理、汚染水の長期保管といった海洋投棄以外の方策を検討すべきです。
東電は「我々の説明が足りなかったと反省している。汚染水の再処理を行う」と説明。経産省は「長期保管も選択肢としている」「近畿大のトリチウム分離技術についても検討していく」と答えましたが、公聴会については「やり直すことは考えていない」。これでは国民の理解は得られません。
「しんぶん赤旗」10月4日付・15面より
情報隠し東電に抗議/共産党議員団/汚染水で聞き取り
日本共産党国会議員団福島チームは3日、東京電力福島第1原発の多核種除去設備(アルプス)で処理した汚染水の処分方法をめぐる公聴会の結果や、約8割にあたる約75万トンの処理水にトリチウム(3重水素)以外の放射性物質が国の放出基準(告示濃度限度)を超えて残っている問題で、経済産業省、東電、原子力規制委員会から説明を受けました。議員団は冒頭、汚染水の情報を隠蔽(いんぺい)してきた東電と国に抗議しました。
東電は、アルプス処理水に含まれる放射性物質濃度のデータを説明していませんでした。東電の木元崇宏原子力・立地本部長代理は「説明が足りなかったことを反省している」と述べ、基準超えの理由を「稼働率を上げて汚染水処理量を増やすことを優先したため」と釈明しました。
資源エネルギー庁の比良井慎司・原子力発電所事故収束対応室長は、基準超え汚染水の存在を以前から知っていたと認め、「今回まとめた資料で8割を超えていると公開した」と述べました。8月末の公聴会で、海洋放出への反対意見が相次ぎ、タンクでの長期保管も提案されたことについては、今後、国の小委員会で検討すると表明しました。
議員団は、汚染水問題は国民的な課題だと強調。また、公聴会はアルプス処理水に含まれる放射性物質はトリチウムだけであることを前提としていたと指摘し、公聴会のやり直しを求めました。
塩川鉄也、高橋千鶴子、藤野保史(以上衆院)、井上哲士、岩渕友、武田良介、山添拓(以上参院)の各議員が参加しました。
 ホンダ狭山工場の移転・閉鎖計画発表からちょうど1年、工場門前で宣伝行動。梅村さえこ参院比例予定候補、党狭山市議団らと参加。
ホンダ狭山工場の移転・閉鎖計画発表からちょうど1年、工場門前で宣伝行動。梅村さえこ参院比例予定候補、党狭山市議団らと参加。








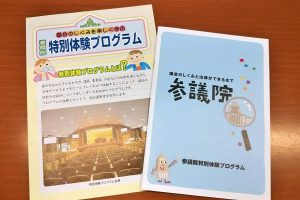



 10月21日告示、28日投票で市議選が行われる草加市で演説会。現職の佐藤のりかず・斉藤ゆうじ・藤家あきらさんと新人の石田けい子・大里よう子さんの5人で現有議席の確保をめざします。平野あつ子県議予定候補、伊藤岳参院埼玉選挙区予定候補らと一緒に訴えました。
10月21日告示、28日投票で市議選が行われる草加市で演説会。現職の佐藤のりかず・斉藤ゆうじ・藤家あきらさんと新人の石田けい子・大里よう子さんの5人で現有議席の確保をめざします。平野あつ子県議予定候補、伊藤岳参院埼玉選挙区予定候補らと一緒に訴えました。 党埼玉県委員会・県議団が主催する予算要望懇談会に出席、各団体から切実で道理のある要望、提案をいただきました。
党埼玉県委員会・県議団が主催する予算要望懇談会に出席、各団体から切実で道理のある要望、提案をいただきました。 日本共産党国会議員団福島チームの現地調査2日目。いわき市内の双葉町いわき事務所を訪問。「双葉町における被災の現状と復興への課題」についてお聞きしました。
日本共産党国会議員団福島チームの現地調査2日目。いわき市内の双葉町いわき事務所を訪問。「双葉町における被災の現状と復興への課題」についてお聞きしました。
