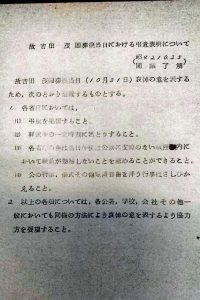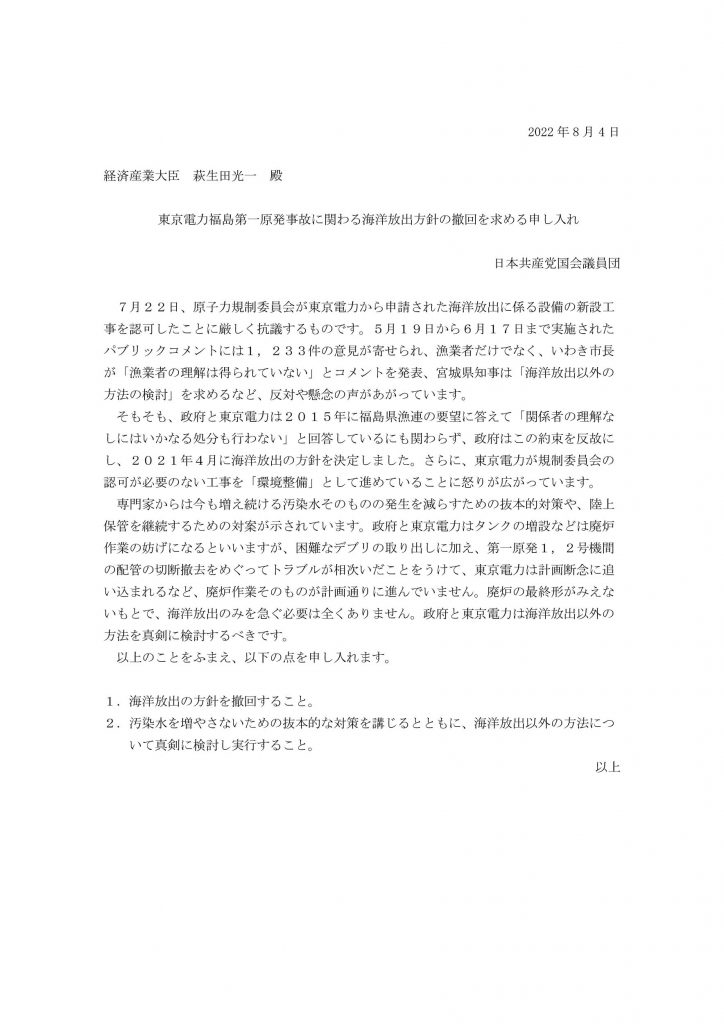7月に豪雨災害のあった埼玉県ときがわ町で、渡邉一美町長と懇談。地すべりなどによる全壊家屋が生じ、緊急地すべり対策に続き恒久対策実施に向けて県と協議中。被災者には県・市町村被災者安心支援制度適用に向けて準備中とのこと。避難指示など気象台との連携も重要。避難者の居住確保策が必要です。
7月に豪雨災害のあった埼玉県ときがわ町で、渡邉一美町長と懇談。地すべりなどによる全壊家屋が生じ、緊急地すべり対策に続き恒久対策実施に向けて県と協議中。被災者には県・市町村被災者安心支援制度適用に向けて準備中とのこと。避難指示など気象台との連携も重要。避難者の居住確保策が必要です。
 地すべりなどによる全壊家屋が生じ、緊急地すべり対策に続き恒久対策実施に向けて県と協議中。被災者には県・市町村被災者安心支援制度適用に向けて準備中とのこと。
地すべりなどによる全壊家屋が生じ、緊急地すべり対策に続き恒久対策実施に向けて県と協議中。被災者には県・市町村被災者安心支援制度適用に向けて準備中とのこと。
避難指示など気象台との連携も重要。避難者の居住確保策が必要です。
大雨災害/生活第一に/埼玉・ときがわ町/塩川氏ら町長と懇談
日本共産党の塩川鉄也衆院議員と守屋裕子埼玉県議は16日、7月12日夜の大雨で土砂災害などがあった埼玉県ときがわ町の渡邉一美町長、小峯光好副町長らと懇談し、国や県への要望を聞きました。野原和夫町議が同席しました。
渡邉町長は、塩川氏らが同町の被災現場の調査に駆け付けたことに感謝を表明。小峯副町長は、町として浸水家屋の消毒を無料で行い、被災者への避難所や住まいの支援、国の予算による被災住宅などの応急対策を進めてきたことを紹介しました。
渡邉町長は、国の被災者生活再建支援制度は全壊家屋10世帯以上などの要件があるとして「2軒でも3軒でも災害があれば、支援があるといい」と要望しました。
塩川氏らは、同制度の対象とならない地域に同様の支援を行う県の被災者生活安心支援制度の利用も呼びかけ、「何よりも、被災されたみなさんの生活が安定するための取り組みが必要。要望をしっかり受け止め、国や県に要請していきたい」と述べました。