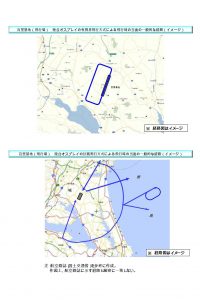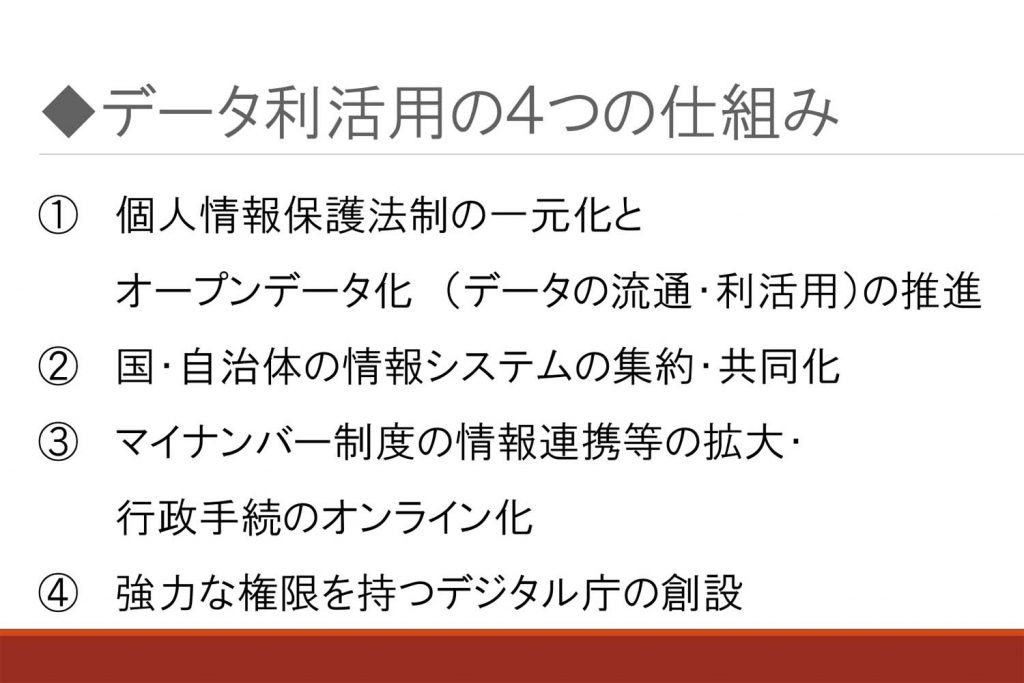緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象地域追加にあたって政府から報告を受け、質疑を行いました。
緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象地域追加にあたって政府から報告を受け、質疑を行いました。
私は、検査不足で感染者を把握しきれていない問題について質問。東京都の検査能力は1日7万件あるのに、この間の検査件数は1万5千件程度と頭打ちになっていると指摘し、PCR検査を拡充し、陽性者の早期把握が必要だ、と主張しました。
西村康稔担当大臣は「保健所に負荷がかかっている中で濃厚接触者の調査が追い付いていない」と認め、「感染拡大防止に検査の拡充は極めて重要だ」と答えました。
また、子どもの感染が拡大しているとして、学校・幼稚園・保育園・学童保育などでのPCR検査実施をと追及。
西村大臣は、感染が疑われる小中学校、幼稚園の児童・生徒用の抗原簡易キット配布や先生向けのモニタリング検査ついては述べたものの、児童・生徒向けのPCR検査拡充には触れませんでした。
私は、五輪開催時より感染状況は深刻だとしてパラリンピックと学校連携観戦の中止を要求しました。
また、全国的な感染拡大の中で全国の事業者にまとまった支援を行うために、持続化給付金、家賃支援給付金の再支給が必要だと強調。政府が今行っている支援は、地域限定、期間限定、金額も少額で、支援が間に合っていないと迫りました。
西村大臣は「緊急事態宣言の地域が拡大してきている中で、その影響には目配りしていかなければならない」としつつ、再支給には応じませんでした。
衆議院TV・ビデオライブラリから見る
「議事録」
<第204通常国会 2021年8月25日 議院運営委員会 第53号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
東京都の陽性率は、八月に入って二〇%を超える事態がずっと続いております。東京都のモニタリング会議では、検査が必要な人に迅速に対応できないおそれがあり、把握されていない多数の感染者が存在する可能性があると指摘をしております。
感染者が把握できていないのではないでしょうか。
○西村国務大臣 検査につきましては、あるいは感染者、陽性者の数につきましては、専門家も様々御指摘をされておりますが、まさに御指摘のように、保健所に負荷がかかっている中で、濃厚接触者の調査が追いついていないという面はございます。それから、検査を積極的に受けようとしない方がいることも事実でありまして、そうしたことから、実際の感染者の数は新規陽性者の報告数よりも多いのではないかという御指摘を専門家からいただいているところであります。
そうした中で、保健所の負荷軽減、これも重要でありますので、厚労省でつくっている枠組み、学校の先生や資格のある方などをプールして派遣をする枠組み、IHEATという枠組みでありますけれども、これによって、これまで延べ約三百九十名を派遣してきております。東京都の保健所でも、それぞれ、大学の先生などに協力をいただいて取り組んでいると聞いております。
いずれにしても、できるだけ正確にこうした感染者、陽性者の数を把握していくことは重要であります。無症状の方が一定程度おられますので、全てを把握することはなかなか難しいということでありますけれども、必要な検査が行われるように、体制整備、厚労省中心でありますが、しっかりとサポートして取り組んでいきたいと考えております。
○塩川委員 保健所の体制強化などが必要であります。
東京都の検査能力は一日七万件といいますが、この間の検査数は約一万五千件程度で、頭打ちであります。
PCR検査を拡充し、陽性者の早期発見が必要ではないでしょうか。
○西村国務大臣 御指摘のように、東京都の能力は七万件程度あると聞いておりますが、実際には一万五千件程度、最近では多いときは二万件程度実施をしておりますが、それに加えて、一日一万件程度の高齢者施設における集中検査をずっと実施しておりますので、これが実際にはプラスになりますので、プラス一万件程度は実施しているということであります。
ただ、いずれにしても、感染者を早期に発見して感染拡大を防いでいくという観点からは、検査の徹底、拡充は極めて重要であります。私からも、小池知事に対しましても、折に触れて、検査件数を増やすこともお願いしてきているところでありますが、厚労省とも連携しながら、検査の充実に引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。
○塩川委員 学校の部活動や学習塾、学童保育、保育園などでクラスターが発生するなど、子供の感染が拡大をしております。
学校や幼稚園、保育園、学童保育などでPCR検査の実施を進めるときではないでしょうか。
○西村国務大臣 御指摘のように、子供たちの感染拡大を防いでいくためにも、学校などにおける検査は重要だと考えております。
これまで、大学、高校、専門学校で抗原検査キットは約四十五万回分を配付しておりますし、今般、小中学校、幼稚園に最大八十万回分の抗原簡易キットを配付する予定としております。ちょっと何か体調の悪い、喉に違和感があるとか、人にうつす量は検知できますので、そういった、ちょっと具合の悪いお子さんがいるときには活用いただければ、生徒さんがいれば活用いただければと考えております。
あわせて、私ども、無症状の先生方に対してモニタリング検査をこれまで大学、高校あるいは専門学校などで行ってきておりますけれども、幼稚園でも行っておりますが、これを小中学校の先生方にも進めていこうということで、各自治体と連携をして、特に緊急事態地域の感染拡大の見られるエリアから、定期的に無料でPCR検査を受けられるような、モニタリング検査を活用した枠組み、今検討を進めているところであります。
○塩川委員 パラリンピックの学校連携観戦について、尾身会長は、五輪開催時と比べ、今の感染状況はかなり悪いと慎重な姿勢でありました。
西村大臣も同様の認識でしょうか。
○西村国務大臣 学校連携観戦プログラムにつきましては、各自治体や学校設置者において適切に判断されていくものというふうに承知をしておりますけれども、橋本会長は、感染状況が更に拡大しているような状況に置かれた場合には、速やかに四者協議を開催して、学校連携というものが取りやめになることは十分考えられると思っておりますとも発言されておられます。
いずれにしましても、今の感染状況がどうなっていくのか、あるいは感染リスク、こういったものを見極めた上で判断していただければというふうに考えております。
○塩川委員 五輪開催時は、緊急事態宣言下の東京、神奈川、千葉、埼玉で学校連携観戦の中止をしました。
更に感染状況が悪化をしており、学校連携観戦の中止が必要ではないでしょうか。
○西村国務大臣 今申し上げたとおりでありますけれども、子供の安全、子供の感染拡大を防ぐということが何より重要でありますので、それぞれの自治体と学校設置者において適切に判断されていくものと思いますけれども、感染状況や感染リスク、こうしたものを踏まえていただいて判断いただければというふうに考えております。
○塩川委員 行動抑制と矛盾したメッセージとなるパラリンピックについては、今からでも中止の決断、このことを求めるときではないでしょうか。
○西村国務大臣 パラリンピックに関する最終的な判断権限はIPCにあると理解をしております。全ての競技で無観客とするというふうに四者協議でも決まったというふうに聞いております。
いずれにしましても、国民の皆様におかれましては、パラリンピックにおきましても、テレビで、自宅で観戦をしていただいて、そして、家族あるいはふだんいつも一緒にいる仲間と少人数で観戦をしていただいて、感動を分かち合っていただく。そして、その感動を外で何かみんなで祝い合おうとか分かち合おうといったことにつながらないように、是非、テレビで、自宅で、家族あるいはいつもの少人数の仲間でということで応援をお願いできればというふうに考えております。
○塩川委員 医療提供体制について、臨時の医療施設の設置、宿泊療養施設の増設はどのように進んでいるのか。
○西村国務大臣 臨時の医療施設につきましては、それぞれの感染状況に応じて、私からもそれぞれの知事に、こうした臨時の医療施設、医療法や建築基準法の特例で早くできますので、これを活用するようにということで強く求めているところであります。
既に十三の都道府県で十九施設が開設されております。今後も支援をしながら取り組んでいきたいと考えておりますし、宿泊療養施設も、例えば大阪で六千床まで増やすという計画を表明しておられたり、それぞれの地域で確保すべく取り組まれておりますけれども、何より看護師さんを始めとする人材確保が必要となってまいりますので、こうした面で、看護師さんを派遣する、送り出す元の医療機関への支援の拡充であったり、様々な取組を進めております。
いずれにしても、必要な方が必要な医療を受けられる体制をしっかりとつくっていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 原則自宅療養の方針の撤回を求めるものです。
全国に感染が広がっている中で、全国の事業者にまとまった支援を行うために、持続化給付金、家賃支援給付金の再支給を是非とも求めたい。
○西村国務大臣 緊急事態宣言の地域あるいは期間が拡大し延長してきている中で、その影響についてはしっかりと目配りをしていかなきゃいけないと考えております。
月最大二十万円の月次支援金も九月まで実施ということにしておりますので、一月からもうずっと続いておりますから、一時支援金と、一月―三月と合わせると最大で百八十万円の支援となります。さらに、今回、地方創生臨時交付金三千億円を配分いたしましたので、それぞれの地域でそれに上乗せする措置、支援策などを講じられるものと思います。雇用調整助成金も十一月末まで延長するということにしております。
こうした取組を進めていく中で、緊急事態宣言などの影響にしっかりと目配りしながら、必要な対策を機動的に講じていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 昨年実施をした持続化給付金は、これで半年間耐えてくれと実施をしたものであります。その後の支援は、地域限定、期間限定、金額も少額で、しかも、不備ループに陥って支援が間に合わない。
そういう点でも、迅速に支給が可能な持続化給付金、家賃支援給付金の再支給こそ行うべきではありませんか。
○西村国務大臣 月次の支援金も、地域、業種を限定せずに、緊急事態や蔓延防止等重点措置の影響を受けた事業者、五〇%以上売上げが減少された方に最大二十万円までの支援、個人でありますと十万円までの支援ということでありますし、それに上乗せする形で、多くの県で地方創生臨時交付金を活用して、三〇%減の事業者にも、あるいは今の二十万円、十万円に更に上乗せして支援も行われてきております。
そうした支援策、そして影響も見ながら、必要な対策は講じていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 菅総理にコロナ対策をしっかりとただし、必要な対策を打つ、そういう場として臨時国会を直ちに召集することを強く求めて、質問を終わります。