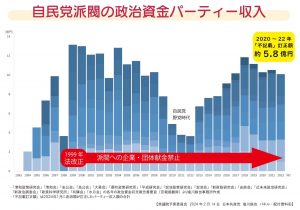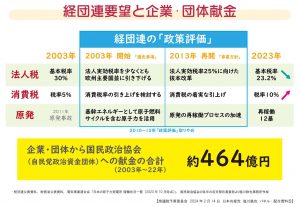政治資金パーティー裏金事件をめぐる自民党の聞き取り調査報告は「極めて不十分だ」として全容解明を迫りました。
政治資金パーティー裏金事件をめぐる自民党の聞き取り調査報告は「極めて不十分だ」として全容解明を迫りました。
私は、岸田派のパーティー券の販売ノルマはいくらかと追及。
林芳正官房長官(岸田派元座長)は「私の場合はパーティー券100枚(200万円)だった」と答え、若手議員のノルマについても「閣僚経験等でいろんな目標があったが、私より低かった」と明らかにしました。
岸田派では2018~20年の3年間で計3059万円の収入不記載により、元会計責任者が略式起訴されています。この間、岸田文雄首相は私の質問に、不記載額の内訳として、18年1322万円、19年841万円、20年896万円だと答えています。
岸田派が1月に訂正した20年の収支報告書では、前年繰越額を1605万円増額させていますが、18、19両年の不記載額計2163万円とは500万円以上の差があります。
私が不記載のパーティー収入の内訳をただすと、林官房長官は、18年764万円、19年841万円、20年896万円だと答弁。18年の差額については「寄付の取り消しが558万円あった」と初めて明らかにしました。
私は続けて、安倍派についてもノルマや裏金づくりの実態を問いましたが、答弁に立った安倍派所属の政務官3人は「内部事務に関わることだ」と繰り返し、口裏を合わせたように全く答えず、1人は自民党調査について「特段感想はない」などと述べました。私は「全容解明の姿勢に立っていない。国民の不信は拡大するだけだ」と批判しました。
「議事録」
213回通常国会 令和6年2月16日(金曜日) 内閣委員会 第2号
○塩川委員 続けて、自民党の派閥裏金問題について、林官房長官にお尋ねをいたします。
林長官にお尋ねしますが、自民党が国会に聞き取り調査に関する報告書を出しました。この聞き取り調査に関する報告書について、これで全容解明はされたと言えるんでしょうか。お答えください。
○林国務大臣 昨日ですが、自民党における外部の弁護士を交えた関係者への聞き取りによりまして、その結果が弁護士のチームにより報告書として取りまとめられたものと承知をしております。
党の調査につきまして官房長官の立場でコメントすることは差し控えますが、岸田総理は、自民党総裁として、説明責任が今回の聞き取り調査や政治資金収支報告書の修正をもって果たされるというものではないこと、さらに、今後とも、あらゆる機会を捉えて、国民の信頼回復に向けて関係者には説明責任を果たしてもらわなければならないし、党としても求めていくこと、こう述べられておるものと承知をしております。
こうした方針に沿って引き続き対応していくものと考えております。
○塩川委員 林長官御自身も自民党の一員でもあります。そういう意味ではまさに関係者で、岸田派は解散をしたという話がありますけれども、そこで座長というお立場で、取りまとめにも関わっておられたわけであります。
そういった立場から見て、岸田派においても三千万の不記載も出ていたわけですよね。こういったことについて、派閥の一員でもあった、その幹部でもあった林長官としてこの報告書をどう受け止めているのかというのは、一人一人が説明責任を果たすという点では、当然のことながら林長官としても説明すべきではありませんか。改めてお答えください。
〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
○林国務大臣 官房長官の立場で報告書の内容についてコメントすることは差し控えたいと思いますが、国民の政治に対する不信の声、これを真摯に受け止めて、引き続き、関係者において適切に説明責任を果たす、このことが重要だと考えております。
○塩川委員 自民党議員として、岸田派の派閥の構成員だった林議員として、岸田派のこの三千万の不記載の問題についてはどのようにお考えですか。
○林国務大臣 私の所属しておりました宏池会についてのお尋ねですが、パーティー関連の収入につきまして、どの議員の紹介によるパーティー券収入か不明な場合には判明するまで収支報告書への記載を保留する、こうした事務手続を取っていたほか、銀行への入金履歴を手書きで転記する際に転記ミスを起こして収支報告書への記載が漏れることもあった、こういうこと等から不記載が生じたというふうに報告を受けております。
会計責任者の不確かな会計知識等に基づくものではありますけれども、結果として政治資金収支報告書に多額の不記載が生じるという事態を招いたことについて、宏池会座長の立場にあった者として遺憾であるというふうに受け止めております。
○塩川委員 この間、岸田総理と、自民党総裁の立場、もちろん宏池会の領袖としてのお立場だったというのも含めてやり取りをしてきましたけれども、宏池会の座長としてお答えいただきましたので、重ねて岸田派、宏池会についてお尋ねしますけれども。
例えば、こういった派閥のパーティーについて、いわゆるノルマを設けていたというのは今回の報告書でも書かれているところですけれども、宏池会においては、このパーティー販売のノルマというのはそもそも幾らだったのか。例えば、林官房長官御自身は、ノルマは幾らだったんでしょうか。
○林国務大臣 宏池会におきましては、達成できなかった場合にペナルティーが科されるといったような意味でのノルマといったものは、そうした厳格なものは設けておらず、議員ごとに緩やかな努力目標があったと承知をしております。
座長はどうだったんだ、こういうお尋ねでございますが、私の場合は、座長という立場であり、最大限対応するというふうにされておりましたが、一応の目安としてパーティー券百枚というものがあったと認識をしております。
○塩川委員 百枚というのは、金額ということでは二百万円ということでよろしいんでしょうかね。
○林国務大臣 一枚二万円でございますので、二百万円でございます。
○塩川委員 例えば一期生、二期生のような若手の方などは、これは幾らぐらいなんでしょうか。
○林国務大臣 今手元に詳細なものを持ち合わせておりませんが、閣僚経験があるかないか等によって、いろいろな、緩やかな努力目標があったのではないかというふうに思っておりますが、したがって、私よりも目標は低かったんだろうというふうに思います。
○塩川委員 岸田総理の答弁の中で、岸田派について、パーティー収入については基本的に全て銀行口座に入金しているという話がありました。
宏池会のパーティー収入については、毎年毎年派閥のパーティーごとに専用口座を作っているということなんでしょうかね。
○林国務大臣 宏池会による政治資金パーティーにおきましては、パーティー関連収支、これを明確に区分する観点から専用口座を設けていたところでございます。
また、年ごとではなくて、パーティー専用の口座を恒常的に設けていたところでございます。
○塩川委員 そうしますと、宏池会のパーティーの収支を扱う口座、専用口座があって、毎年毎年、そこにお金も入り、そこから出ていく。ただ、この口座であれば派閥のパーティーの出入りのお金だというのがはっきりしている、そういうことでよろしいですかね。
○林国務大臣 委員の御指摘のとおりだと思います。
○塩川委員 その場合に、どの議員の紹介によるパーティー券か不明な分について、これを別にしていたというふうな答弁があるんですけれども、誰の紹介か分からない不明分については別にしていた、その不明な金額の内訳を教えていただけますか。
○林国務大臣 不記載金額の内訳ですが、二〇一八年の政治資金収支報告書に係るものが七百六十四万円、二〇一九年の政治資金収支報告書に係るものが八百四十一万円、二〇二〇年の政治資金収支報告書に係るものが八百九十六万円であったと認識をしております。
○塩川委員 元々派閥パーティー収入について不記載だったものが三千五十九万円で、二〇二〇年八百九十六万円、二〇一九年が八百四十一万円。三千五十九万円の内訳として、二〇一八年に千三百二十二万円だったんですけれども、今のお答えの七百六十四万円との差は何なんでしょうか。
○林国務大臣 寄附の取消し要請というものがございまして、五百五十八万円でございます。したがって、略式起訴に係る千三百二十二万円から五百五十八万円を引きまして七百六十四万円、こういうことでございます。
○塩川委員 それぞれの金額について、内訳ということなんですけれども、不明分についてどういうふうな、要するに、入金した団体があるわけですよね。それごとの区分が当然あるわけですけれども、そこを教えてもらえますか。
○林国務大臣 お尋ねの趣旨が必ずしも理解できているかどうかちょっとあれでございますが、先ほど申し上げたような、どの議員の紹介によるパーティー券か不明な分が、それぞれ、先ほど申し上げたような年ごとにあったということだと思います。
○塩川委員 では、その前の段階の話として、どの議員が集めたお金か分からないといった部分があるということなんですが、どの議員か特定というのは、例えば議員ごとのナンバーとかがあって、それが入金の際に記録をされるという形ではっきりしているということでよろしいですか。
○林国務大臣 先ほどちょっと申し上げましたように、達成できなかった場合のペナルティーが科されるようなノルマというものがございませんで、議員ごとに緩やかな努力目標がありました。
その上で申し上げますと、パーティー券がどの議員との関係での売上げであるかは、振り込み時にパーティー券の番号を記載いただいたり、当該議員事務所がまとめて振り込みをしてくることなどにより、事務局において確認していたと承知をしております。
ちょっとその内訳については手元に数字はございません。
○塩川委員 是非改めて内訳を教えていただきたいと思います。
それで、派閥の中では、各議員の、緩やかな努力目標と言っている、いわゆるノルマの基準を達成したかどうかの確認というのは、具体的には誰がどのように行っていたわけなんですか。
○林国務大臣 先ほど、ちょっと最後の方に申し上げましたけれども、振り込み時にパーティー券の番号を記載いただいたり、当該議員の事務所がまとめて振り込みをしてくることなどにより、事務局において確認をしていたということでございます。
○塩川委員 この点について改めて精査してお聞きもしたいと思うんですが、そもそも、この収支報告書の不記載となっていた三千五十九万円の内訳について、二〇一八年が千三百二十二万円、二〇一九年が八百四十一万円、二〇二〇年が八百九十六万円と岸田総理は答弁されました。
この二〇二〇年の収支報告書の訂正では、本年の収入額に八百九十六万円が追加をされています。前年からの繰越額については一千六百五万円増加をしています。一八年、一九年の不記載分の合計は二千百六十三万円なんですが、二〇二〇年の前年からの繰越額というのは一千六百五万円で、五百万円以上違うのは、これはどういう理由なんでしょうか。
○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、二〇一八年分、これは五百五十八万円が寄附の取消しということでございまして、略式起訴に係る千三百二十二万円からこれを引いた額が七百六十四万円、これが先ほど申し上げましたような、どの議員の紹介によるパーティー券か不明な部分について別にしていた、こういう部分でありますので、そこを差引きすると先ほどのような数字になってくるということであろうというふうに思います。
○塩川委員 先ほどの取消し要請は五百八十四万で、今の私が言った差額が五百五十八万で、若干違うんですが。
○林国務大臣 さっき間違えて言ったかもしれませんけれども、五百五十八万円です。
○塩川委員 改めて事実関係を確認したいと思います。
最後に、岸田派のパーティーのことですけれども、二〇二〇年の収支報告書の訂正では、派閥のパーティー収入額が八百九十六万円増加しているのに購入者数は二千二百十八人のままで変わらない点について質問しましたら、総理は精査を続けていると答弁されましたが、これはどうなったか、教えていただけますか。
○林国務大臣 お尋ねの人数につきましては、精査を続けているところと聞いております。
○塩川委員 精査を続けるという質問でもう一か月ぐらいになっているんですけれども、こういう点でも、本当に全体像が明らかになっているのか、そうはとても言えないということがあると思います。
そういう点でも岸田派としての説明責任を尽くされていないということを申し上げなければなりませんし、昨日自民党が出した報告書そのものも極めて不十分なものであって、実際には、中身を見ても、誰がいつか始めたのかも全く明らかになりませんし、使途についても、いろいろ項目は挙げられていますけれども、何で安倍派の参議院議員改選組がその年だけ金額が多いのか、選挙に使ったんじゃないのか、こういうことについて何らのコメントもないわけで、こういった問題についての徹底解明が求められる、このことを改めて申し上げておくものであります。
それでは、安倍派の派閥裏金問題について、清和研に所属をされておられました塩崎政務官、石井政務官、松本政務官にお尋ねをいたします。その順番でそれぞれお答えいただければと思うんですけれども。
昨日、聞き取り調査に関する報告書が出されました。御覧いただいていると思います。今回、この聞き取りに当たって、聞き取りの対象になっていたかどうかという事実関係の確認と、あわせて、報告書の内容をどのように受け止めたのか、所感をお答えいただけますか。
○塩崎大臣政務官 塩川委員の御質問にお答えいたします。
私自身は聞き取りの対象とはなっておりません。
報告書については、まだ全体を熟読するには至っておりませんけれども、今回の事案についてのヒアリング結果を基に、弁護士の先生方が客観的な観点から評価をされたものと認識しております。
以上でございます。
○石井大臣政務官 お答えいたします。
先ほどの答弁にも同じでございまして、私も聞き取り調査の対象とはなっていないところでありますので、よって、聞き取り調査は受けていないということの答えにもなります。
よろしくお願いします。(塩川委員「報告書の感想、受け止め」と呼ぶ)報告書の受け止め。
○星野委員長 一応、委員長を通してください。
○石井大臣政務官 はい。
報告書の私自身の受け止めについては、あらましは拝見させて、読んでおりますけれども、特段、そういうことかなという点だけで、特に感想はございません。
○松本大臣政務官 お答えいたします。
私は、聞き取りは受けておりません。
報告書の感想につきましては、昨日、私もざっと目を通させていただきましたけれども、やはり、同じ清和研の人間としては非常に残念なことだなというふうには思っております。幾つかの批判等々も出ていたようでございますけれども、若手の人間としてはもっともなことだろうというふうに思いました。
以上です。
○塩川委員 次にお尋ねしたいのが、この清和研、安倍派のパーティーについてのノルマのことなんですけれども、お三方は二〇二一年の当選ですので、二〇二一年の十二月にもパーティーがあるんですけれども、二〇二一年の十二月、二〇二二年の五月、二〇二三年の五月と派閥のパーティーが三回あるんですが、その際に、それぞれノルマを持って取り組まれたのか、その額が幾らか、この点を教えてもらえますか。
○塩崎大臣政務官 塩川委員の御質問にお答えいたします。
二〇二一年の当選以降ですので、派閥のパーティーとしては、私の理解としては二回というふうに理解しております。
それぞれにおいて販売目標というか努力目標みたいなものはお示しがあったように記憶しておりますけれども、そのつぶさな中身については、これは政策集団の内部事務に関することでございますので、差し控えさせていただきたいと思います。
○塩川委員 ノルマの額、是非お答えいただきたいんです。だって、林さんもお答えになっているんですから。しっかりとお答えいただけますか。
○塩崎大臣政務官 販売目標の具体的な金額については、これは政策集団の内部事務に関することでございますので、答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、私の政治資金につきましては、全て法にのっとって適正に処理をしているものでございます。
○塩川委員 何で言えないんですか。だって、皆さんは目標を持ってやっているんでしょう。適正にということをおっしゃっておられるのであれば、基本、透明性を確保することこそ政治の信頼、土台ですから、そういった点では、まず、入口である販売目標、ノルマの金額、言っていただけませんか。
○塩崎大臣政務官 塩川委員の御質問にお答えいたします。
政治資金規正法上の透明性という観点から、派閥のパーティーの売上げにつきましては、これは公開を法にのっとってさせていただいているものでございます。
また、私の政治資金につきましても、これは法にのっとって適正に処理をさせていただいているものでございますので、お答えとしては、派閥の具体的な販売努力目標ということについては差し控えさせていただきたいと思います。
○塩川委員 済みません、では、石井政務官、松本政務官は、その点、ノルマはどうだったのか、教えてもらえますか。
○石井大臣政務官 お答えいたします。
いわゆる派閥、政策集団から努力目標のものはもちろん提示されたということはありますけれども、同じく、やはり政策集団の内部事務に関わることでございます。回答を差し控えさせていただきたいと思います。
○松本大臣政務官 お尋ねにつきましては、私も同じ、努力目標というのは提示されたことがございました。その中身については、今の答えと同じになりますけれども、少なくとも、林官房長官の数よりは多くなることはないということだけは言えると思います。
ありがとうございます。
○塩川委員 いや、全く納得いきませんね。初歩の初歩の話じゃないでしょうか。内部事務に関わること、回答を控えたい。だって、派閥はないんでしょう。要するに、清和研を解散と言っているわけじゃないですか。何でそんなに縛られるんですか。おかしいじゃないですか。内部事務という、清和研そのものがなくなるというときに、何でそこにこだわる必要があるんですか。ちゃんと答えてください。
では、塩崎さん、どうですか。
○塩崎大臣政務官 塩川委員の御質問にお答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、販売目標というものはございましたが、私の政治資金につきましては、法にのっとって全て明らかにしているところでございます。
そのほかは先ほど申し上げたとおりでございます。
○塩川委員 内部事務に関わることなのでお答えは差し控えたいということについて、いや、内部事務といっても、清和研そのものがなくなるわけですから、何でそこにこだわるんですか。
三人そろって同じようなことを言うということは、これは口裏合わせをしているということになるんじゃないですか。組織的にこういったことについて公表しない、後ろ向きの姿勢だ、そういうことを自ら語るということになるんじゃないですか。そのことが政治不信を拡大することになるということをしっかりと受け止めるべきじゃありませんか。
そういうことを、じゃ、もう一回、塩崎さん、どうですか。
○塩崎大臣政務官 塩川委員の御質問にお答えいたします。
私のお答えの仕方が何か十分誠実に伝わっていなかったんだとしたら大変申し訳なく思いますが、我々三人、同じ一回生でございまして、同じグループに属していたものでございますから、同じ質問について同じ答えになるのはやむを得ないところかということで御理解をいただければというふうに思います。
○塩川委員 内部事務だからお答えは差し控えたいという、そういう指導、指示が派閥からあったということなんですか。
○塩崎大臣政務官 塩川委員の御質問にお答えいたします。
今、誰かから指示があったのかという御質問がございましたが、特段そういう指示はいただいておりません。
以上です。
○塩川委員 こういうことだってまともに答えられないような話で、国民の信頼を回復することはできないということは強く受け止めるべきであります。納得するものではありません。
関連することがありますので、ほかの点でお尋ねしますけれども、こういった販売目標、ノルマを超えた部分については派閥から還付されるという、いわゆるキックバックの仕組みがあるということについては、お三方は承知しておられたのか、その点。
○塩崎大臣政務官 塩川委員の御質問にお答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、私は、政治資金につきましては全て法にのっとって適正に報告をしておりますので、いわゆる還付金のありやなしや、そういったことについての特段の認識はございません。
○石井大臣政務官 お答えいたします。
私自身は、先ほどの還付金の話でございますけれども、特段認識しているものではありません。
○松本大臣政務官 お答えをいたします。
私も、還付金はいただいておりませんでしたので、その時点で、いわゆる還付金の仕組みがあるかどうかということについては承知をしておりませんでした。
○塩川委員 その時点では承知していなかったと。今はそういう仕組みがあるということは御理解をしているということですか。
○松本大臣政務官 既に報道等の、こういう状況でございますし、昨日も党から報告書がありましたので、現時点で、そういったものがあったということについては、皆様承知しているとおり、同じように承知をしているところです。
○塩川委員 昨日出された報告書の中でも、還付金の仕組みあるいは留保金の仕組みという格好で、実際に不記載になるような仕組みについて書かれたところが出ていたわけであります。
そういったことについて違法性が問われていたわけですけれども、今の認識で結構ですから、派閥としてパーティー収入の一部を不記載にしていたということについて、違法性があった、そういうことは受け止めておられますか。
○塩崎大臣政務官 塩川委員の御質問にお答えします。
私個人としては、政治資金につきましては適正にこれまでも処理をしてまいりましたが、昨日報告書も公表されましたとおり、所属していた清和政策研究会において、こうした還付金の問題、そしてその不記載の問題等があったことにつきましては、これは、その一員として残念に思っているところでございます。
○石井大臣政務官 お答えいたします。
先ほどの違法性というお話で、そういう認識ももちろん、つまり、収支報告書に派閥としての記載がなかった点、そして修正をした点、そして各皆さんがそれに基づいて修正をしている点についてでございますので、それは、不記載ということであれば違法性を、だということで、私も承知しております。
○松本大臣政務官 お答えいたします。
ほかのお二方とも同じ感想でございますけれども、基本的に、違法性があるということは、この事態を知って初めて、こういうことがあるんだなということで認識をした次第で、それ以前については、適正に私自身は処理をしておりましたので、何も分からなかったというのが正直なところでございます。
ありがとうございます。
○塩川委員 三人は、一応不記載がないということでありますので、そういう点での政治資金規正法の違法行為ということに直接携わるということは、今回の件については指摘はされていないところでありますけれども、しかし、派閥全体が大きく疑われているわけなんですよ。そういったことについて、きちんとその問題について明らかにして本来の信頼回復の道があるわけですから、今のような答え方を続けたとしたら、安倍派はずっと裏金問題について隠し続けるのか、こういう批判を浴び続けるのは必至じゃありませんか。そのことについて、これでいいのかというのが厳しく問われるわけであります。
そういう点でも、二〇二二年、二〇二三年、安倍さんが会長に就いた、その際に、このキックバックの仕組みの変更の話があったということが報道されておりますし、幹部の方々の中でも若干そういうやり取りのことが紹介されているんですけれども、この二〇二二年、二〇二三年の派閥パーティーの際に、キックバックの仕組みの変更に関して派閥側から指示があったのか、文書とかメール等が出されたのか、こういうことについての認識をお伺いします。
○塩崎大臣政務官 塩川委員の御質問にお答えします。
そのような事実は承知しておりません。
○石井大臣政務官 私も同じくですけれども、書面、メールというのも覚えがなく、また、聞き漏らしておったら申し訳ないですけれども、私としても、キックバックの仕組みの変更ということについては認識しておりません。
○松本大臣政務官 私も同様に、そのような変更に関してというか、そもそもそういう仕組みがあるということは存じませんでしたので、派閥から指示があったということについては全く存じ上げません。
○塩川委員 是非、事務方も含めて、事実関係がどうかということは明らかにしていただきたいと思います。
最後に、今回の報告書の中でも、幹部の責任を問うような声なんかも紹介をされておりました。お三人には、安倍派の裏金問題に対する対応について、派閥の幹部の対応について、どう受け止めておられるかをそれぞれお答えください。
○塩崎大臣政務官 塩川委員の御質問にお答えいたします。
今回の問題、私自身は政治資金の報告については適正に行っておりましたけれども、先ほど申し上げたとおり、所属していた政策集団においてこのような問題が起きてしまったことを大変残念に思っておりますし、そうしたことによって国民の皆様に政治不信を招いてしまっていることを大変申し訳なく思っているところでございます。
それぞれが、国会議員でございますので、ほかの人がどうこうというよりは、自分がまず、政治不信の解消のために何ができるか、そういったことをしっかりと考えて行動してまいりたいと思っております。
○石井大臣政務官 お答えします。
派閥の幹部の責任という御質問でございますけれども、まず、私自身、所属していた集団、政策集団における派閥の幹部の責任をどう私が思っているかどうかということは、この場でお答えすること自体を差し控えさせてはいただきたいと思っておりますし、派閥の責任については派閥の責任の中で、今後についても考えていただきたい点だと思っております。ここでお答えするのは差し控えさせていただきたい、そう思います。
○松本大臣政務官 お答えいたします。
リーダー論については、いろいろ思うところ、たくさんございますけれども、ここでそれを披瀝するのは差し控えたいと思います。
ただ、少なくとも、個々でいろいろな判断があって、個々でいろいろな事実があるんだろうというふうに思います。それを明確にしていくということは必要だろうというふうには思っております。
以上です。
○塩川委員 極めて残念な答弁であります。やはり国民がこれだけ怒っているときに、その批判の中心となっている安倍派における裏金問題について全容解明をするという立場に立っていないということでは、国民の不信が拡大するだけであります。
改めて、厳しくその問題を指摘するとともに、今後是非しっかり答えていただきたいということを重ねて申し上げて、お三方はここで退出していただいて結構であります。