党国会議員団の茨城県原子力施設調査。今日は日本原電の東海第2原発の周辺自治体と懇談。東海村、那珂市、茨城県、水戸市を訪問。その後、市民団体と懇談します。笠井亮・藤野保史衆院議員、岩渕友参院議員と参加。梅村さえこ参院比例予定候補、大内くみ子参院茨城選挙区予定候補、江尻かな県議、党市村議も一緒です。
 山田修・東海村長と懇談。日本原子力発電(原電)は3月、東海村及び周辺5市との間で、東海第2原発の再稼働の際には事前了解を必要とする協定を結びました。
山田修・東海村長と懇談。日本原子力発電(原電)は3月、東海村及び周辺5市との間で、東海第2原発の再稼働の際には事前了解を必要とする協定を結びました。
山田村長は「村と周辺5市の関与は重要。事前了解は譲れないと村上前村長も頑張った。協定の運用では課題もある。5市と連携取りながらやりたい」と述べました。広域避難計画については、複合災害が想定されていないことを指摘しました。
 海野徹・那珂市長と懇談。海野市長は「1000人の市民アンケートで、東海第2原発の再稼働に賛成できないという回答が65%に上った。市民の意向に沿った対応をしたい」「JCO事故のとき、最も線量が高かったのは那珂市内の地域だった。隣接自治体も入れた協定にしようと原電と交渉した。6自治体が拒否権を持つことになる」「いったん事故が起これば廃墟になる。原発はやめてほしい。大地が揺れる日本は原子力には向かない」と語っていました。
海野徹・那珂市長と懇談。海野市長は「1000人の市民アンケートで、東海第2原発の再稼働に賛成できないという回答が65%に上った。市民の意向に沿った対応をしたい」「JCO事故のとき、最も線量が高かったのは那珂市内の地域だった。隣接自治体も入れた協定にしようと原電と交渉した。6自治体が拒否権を持つことになる」「いったん事故が起これば廃墟になる。原発はやめてほしい。大地が揺れる日本は原子力には向かない」と語っていました。
 高橋靖・水戸市長と懇談。高橋市長は「事前了解権が取れたのは大きな成果だった」「再稼働の判断にあたっては、広域避難計画の策定や有識者会議の議論、市民の意見を聞くなど、いろんな政策決定過程を踏まえないといけない」「実効性ある広域避難計画ができない限り、再稼働はあり得ない」と語りました。
高橋靖・水戸市長と懇談。高橋市長は「事前了解権が取れたのは大きな成果だった」「再稼働の判断にあたっては、広域避難計画の策定や有識者会議の議論、市民の意見を聞くなど、いろんな政策決定過程を踏まえないといけない」「実効性ある広域避難計画ができない限り、再稼働はあり得ない」と語りました。
茨城県担当者との懇談もおこないました。また、夜には市民団体のみなさんと意見交換会をおこない、貴重な提案をいただきました。
東海第2原発再稼働反対の市民の運動と世論の広がりが自治体を動かし、原電に迫る力となっています。この力をさらに大きく!国会論戦でも頑張ります!
東海第2原発の再稼働ストップ、運転延長阻止、そして廃炉を実現しよう!
「しんぶん赤旗」9月14日付・15面より
再稼働事前了解で懇談/東海第2/共産党国会議員団と首長
日本原子力発電(原電)が老朽原発の東海第2原発(茨城県東海村)の再稼働を狙っている問題などに関して、日本共産党の国会議員団らは13日、同県を訪れ高橋靖水戸市長、海野徹那珂市長、山田修東海村長とそれぞれ懇談しました。
同原発の再稼働をめぐっては、立地する東海村と周辺30キロ圏内の計6市村が今年3月、事前了解権を有する安全協定を原電と結びました。県と立地する市町村のみに限られていた事前了解権を周辺自治体に拡大したのは全国初。
高橋市長は、「事前了解権を得られたのは大きな成果だ。これからも6自治体で連絡、連携を密にしたい」と述べました。水戸市議会が今年6月、再稼働を認めない意見書を可決したことについて「市民の代表者である市議会の決定であり、真摯(しんし)に受け止めて対応したい」と表明。「実効性のある避難計画が策定されない限り、再稼働の議論はあり得ない」と強調しました。
海野市長は、事前了解権について「原発のリスクは、1カ所だけでなく周辺自治体も背負っている」と指摘。市民アンケートで再稼働に反対する意見が多数だったと紹介し「首長としては、市民の意向に沿った行動をとるのが私の責任だ」と述べました。
東海村の山田村長は「事前了解権は最低限であり、譲れない。住民の安全安心のため、首長が声を上げ続けることが大事だ」と述べました。
懇談には、笠井亮、塩川鉄也、藤野保史の各衆院議員、岩渕友参院議員、梅村さえこ参院比例予定候補(前衆院議員)、大内くみ子同茨城選挙区予定候補、山中たい子、江尻加那、上野高志の各県議など自治体の党議員らが参加しました。
水戸市内で、再稼働に反対する県内の住民団体などと懇談し、意見交換しました。
 公文書作成に関する野党合同ヒアリングに出席。
公文書作成に関する野党合同ヒアリングに出席。
 埼玉県北本市で日本共産党を語るつどい。中村洋子・湯沢美恵 両北本市議も一緒です。
埼玉県北本市で日本共産党を語るつどい。中村洋子・湯沢美恵 両北本市議も一緒です。



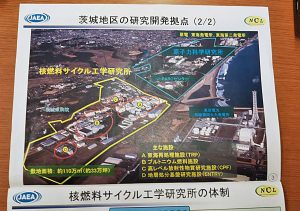
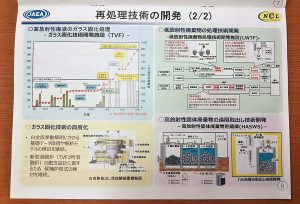
 山田修・東海村長と懇談。日本原子力発電(原電)は3月、東海村及び周辺5市との間で、東海第2原発の再稼働の際には事前了解を必要とする協定を結びました。
山田修・東海村長と懇談。日本原子力発電(原電)は3月、東海村及び周辺5市との間で、東海第2原発の再稼働の際には事前了解を必要とする協定を結びました。 海野徹・那珂市長と懇談。海野市長は「1000人の市民アンケートで、東海第2原発の再稼働に賛成できないという回答が65%に上った。市民の意向に沿った対応をしたい」「JCO事故のとき、最も線量が高かったのは那珂市内の地域だった。隣接自治体も入れた協定にしようと原電と交渉した。6自治体が拒否権を持つことになる」「いったん事故が起これば廃墟になる。原発はやめてほしい。大地が揺れる日本は原子力には向かない」と語っていました。
海野徹・那珂市長と懇談。海野市長は「1000人の市民アンケートで、東海第2原発の再稼働に賛成できないという回答が65%に上った。市民の意向に沿った対応をしたい」「JCO事故のとき、最も線量が高かったのは那珂市内の地域だった。隣接自治体も入れた協定にしようと原電と交渉した。6自治体が拒否権を持つことになる」「いったん事故が起これば廃墟になる。原発はやめてほしい。大地が揺れる日本は原子力には向かない」と語っていました。 高橋靖・水戸市長と懇談。高橋市長は「事前了解権が取れたのは大きな成果だった」「再稼働の判断にあたっては、広域避難計画の策定や有識者会議の議論、市民の意見を聞くなど、いろんな政策決定過程を踏まえないといけない」「実効性ある広域避難計画ができない限り、再稼働はあり得ない」と語りました。
高橋靖・水戸市長と懇談。高橋市長は「事前了解権が取れたのは大きな成果だった」「再稼働の判断にあたっては、広域避難計画の策定や有識者会議の議論、市民の意見を聞くなど、いろんな政策決定過程を踏まえないといけない」「実効性ある広域避難計画ができない限り、再稼働はあり得ない」と語りました。 北海道胆振東部地震についての野党合同対策会議。政府から取り組み状況を聞くとともに、現地の議員から被災者の要望、対応策について報告、提案がありました。
北海道胆振東部地震についての野党合同対策会議。政府から取り組み状況を聞くとともに、現地の議員から被災者の要望、対応策について報告、提案がありました。 復旧策や全道停電など政府の災害対応についての検証と被災者支援のための制度創設・財政措置を求めたい。
復旧策や全道停電など政府の災害対応についての検証と被災者支援のための制度創設・財政措置を求めたい。 新宿駅西口で、憲法共同センターの憲法9条宣伝行動。3000万人署名への協力を訴えました。
新宿駅西口で、憲法共同センターの憲法9条宣伝行動。3000万人署名への協力を訴えました。 緊急事態には国の権限を強めることが必要だと言いますが、災害時に必要なことは、現場の権限を強めること、被災者に一番近い自治体の権限を強化することです。有事を口実に基本的人権を侵害することは認められません。
緊急事態には国の権限を強めることが必要だと言いますが、災害時に必要なことは、現場の権限を強めること、被災者に一番近い自治体の権限を強化することです。有事を口実に基本的人権を侵害することは認められません。 大宮駅西口デッキで、オール埼玉総行動実行委員会のリレー駅頭大宣伝。
大宮駅西口デッキで、オール埼玉総行動実行委員会のリレー駅頭大宣伝。 通常国会の憲法審査会で、改憲議論を行わせなかったのは、安倍改憲ストップの3000万人署名の力。市民と野党の共闘の成果です。
通常国会の憲法審査会で、改憲議論を行わせなかったのは、安倍改憲ストップの3000万人署名の力。市民と野党の共闘の成果です。 オール埼玉総行動実行委員会のリレー駅頭大宣伝、上尾駅東口。
オール埼玉総行動実行委員会のリレー駅頭大宣伝、上尾駅東口。 立憲主義を取り戻す!戦争させない!9条こわすな!
立憲主義を取り戻す!戦争させない!9条こわすな! 熊谷駅北口。オール埼玉実行委員会が取り組むリレー駅頭大宣伝に参加。
熊谷駅北口。オール埼玉実行委員会が取り組むリレー駅頭大宣伝に参加。 小出実行委員長、後援団体の埼玉県弁護士会・連合埼玉・埼労連の代表、11区・12区市民の会代表らがあいさつ。
小出実行委員長、後援団体の埼玉県弁護士会・連合埼玉・埼労連の代表、11区・12区市民の会代表らがあいさつ。 首都圏反原発連合の原発ゼロ、再稼働反対抗議行動。
首都圏反原発連合の原発ゼロ、再稼働反対抗議行動。 日本共産党国会議員団は新宿駅西口で、北海道大地震、台風21号災害の被災者救援募金に取り組みました。
日本共産党国会議員団は新宿駅西口で、北海道大地震、台風21号災害の被災者救援募金に取り組みました。 八ッ場ダムを考える1都5県議会議員の会の勉強会に参加。渡辺洋子さん、嶋津暉久さんが講演しました。
八ッ場ダムを考える1都5県議会議員の会の勉強会に参加。渡辺洋子さん、嶋津暉久さんが講演しました。
