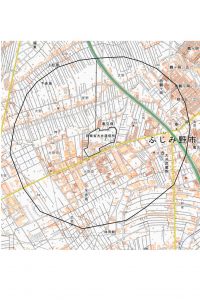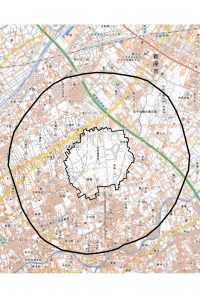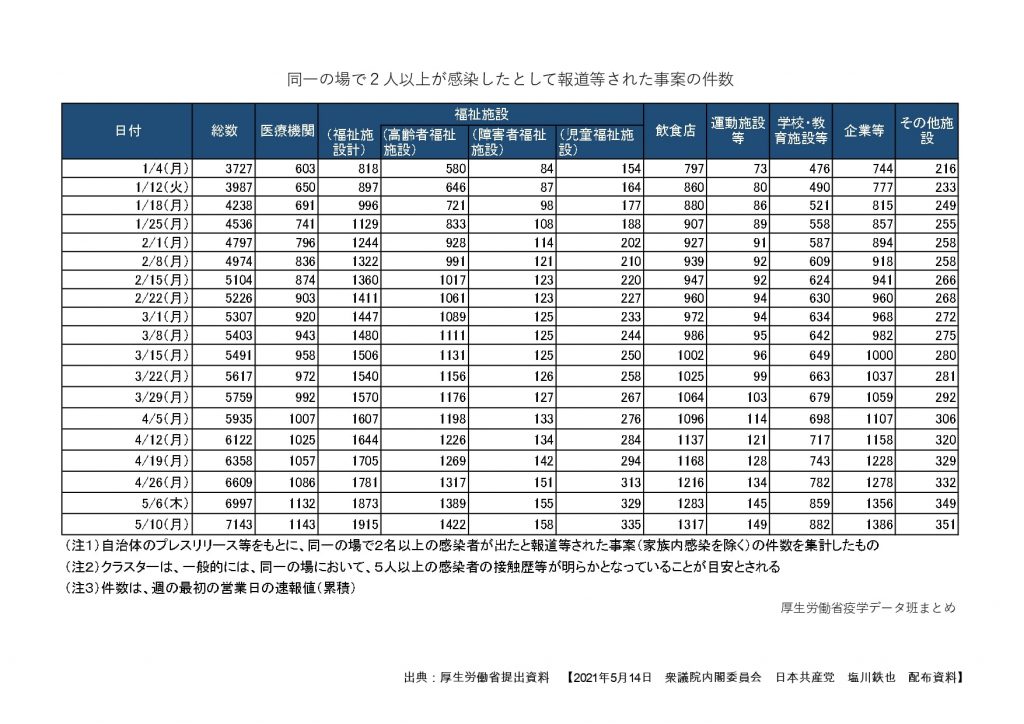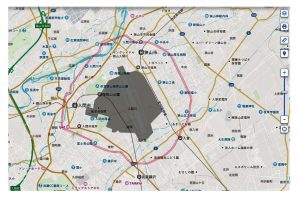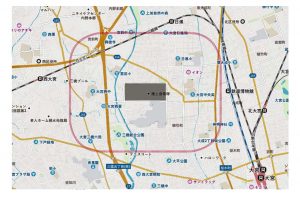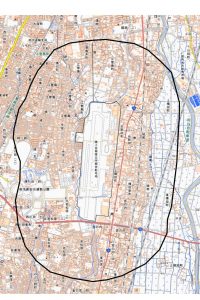緊急事態宣言と「まん延防止等重点措置」の期間延長・適用拡大にあたり政府から事前報告を受け、質疑を行いました。
緊急事態宣言と「まん延防止等重点措置」の期間延長・適用拡大にあたり政府から事前報告を受け、質疑を行いました。
東京オリンピック・パラリンピック期間中に、大会組織員会が看護師500人、スポーツドクター200人の派遣や指定病院として都内約10か所、都外約20か所の確保を要請している。
私は、医療現場への負担を考えてもオリンピックとコロナ対策は両立しないと強調し、開催は変異株など感染拡大の危惧がある。中止を提起すべきだと迫りました。
西村康稔担当大臣は「最終的な判断権限はIOCにある。安全・安心な大会の実現に向け、緊急事態宣言の延長も含め、感染を抑える」と強弁。
私は、菅義偉総理は『IOCが開催権限を持っている』として、責任を丸投げしようとしているが許されないと批判しました。
また、事業者が安心して休業できるよう事業規模に応じた補償が必要、持続化給付金の再支給を行うよう迫りましたが、西村大臣は応じませんでした。
私は、政府が発熱患者の診療や検査をする診療・検査医療機関への補助金を3月末で打ち切ったことを厳しく批判し、補助制度を復活をと主張しましたが、西村大臣はこちらにも応じませんでした。
衆議院TV・ビデオライブラリから見る
「議事録」
<第204通常国会 2021年5月7日 議院運営委員会 33号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
感染が広がる中、コロナ対策とオリンピック・パラリンピック開催は両立しないのではないか。
オリンピック・パラリンピック期間中、来日する選手は約一万五千人、大会関係者は数万人です。必要となる医療スタッフは約一万人。大会組織委員会は、日本看護協会に看護師五百人の派遣を要請し、日本スポーツ協会に二百人のスポーツドクターを要請したといいます。これらとは別に、大会指定病院として、都内約十か所、都外約二十か所程度を確保するといいます。ホストタウンとなっている五百二十八の自治体や医療機関の負担も大きい。
コロナ感染症対応、ワクチン接種で奮闘している医療現場にとって、このようなオリパラ対応は大きな負担ではありませんか。
○西村国務大臣 東京大会に必要な医療スタッフの確保につきましては、現在、組織委員会におきまして、地域の医療体制に支障を生じさせないよう、医療機関や競技団体等の意見を丁寧に伺いながら、必要な医療スタッフの精査を行っている状況にあると聞いております。
御指摘の、看護師の派遣につきましては、組織委員会が日本看護協会に対しまして大会期間を通じてトータル五百人程度を目安に協力の要請を行ったというふうに承知をしております。スポーツドクターについても同様に、日本スポーツ協会に対してトータル二百人程度を目安に協力の依頼を行ったと承知しております。
また、御指摘の大会指定病院につきましては、アスリート等に対して、選手村、総合診療所、あるいは競技会場の医務室等の機能を超える治療等が必要な場合などに搬送する仕組みとなっておりますけれども、現在、組織委員会におきまして、都内約十か所程度、都外約二十か所程度を念頭に、競技会場等周辺の大学病院等を大会指定病院の指定先として調整しているものというふうに聞いているところであります。
○塩川委員 オリンピック・パラリンピック開催は、変異株など感染拡大の強い危惧が生じます。また、医療機関、医療スタッフにも大きな負担をかける。コロナ対策担当大臣として、開催中止を提起すべきではありませんか。
○西村国務大臣 東京大会に対する最終的な判断権限はIOCにあるというふうに理解をしております。現在、関係者が一丸となって、今年の夏に東京大会を開催すべく準備を進めているところであります。
安全、安心な大会にするために感染対策が極めて重要であること、これはもう間違いございません。地域医療に支障を生じさせず、大会において必要な医療体制を確保できるよう、組織委員会において、様々な団体、医療機関の意見を聞きながら、丁寧に調整を進めているところと承知をしております。
私は開催の可否についてコメントする立場にはありませんけれども、とにかく、安心、安全な大会となるように、その実現に向けて、引き続き、この緊急事態宣言の延長も含めて、感染を抑えていく、そのことに全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております。
○塩川委員 菅総理は、IOCが開催権限を持っているとして、責任を丸投げし、自らの責任を回避しようとしているというのは許されません。コロナ感染拡大を防止するため、開催地となる国の政府として、中止の決断をするよう、改めて働きかけるべきではありませんか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、この夏に開催するべく、現在、関係者が一丸となって準備を進めているところでございます。先日のIOC総会、三月十一日の総会では、組織委員会がコロナ対策を中心とした準備状況の報告を行い、今年の夏に大会を開催することが改めて確認をされております。
いずれにしても、感染対策が重要なことは、これはもう論をまたないところでありますので、今回の緊急事態宣言の延長も含めて、とにかく、この感染を徹底して抑えていく、このことに全力を挙げていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 事業者支援についてお聞きします。
安心して休業できるように、思い切った補償を行うべきであります。事業規模に応じた支援が必要です。また、持続化給付金の再支給を是非とも行うべきではありませんか。
○西村国務大臣 去年の春からすればもう一年、そして今回の緊急事態宣言、そして延長と、飲食店始め、あるいはエンターテインメントの皆さん方、文化芸術の皆さん方、あるいは、今回、百貨店、大型施設の皆さん方、もう様々な事業者の皆さんに休業要請や時短の要請などを行って、本当に厳しい状況におられると思います。
政府としてできる限りの支援をしっかりと行っていきたいと考えておりますが、国会でも御議論いただきましたように、それぞれの事業規模や影響に応じて支援を考えていくべきだということで、今般、飲食店に対しては月額最大六百万円の支援、協力金の支給、それから、大型の商業施設につきましても、規模に応じた支援となるよう、テナントの数などに応じた支援、協力金の仕組みをつくったところでございます。
また、雇用調整助成金、これは大企業も含めて、パート、アルバイトも含めて一日一万五千円まで、シフト減も含めて国が全額支援をできる仕組みを構築しておりますので、雇用もしっかりと維持をしていただければありがたいというふうに考えております。
個人の事業主最大二十万円、あるいは法人四十万円の、影響を受けた皆さん方への支援金も、経産省において準備を急いでいるところでございます。
いずれにしましても、感染状況や経済的な影響をしっかりと見極めながら、残り四・五兆円の予備費もございますので、必要な対策を機動的に講じていきたいと考えております。
○塩川委員 持続化給付金の再支給は考えませんか。
○西村国務大臣 持続化給付金につきましては、感染症の影響が不透明な昨年の、よく分からなかった段階で全国に緊急事態宣言を発出した、幅広く経済を人為的に止めた中で、厳しい状況に置かれた事業者に一律に給付をしたものでございます。
今回、緊急事態措置、蔓延防止重点措置など、一月―三月は飲食店に焦点をかなり絞っておりますし、今回、百貨店や大型施設に、あるいは様々なイベント、こういったところに対しては、キャンセル料の支援や、あるいは大型施設への協力金など、必要な支援を行ってきているところでございます。
いずれにしましても、感染状況あるいは経済の状況を見ながら、機動的に対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 雇用調整助成金については、全国の特例措置は四月末までで、五月以降、縮減していくことになっています。
この現行の特例措置を五月以降もしっかりと継続すべきだと思いますが、この点、いかがですか。
○西村国務大臣 前年又は前々年の同期と比べて、最近三か月の月平均が三〇%以上減少している企業、これは、大企業、中小企業、あるいは地域、業種問わず、こういった企業については、五月、六月、引き続き、先ほど申し上げたパート、アルバイトを含めて一日上限一万五千円、一〇〇%で国が支援をしていくこととしております。
今後とも、この雇調金につきましては、まずは厚生労働省において適切に対応されていくものと考えておりますけれども、感染状況、雇用状況など、私の方でも分析をしながら、田村大臣と連携をして対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 地域医療機関の支援が必要です。コロナ患者受入れの有無にかかわらず、地域医療を支える医療機関に減収補填を行うべきだ。また、診療・検査医療機関に対する外来診療、検査体制確保の補助制度を是非とも復活してもらいたい。
○西村国務大臣 医療機関の皆様方にも、様々な現場での対応、本当に心から敬意を表したいというふうに思います。
そうした皆様方、コロナ患者受入れの有無にかかわらず、しっかりと支援をしていくことが大事だと考えております。
コロナ対応を行っておられない診療所や薬局に対しても、これまで、感染拡大防止のための支援も含めて、医療機関支援としては全体として四・六兆円の予算を計上し、様々な費用の補助を行ってきているところでございます。
また、コロナ病床に対しては、一床最大一千九百五十万円の支援を引き続き行ってきているところでございまして、コロナ病床は昨年五月時点の一万六千床から現時点で約三万床に増加をしているところでございます。
引き続き、都道府県、そして厚労省、連携しながら、必要な地域医療を確保できるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
また、御指摘の補助制度につきましては、昨年九月に、インフルエンザと同時流行を想定して、予備費による財政支援を実施したものでございます。これは、幸い、多くの人がマスクをつけて感染防止策を徹底されたおかげだと思いますけれども、インフルエンザの流行は実際には大きなものは起こらず、その想定時期も過ぎたことから、この事業は予定どおり年度末で終了したものでございます。
他方、昨年の十二月、三次補正によりまして、診療・検査医療機関に対する感染拡大防止対策や診療体制確保に対する費用に対する補助の制度を継続することとしております。
診療報酬においても一定の加算ができることとしておりますので、引き続き、国民の皆様に必要な、相談あるいは外来の診療、こうした体制を確保すべく、厚労省と連携をして対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 終わります。
 2018年の公職選挙法の改定で罰則規定が抜け落ち2年以上放置されていたことを受け、誤りを修正した改正案が、日本共産党を含む賛成多数で可決しました。
2018年の公職選挙法の改定で罰則規定が抜け落ち2年以上放置されていたことを受け、誤りを修正した改正案が、日本共産党を含む賛成多数で可決しました。