地方議会でも意見書採択が相次いでいます。
物価高騰に見合った診療報酬の引き上げとともに緊急対策としての財政支援を。
専門性にふさわしい賃金水準に。
 新方川の堤防改修や堤防未整備箇所の予算措置など埼玉東部南地域の党の責任者として奮闘してきたのが苗村京子さん。
新方川の堤防改修や堤防未整備箇所の予算措置など埼玉東部南地域の党の責任者として奮闘してきたのが苗村京子さん。
 自民党が6割を占める県議会で県民の声を届けてきたのが党県議団。
自民党が6割を占める県議会で県民の声を届けてきたのが党県議団。
学校給食費無償化、消費税減税、大軍拡反対の願いを苗村候補へ!
暮らし守る なえむら氏を/埼玉県議補選/城下・塩川氏ら応援
30日投票の埼玉県議補選東8区(越谷市、欠員2)は、日本共産党の、なえむら京子候補=新=と、自民系の3氏、地域政党「越谷市民ネットワーク」の前市議の新人5氏による大激戦となっています。
県議補選は、県民の暮らしが厳しいなか、国政でも県政でも暴走を続けてきた自民党に対し、なえむら氏の勝利でノーを突きつけるかどうかが問われています。
21日には城下のり子県議団長、24日には塩川鉄也国対委員長・衆院議員が、なえむら氏の応緩に駆けつけました。
城下氏は、県議会では、共産党以外の賛成で県が自治体に供給する水道用水の21%値上げが決まったこと、自民党県議団が虐待禁止条例の改定で子どもだけの留守番を禁止しようとしたことを告発しました。
共産党は県民とともに水道用水値上げ反対の署名を3万人分以上集め、幅広い県民との運動で虐待禁止条例の改定を撤回させたと強調し「県議会では自民党が多数の議席を占めるなか、県民への負担増やサービス切り捨てが進められてきた。なえむらさんの勝利で、何としても変えよう」と呼びかけました。
塩川氏は、水害の多い越谷市で、共産党の金子正江元県議(東8区選出)の追及で新方川の堤防改修などが実現したとして「共産党の、なえむら候補の議席は災害対策を前に進めるために、なくてはならない議席です」と強調。国の悪政にもはっきりとものか言える議席が必要だとして「越谷から高市政権に厳しい審判を」と訴えました。
24日には、北越谷駅前でロングラン宣伝も行われ、党員らがシールアンケートで県民と対話。消費税減税や平和外交を求める声がつぎつぎと寄せられました。
多くの県民の願いを聞いてきた、なえむら氏は「命・暮らしを守る政治の実現へ、県議会に送ってください」と訴えています。
 私は、今年6月に全会一致で成立した、手話のさらなる普及をめざす「手話施策推進法」に基づく取組の具体化として、各省庁の審議会や要請の場などで手話通訳者を配置すること、そして手話通訳者の配置についてホームページ(HP)等で周知するよう求めました。
私は、今年6月に全会一致で成立した、手話のさらなる普及をめざす「手話施策推進法」に基づく取組の具体化として、各省庁の審議会や要請の場などで手話通訳者を配置すること、そして手話通訳者の配置についてホームページ(HP)等で周知するよう求めました。
今年6月に行われた手話施策推進法の質疑で、私が「手話通訳者の手配を政府が負担する形で実施すべきだ」と求めたのに対し、当時の三原内閣府担当大臣は「各府省庁に対して通知を発出して各種審議会での取り組みを促していきたい」と答えました。これを受け内閣府は6月25日、各省庁に対し、各審議会等において手話通訳者の配置など適切な情報保障を実施するよう求める事務連絡を出しました。
私は、事務連絡に対する各省庁の対応状況について内閣府は把握しているか質問。黄川田大臣は、内閣府としては把握していないと答えました。
私が独自に各府省庁に対して対応状況について回答を求めたところ、手話通訳等の配置についてHPで周知していることが確認できたのは、内閣府の障害者施策担当だけだったことを指摘。「手話通訳者の配置を国の負担で行うと共に、各府省庁のHPで『事前に連絡があれば手話通訳の配置等の対応をする』と掲示すべきだ」と強調しました。
黄川田大臣は、「障害者差別解消法の主旨を踏まえ障害のある傍聴者に対して合理的配慮を行う必要がある。障害のある方が希望を伝えやすいようHP等で案内することは重要だ。改めてHPの記載例を示すなどさらに分かりやすく通知し、各省庁に周知したい」と答えました。私は、「ぜひ力を尽くしてほしい」と求めました。
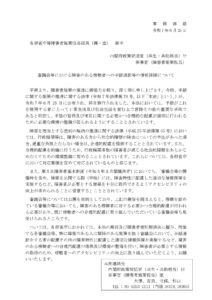 |
 |
 |
 |
手話通訳配置 周知を/塩川議員 国は対応未把握/衆院内閣委
日本共産党の塩川鉄也議員は19日の衆院内閣委員会で、6月に全会一致で成立した手話の普及をめざす「手話施策推進法」に基づく取り組みの具体化として、各省庁の審議会や要請の場などに手話通訳者を配置し、配置についてホームページ(HP)などで周知するよう求めました。
6月の同法案の質疑で、塩川氏が「手話通訳者の手配を政府が負担する形で実施すべきだ」と求めたのを受け、内閣府は同25日、各省庁に、各審議会などへの手話通訳者の配置など、聴覚障害者への適切な情報保障を実施するよう求める事務連絡を出しました。
塩川氏は、各省庁の対応状況を把握しているのかと質問。黄川田仁志内閣府担当相は、把握していないと答えました。塩川氏が独自に各府省庁に対応状況について回答を求めたところ、HPでの手話通訳等の配置の周知を確認できたのは内閣府の障害者施策担当だけだったと指摘。「手話通訳者の配置を国の負担で行うとともに、各府省庁のHPで『事前に連絡があれば手話通訳の配置等の対応をする』と掲示すべきだ」と強調しました。
黄川田担当相は「障害のある傍聴者に対して合理的配慮を行う必要がある。障害のある方が希望を伝えやすいようHP等で案内することは重要だ。改めてHPの記載例を示すなどさらに分かりやすく通知し、各省庁に周知したい」と答えました。
 私は、高市早苗首相が策定を指示した総合経済対策の3つの柱の1つに「防衛力の強化」が位置付けられている問題を追及しました。
私は、高市早苗首相が策定を指示した総合経済対策の3つの柱の1つに「防衛力の強化」が位置付けられている問題を追及しました。
私は「これまで政府が経済対策の柱として『防衛力の強化』を掲げたことはあるか」と質問。城内実経済財政担当大臣は「柱として掲げたことはない」と答えました。
私が「防衛力の強化がなぜ経済対策なのか」と追及したのに対し、城内大臣は、その理由として、自衛官の所得向上による生産消費の活性化、デュアルユース(軍民両用技術)の民生転用の波及効果、などを挙げました。
私は「GDP比2%の大軍拡を前倒しで達成するために1.1兆円が必要となる。それを積む補正予算の理屈なのではないか」と指摘し「大軍拡を具体化する口実として、経済対策の柱の1つとしていることが問われる」と批判。
また、デュアルユースの問題点として「デュアルユースの名の下にAI技術の軍事利用が進んでいる」と指摘。すでに日米が2023年末に、次期戦闘機と連動する無人機の共同研究に合意しているとして「憲法9条を持つ国として断じて認められない」と強調しました。
さらに、防衛装備の海外移転についても追及。自民と維新の連立合意に盛り込まれた「防衛装備移転三原則」の運用指針の撤廃について、「殺傷能力のある武器の輸出が経済対策として推進されることになるのではないか」と質問。防衛装備庁は「経済対策の中身について現時点で答えることは控える」としつつ「22年に決定された防衛力整備計画では、『防衛装備品の海外移転は、販路拡大を通じた防衛産業の成長性の確保にも効果的』とある」と答えました。
私は、政府の日本成長戦略会議でも、同盟・同志国との防衛産業サプライチェーンの協力推進について議論が行われているとして、どのようなことを検討しているのか追及。防衛装備庁は、日米両政府の「日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議(DICAS)」などを通じ協力を進めたいと答弁しました。
私は、トランプ大統領が大軍拡を要求する下で、「(日本の軍需産業が)世界各地の紛争国に兵器を提供している米国の下請けになるのではないか」と批判しました。
大軍拡 どこが経済対策/衆院内閣委/塩川氏“憲法9条に反する”
日本共産党の塩川鉄也議員は19日、衆院内閣委員会で、高市早苗首相が策定を指示した総合経済対策の柱に「防衛力の強化」が位置づけられている問題を追及しました。
塩川氏は「これまで経済対策の柱として『防衛力の強化』を掲げたことはあるか」と質問。城内実経済財政相はないことを認めました。塩川氏の「防衛力の強化がなぜ経済対策なのか」との追及に対し、城内氏は▽自衛官の所得向上による生産消費の活性化▽デュアルユース(軍民両用技術)の民生転用の波及効果―などを挙げました。
塩川氏は「GDP(国内総生産)比2%の大軍拡の前倒しを達成するために1・1兆円必要になる。それを積む補正予算の理屈なのではないか」と指摘。デュアルユースの名の下にAI(人工知能)技術の軍事利用が進み、日米が2023年末に次期戦闘機と連動する無人機の共同研究に合意したとして「憲法9条をもつ国として断じて認められない」と強調しました。
さらに、自民と維新の連立合意書に盛り込まれた「防衛装備移転三原則」の運用指針の撤廃を巡り、「殺傷能力のある武器の輸出が経済対策として推進されることになる」と告発。政府の日本成長戦略会議が議論している、同盟・同志国との防衛産業サプライチェーン(供給網)での協力推進とは何かと追及しました。
防衛装備庁の小杉裕一装備政策部長は、日米両政府の「日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議(DICAS)」などを通じ協力を進めたいと答弁。塩川氏は、トランプ政権が大軍拡を要求する下で「(日本の軍需産業が)世界各地の紛争国に兵器を提供している米国の下請けになる」と批判しました。
日本共産党はこの間、ガソリン暫定税率廃止のための与野党協議会に参加、実現のために力を尽くしてきました。
物価高騰下の国民の負担軽減策として早期の実施を求め、財源としては庶民に負担転嫁することのないように担税力のある大企業や富裕層への応分の負担を働きかけてきました。
粘り強く求めてきたことで、ガソリン暫定税率は年内の12月31日に廃止することとし、それに先立ち補助金を使った負担軽減措置が実施されることになりました。
財源については、法律に「法人税関係特別措置の見直し」や「極めて高い所得に対する負担の見直し」の税制の見直しが規定されることに。
今度はぜひとも消費税減税を実現したい。与野党協議を呼びかけていくものです。財源はガソリンの場合と同様、大企業・富裕層への負担でこそ。
 コメの増産、クマ被害対策、中小企業への賃上げ支援、PFAS汚染対策への支援、学校給食費無償化、JR吾妻線の存続・拡充、保育士の処遇改善、桐生市による違法・不適切な生活保護行政に対する監査指導の強化、医療機関への支援など切実な要望を届けました。
コメの増産、クマ被害対策、中小企業への賃上げ支援、PFAS汚染対策への支援、学校給食費無償化、JR吾妻線の存続・拡充、保育士の処遇改善、桐生市による違法・不適切な生活保護行政に対する監査指導の強化、医療機関への支援など切実な要望を届けました。
コメ価格保障・クマ対策・生活保護/県民の要求で政府交渉/党群馬
日本共産党群馬県委員会は17日、県民の切実な要求について政府交渉をしました。酒井宏明、大沢綾子両県議ら12人の地方議員などが参加し、1府12省庁に108項目を要請。塩川鉄也衆院議員、岩渕友参院議員、梅村さえこ元衆院議員が同席しました。
農水省への要請で、コメの増産にかじを切った前政権に対し、高市政権では「また減産か」という不安の声が農家から出ているとただし、価格保障を求めました。拡大しているクマの被害について、沼田市の大東宣之市議は「沼田市では10月だけで43頭を捕獲、例年2、3頭の10倍以上」と訴え、対策の強化を求めると、農水省担当者は政府が14日にとりまとめた「クマ被害対策パッケージ(概要)」を説明。参加者は「引き続きの強化」を求めました。
厚労省への要請では、今年の夏の異常な暑さを前提に、新規の生活保護利用者へのエアコン導入だけでなく、既利用者へのエアコン購入・修理・交換への補助を要求。厚労省担当者は「保護費のやり繰り」や「生活福祉資金の貸し付け」で購入を求めると回答。参加者は 「いまや『健康で文化的な最低限度の生活』にエアコンは必要不可欠、しかも『やり繰り』や貸し付けの返済ができる保護費が渡されているのか、実態を知るべきだ」と見直しを求めました。
地域要求では高崎市の堤ケ岡飛行場跡地の優良農地存続や小学校午前7時開門、学校給食無償化、JR吾妻線の存続、渋川市のPFAS、邑楽町の系統用蓄電所、文化財保護、米軍機低空飛行などの問題について要望しました。
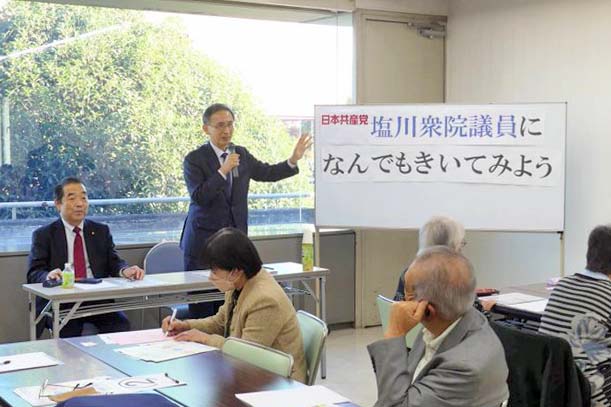 高市政権をどう見るか、中小企業への賃上げ支援策、自営業や年金生活者への支援、地球温暖化対策、食料・農業問題、派遣や契約社員などの不安定雇用問題など、多岐にわたる質疑応答。
高市政権をどう見るか、中小企業への賃上げ支援策、自営業や年金生活者への支援、地球温暖化対策、食料・農業問題、派遣や契約社員などの不安定雇用問題など、多岐にわたる質疑応答。
日本共産党としんぶん赤旗の魅力を訴えました。
年金・医療…疑問に答える/群馬/塩川氏が集いで入党訴え
日本共産党の塩川鉄也衆院議員・国対委員長は15日、群馬県太田市・大泉町と同館林市の2ヵ所の集いに参加し、国会情勢と党の立場を話し、参加者の疑問に丁寧に答え、入党を訴えました。
太田市・大泉町の集いには45人が参加。「高市政権に共産党はどう立ち向かう?」「最賃が毎年上がっているが、物価高でも下請け単価が上がらない。最賃1500円以上になると商売がやっていけなくなるかも」などの質問に、塩川氏が丁寧に答えました。母親と初めて参加した女性(20代)は、「共産党の人は初めて会っても、なんでも話を聞いてもらえる安心感があります。お金が一番のような世の中はおかしい。無理な働き方をしなくても不安なく生きていける世の中になってほしい」と話しました。
塩川氏と水野正己太田市躡は3人に入党の働きかけを行いましたが、その場での入党には至りませんでした。
館林市の集いは「塩川衆院議員に、なんでもきいてみよう」と題して開催し、35人が参加。「高市政権をどう見るか」「質上げと中小企業支援」「年金」「医療」「環境問題」「農業」など多岐にわたる質問がありました。また、「共産党の政策は分かりやすいのに、国民の支持が得られないのが不思議」との声もありました。
この後、6グループに分かれて、日頃思っていることや感想を出し合いながら懇談。「入党のよびかけ」を読み合わせるなどして、11人に入党を働きかけました。その場での決意になりませんでしたが、日曜版読者が1人増えました。篠木正明・田辺純子両館林市議が参加しました。
申入書では議長の下に置かれた「衆院選挙制度調査会答申(2016年)」は、定数を「削減する積極的な理由や理論的根拠は見出し難い」と結論付けていると紹介。全党による丁寧な選挙制度の議論を求めました。
【衆院議員定数 超党派議連が衆院議長に「定数は選挙制度と切り離せるものではない」と申し入れ】
超党派の「政治改革の柱として衆議院選挙制度の抜本改革を実現する超党派議員連盟」が、額賀福志郎衆院議長らに、衆議院議員定数問題に関する申しれを行いました。
自民と日本の維新の会の「連立政権合意書」は、衆院議員定数1割削減を掲げています。
申入書では「衆議院選挙制度に関する調査会答申(2016年)」は、定数を「削減する積極的な理由や理論的根拠は見出し難い」と結論付けていると指摘。さらに、現在、衆院議長の下に置かれている「週銀選挙制度に関する協議会」では、全党は代表によって着実に議論が進められているとしています。
その上で、「衆議院議員定数の在り方は衆議院選挙制度の在り方と切り離せるものではなく」、同協議会において議論を行うよう求めています。
申入れで、私は「定数削減は民意を切り捨て、行政の監視機能を後退させる」などと指摘し、定数削減に反対を表明。2016年調査会答申が国会における議論の到達点であるとして、「このような議論を踏まえ、丁寧な議論をすべきだ」と主張しました。
公明党の岡本三成議員は「行政府側の合意の中で、立法府を制限するような項目を入れるのは越権行為ではないか」と自民・維新の合意書を批判。
自民党の古川禎久議員は「にわかに議員定数削減が持ち上がった」として、「選挙のあり方は全党派で議論すべきもの。その立場は揺らがない」と発言しました。
これを受け、額賀議長は「各党の議論は自由だが、国民を代表する院のあり方をどうするかは、各党の意見をきいて、議論し決めてい行くものだ」と発言。
浜田靖一議院運営委員長は「長きにわたり議論してきたことを尊重すべきだ」と述べました。
申入れには、自民・維新も含めた衆院に会派をもつ10党・会派の議員が名を連ねました。
定数は選挙制度のあり方/超党派議連、全党派で議論を
「政治改革の柱として衆議院選挙制度の抜本改革を実現する超党派議員連盟」は6日、額賀福志郎衆院議長を訪れ、衆院議員定数削減問題を巡り、文書で申し入れました。
自民党と日本維新の会の「連立政権合意書」は、衆院議員定数1割削減をめざすと明記しています。同議連の申し入れ書は、「衆議院選挙制度に関する調査会答申」(2016年)では「(定数を)削減する積極的な理由や理論的根拠は見いだしがたい」と結論づけており、衆院議長のもとに置かれている「衆議院選挙制度に関する協議会」でも、現在、全党派の代表によって「着実に議論が進められている」としています。その上で、「衆議院定数のあり方は衆議院選挙制度のあり方と切り離せるものではなく」、同協議会で議論を行うよう求めています。
申し入れで日本共産党の塩川鉄也国対委員長は、「定数削減は民意を切り捨て行政監視機能を後退させる」と指摘し反対を表明。16年の調査会答申は国会での議論の到達点だとして、「このような議論をふまえ、丁寧な議論をすべきだ」と主張しました。
公明党の岡本三成議員は「行政府側の合意(自民・維新両党の連立政権合意書)のなかで立法府を制限するような項目を入れるのは越権行為でないのか」と批判。自民党の古川禎久議員は「にわかに議員定数削減が持ち上がった」として、「選挙のあり方は全党派で議論すべきものだ。その立場は揺らがない」と発言しました。
申し入れに対し額賀議長は、「各党の議論は自由だが、国民を代表する院のあり方をどうするかは各党の意見を聞いて議論し、決めていくものだ」と発言。浜田靖一衆院議院運営委員長は「長きにわたり議論してきたことを尊重すべきだ」と語りました。
申し入れ書には、自民、維新も含め、衆院に会派がある10党・会派の議員が名を連ねました。