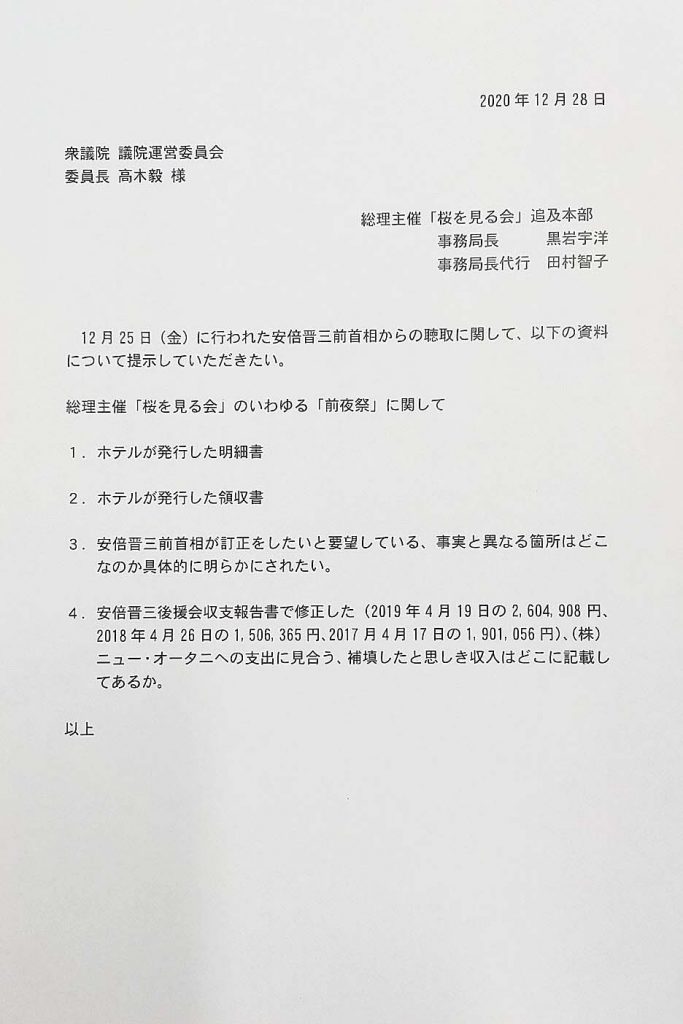科学的知見を軽視し、緊急事態宣言の再発令を招いた政府の責任を追及しました。
科学的知見を軽視し、緊急事態宣言の再発令を招いた政府の責任を追及しました。
新型コロナウイルス対策の特措法では、政府はコロナ対策の指針である基本的対処方針を定め、自治体はこの方針に基づいて対策を行うと定めています。
私は、基本的対処方針が昨年5月以降改定されず、状況が大きく変遷する中でも放置されてきた。今回のように緊急事態宣言に至らないよう、政府としてどう取り組むのかを曖昧にし、統一的な指針を示さなかった、と政府の責任を追及しました。
 西村康稔経済再生相は「5月の改定以降も専門家の提言を踏まえて通知等を出してきた」と答えたのに対し、私は、分科会提言など専門家の重要な科学的知見が繰り返し示されてきたにもかかわらず、政府が基本的対処方針に反映しなかったのは、科学的知見の軽視と言わざるを得ない、と批判しました。
西村康稔経済再生相は「5月の改定以降も専門家の提言を踏まえて通知等を出してきた」と答えたのに対し、私は、分科会提言など専門家の重要な科学的知見が繰り返し示されてきたにもかかわらず、政府が基本的対処方針に反映しなかったのは、科学的知見の軽視と言わざるを得ない、と批判しました。
さらに、分科会提言で、感染状況(ステージ)に応じた対策が必要だと示しているにもかかわらず、緊急事態宣言が発令された1都3県で、感染拡大が続いてきた中でもステージの判断を誰も行ってこなかったことを政府も認めざるをえなかった。科学的知見を軽視した国の対応が緊急事態宣言の再発令という深刻な事態を招いた反省こそ必要だ、と主張しました。
衆議院TV・ビデオライブラリから見る
「議事録」
<第203臨時国会 2021年1月13日 内閣委員会 8号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
一月七日、一都三県に緊急事態宣言が発出をされ、基本的対処方針が改定をされました。その基本的対処方針の中では、緊急事態宣言の発出及び解除の考え方を示したところであります。
緊急事態宣言発出の考え方については、国内での感染拡大及び医療提供体制、公衆衛生体制の逼迫の状況(特に、分科会提言におけるステージ4相当の対策が必要な地域の状況等)を踏まえて、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を踏まえた上で総合的に判断するとしています。そして、このようなステージ判断の指標を示した八月七日の分科会提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言の判断を行うとしております。
そこで、西村大臣にお尋ねいたします。
ステージ4相当の地域については、緊急事態宣言の発出という関係になるわけですが、そうしないためには、その前の取組が重要であって、だからこそ、このステージの判断ではステージ3が設定をされている。だとすると、ステージ1、ステージ2、ステージ3、ステージ4、ステージ4にしないためにもステージ3にどう取り組むかということが求められていたわけですが、一都三県においては、このステージ3という判断があったんでしょうか。
○西村国務大臣 ステージ3の判断につきましては、それぞれの地域の感染状況あるいは病床の確保の状況、これはそれぞれの都道府県知事が一番よく把握をしておられるわけでありますので、基本的に知事が判断をしていくということになります。そして、国としては、その状況を共有しながら、知事が適切に判断していけるようにサポートしていくことになります。
知事がステージ3であるとかということの表明があるなしにかかわらず、それに必要な対策、これは、時短であったり、さまざまな呼びかけであったり、イベントの厳格化であったり、こういった対応をとってもらっているところであります。その意味で、ステージ3相当の対策が必要な地域という言い方をしていると思います。
ステージ3に当たっているかどうか、それぞれの知事、これは機械的に全部当てはめるのではなくて、総合的に判断していくことになっておりますので、知事の判断で明確に、3になっているかなっていないかということの表明にかかわらず、それぞれの判断で、そのステージ3相当の対策が必要な地域として対策を講じてもらっているというふうに理解をしております。
○塩川委員 今まで、八月七日のこのステージ判断の指標についての提言というのは、政府の基本的対処方針に当然なかったわけです。今回盛り込まれた。そういう点でも、発出に当たってはステージ4相当の対策が必要な地域の状況という判断があり、解除に当たってはステージ3相当の対策が必要な地域の状況という判断がありという点でいえば、まさにステージというのが緊急事態宣言をめぐっての基本となるような指標ということを政府の文書にはっきりと盛り込んだわけですね。
そういったときに、そもそも緊急事態宣言にならないようにということで努力をしているときに、ステージ4にはしない、だとしたら、その前のステージ3が必要なわけで、そのステージ3という判断が行われないままだったという状況というのはまずくはないですか。
○西村国務大臣 ここは都道府県のそれぞれのお考えもあると思いますけれども、知事が基本的に病床とか感染状況を判断しながら、状況を判断しながら、自分の都道府県がどのレベルにあるかということを常に見ていくという仕組みになっております。これは私も毎日見ております。
その中で、明確にステージ3に今なっていると表明された都道府県も幾つかあると思いますけれども、そして、その中で、言っていないところも含めて、ステージ3相当の対策が必要だということで、それぞれの地域で対応がとられているというふうに理解をしております。
今回のステージ4に当たっているかどうかも、それぞれの知事が、うちは4だからと言っているところもあれば、緊急事態宣言が必要だと言っているところもあれば、4ということは明確に言わないけれども、もう緊急事態宣言が必要だという判断をされている、要請をされたところもあります。
そういう意味で、あくまでもステージ3とか4とかというのは目安で、最終的には知事がそれを見ながらどういった対策が必要かを判断していくということでございます。
○塩川委員 ちょっと戻って、確認ですけれども、じゃ、そもそも、今宣言が発出されている一都三県において、このステージの判断というのは都道府県対策本部長が行うということですよね。ですから、この一都三県で、ステージ3という判断を、この対策本部長、知事がされているかどうか。
○西村国務大臣 またちょっとややこしいんですけれども、ステージ3とか2とかいう判断、これは基本的にそれぞれの都道府県知事が、まさに感染状況や病床の状況を踏まえて基本的には判断をされていきます。
ステージ4だけがいわば……(塩川委員「いや、ステージ3について」と呼ぶ)3はそういうことです。(塩川委員「ステージ3については、一都三県の知事はそういう判断をしたのかということを聞いています」と呼ぶ)ステージ3についても、明確に、これは3も4も両方そうなんですけれども、それぞれの知事が、自分のところは3だとか4だとかということは、明確におっしゃってはいないと思います。ただ、それぞれの地域が、国の基準と相対するような、関連するような指標を設けて、それぞれの県で、自分のところは国でいえばステージ3相当の対策が必要だという判断はされてきている、今もうステージ4相当の対策が必要だということで判断をされてきているというふうに理解をしております。
○塩川委員 もともと、ステージの判断は都道府県の対策本部長ということで、この間、政府もそう言ってきましたし、実際に、でも、一都三県について言えば、知事はステージ3という判断はしていない。ですから、ステージ3相当の対策が必要な地域という前提がなしに施策を行っていたということになるんじゃないのか。
そういう点でいうと、ステージの判断をなしに行っているという今の現状というのは、国として、これはまずいとお考えになりませんか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、ステージ3かどうか明確に言うか言わないかは別として、ステージ3段階相当の対策が必要だという認識は一都三県の知事もされ、これは私からも、相応の対策が必要だということで、ステージ3相当の対策が必要だということで知事にも申し上げてきておりますし、そうした対策をとられてきている。
そして、ステージ4は、これは緊急事態宣言になりますので、最終的に国が判断をして、今回、緊急事態宣言を発出させていただきましたけれども、これは、知事もステージ4相当の対策が必要だという理解であります。
ステージ4になっているかどうかと明確に言うかどうかは別として、それぞれ、自分のところがどのレベルにあるのかということは指標に基づいて総合的に判断しながら、そのレベル相当の、ステージ3相当の対策が必要だということはそれぞれの知事が理解をしてきているというふうに思います。
○塩川委員 ただ、もともとの分科会提言というのは、やはりステージの判断で、まさに必要な対策、何をやるのかということが決まってくるという点でも、ステージの判断というのは重要だと。その判断がない中で、結果としてステージ4に行くような事態、緊急事態宣言にならざるを得なかったという点では、そういうステージの判断について曖昧なままにしていた、そういう点でも国の責任も問われざるを得ない。ステージ判断の指標というのを、分科会の提言、専門家の意見として八月七日に聞きながら、軽んじてきたのではないのかということを言わざるを得ません。
それで、コロナ対策の政府文書の根幹は、基本的対処方針であります。
特措法の逐条解説には、新型インフルエンザ対策等は、多数の関係機関により広範かつ大規模に行われることが想定されるが、これらが相互に連携して的確かつ迅速に行われるようにするためには、専門的知見と国内外の情報の集約が可能な国において、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっての準拠となるべき統一的指針を状況の変遷に応じて機動的に定め、これに基づき各主体が主体的に実施し、必要に応じ総合調整ないし指示により、その総合的かつ強力な推進を図る必要があると述べています。
このコロナ対策実施の準拠となるべき統一的指針が基本的対処方針であり、自治体も基本的対処方針に基づき対策を実施する、大臣、そういうものだということでよろしいですね。
○西村国務大臣 基本的対処方針は、まさに御指摘のように、多くの関係機関が対策を相互に連携して的確かつ迅速に実施するに当たっての準拠となるべきいわば統一的指針でありますので、そういった趣旨をしっかりと書き込んでいるものということであります。
○塩川委員 その統一的指針となるべき基本的対処方針が前回改定されたのが、前回の宣言の解除のタイミングの五月の末だったわけであります。ですから、七カ月以上改定がされなかった。これは余りにも、この統一的な指針、準拠すべきそういった方針として粗末な扱いだったのではありませんか。
○西村国務大臣 幾つかの理由がございます。
一つは、この感染状況が日々変化をし、御案内のように、夏に感染拡大し、九月、十月で一旦おさまるかのように見えても、また寒くなる中で、北海道から始まり、感染拡大が広がっていった。この日々の状況、この対処を機動的に行う必要があるということが一つ。
それから、もう一つは、このコロナについて、なかなか当初、三月、四月、わからなかったことが多かったわけですけれども、その後さまざまな新たな知見も出てきて、この国内外の研究の成果もあります、そして、最近では変異株というものも出てきている。
この変化の激しい中で、何度も何度も変更しなきゃいけない、そうした作業にも当然時間もかかるわけでありますので、そういったことから、国民に広く政府の方針を示す、あるいは関係機関が連携して取り組む必要性が生じた場合、あるいは今申し上げたような経験や知見が積み重なってきて大きな対処方針を新たに示す場合というときに改定をするということにしてきたわけであります。
今般、緊急事態宣言、そしてこの間のさまざまな知見、こういったものもありますので、改めて、前回の緊急事態宣言のときとはかなり様相が違いますので、それも含めて大きな方針を示すということで変更させていただいたものでございます。
○塩川委員 そもそも、この基本的対処方針については、特措法の逐条解説などでも、状況の変遷に応じて機動的に定めるとしているわけですよ。ですから、ある意味、専門家の知見を踏まえて、新たな知見が出れば、この間でいえば分科会の提言が何度も出されているわけです。それを織り込むということをその都度その都度やはりやってこそ、基本的な方針、統一的な指針としての役割を発揮できるんじゃないのか。
今回の場合でいえば、まさに八月七日の分科会提言におけるこのステージの判断の指標というのをそういう時点で織り込めば、ステージ3の意味もはっきりするし、ステージ4の意味もはっきりするということだったわけで、これは、そもそも基本的対処方針について、状況の変遷に応じて機動的に定めるといったことを政府として放置をしてきた、そこに問題があるんじゃないですか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、この間、何度となく、夏、そしてこの秋から冬にかけてと感染拡大を経験をして、いわば最も大きな流行を今経験しているわけでありますけれども、そして、さまざまな知見が、日々いろいろな知見が内外の研究から明らかにされてくる、新型コロナについてわかってくる。また、私どももさまざまな研究を重ね、スーパーコンピューターを使ったり人工知能を使っていろいろな知見も重ねてきました。
そういう意味で、もちろん基本は機動的にやるべきだということでありますけれども、新型コロナについてわかっていることが少なかっただけに、次から次へと新しいそうした知見も重なり、また感染拡大を経験する中で、大きな方向を示すこの緊急事態宣言を新たに再び発出したときに変更するという判断をしたものでございます。
○塩川委員 そもそも機動的にということが趣旨であるわけですし、現実に七カ月以上も放置をしていたというのが実態であります。
要は、基本的対処方針を改定するというのは、緊急事態宣言が発出をされる、解除をされる、そのタイミングだけしかやっていないんですよ。ということは、緊急事態宣言に至らないようにするための措置を、政府としてどう取り組むのかといった方針が結局曖昧なまましているということになるんじゃないですか。緊急事態宣言にかかわるときしか出さないということは、緊急事態宣言にならないように政府として統一的な指針を示すということをやらないということに実態としてなっているんじゃないですか。
○西村国務大臣 五月二十五日の段階でその後の大きな方針はお示しをしておりますので、それに基づいて、専門家の皆さんのそれぞれの分科会での提言なども踏まえて、必要に応じて通知などを行ってきております。都道府県、それから経済界やさまざまな団体ともそうした情報を共有しながら対応してきておりますので、今回、大きな方向を変更する、大きな方針を示すという意味で新たに改定することとしたものでございます。
○塩川委員 自治体向けの通知、事務連絡文書は膨大にあるわけで、それ一つ一つ意味のあることだと思います。ただ、それを全体として統一的な指針を示すということが重要だ、それがまさに基本的対処方針であって、実際のこういった感染症対策、コロナ対策について自治体が主体となって取り組む、その際の基本的な、統一的な指針が基本的対処方針だということを改めて強調しなければなりませんし、そういう点でも、この分科会提言など、専門家の科学的知見が繰り返し繰り返し出されたのに、それを基本的対処方針に盛り込まなかったということは、科学的知見を国として軽視をしていたと言われても仕方がないのではないでしょうか。
○西村国務大臣 私ども、この間、専門家の、分科会の提言をしっかりと受けとめて、その時々に必要な対応、対策を、都道府県知事と情報共有しながら講じてきているところであります。
今申し上げたとおり、そのことについては、通知であったり、さまざまな形で連絡をとり合い、対応してきております。大きな方針を変更するという段階になったということで、これまでの知見の積み重ねもいわば全て含めて、今回改定をさせていただいたということでございます。
○塩川委員 科学的知見を軽視した国の対応が緊急事態宣言の再発出という深刻な事態を招いたという反省こそ必要だということを申し上げて、質問を終わります。
 新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域追加について政府の責任をただしました。野党は菅義偉首相の出席を求めましたが応じませんでした。
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域追加について政府の責任をただしました。野党は菅義偉首相の出席を求めましたが応じませんでした。













 今年は丑年、私は年男。一歩一歩着実に、結果を出せる年にしたいと決意しています。
今年は丑年、私は年男。一歩一歩着実に、結果を出せる年にしたいと決意しています。